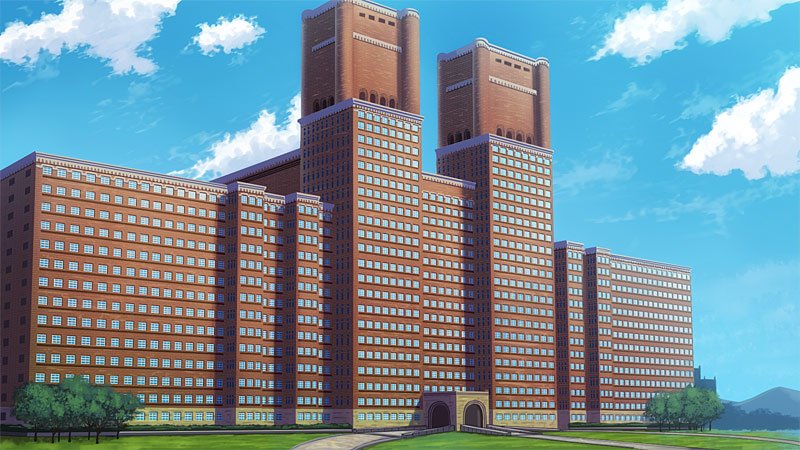|
 |
リアクション
●春の夜は人を……
アイビスの歌声が、火村 加夜(ひむら・かや)と山葉涼司、二人の元にも流れてくる。
彼女と彼はと肩を寄せ合い、夜の桜を眺めていた。
懇親会は、もう終わりだ。帰り支度をする姿も見えるが、歌声はまだ二人の頬をなでている。
それに、二人の夜はこれからといっていい。校長としての職務から離れられるまで加夜は彼を待っていたのである。
「涼司くんと夜桜見るの初めてですね……」
「そうだったな」
今日も忙しかっただろうに、涼司は加夜の前では安らかな顔をしていた。
「……疲れてないですか?」
「疲れてないと言えば嘘になるが、加夜といれば疲れは吹き飛ぶな」
そんな言葉、彼が他の人に言うことは決してないだろう。加夜の前でだけは、涼司は気障にも、少年のようにもなれる。
冷えた缶ジュースで乾杯。
「来年はお酒を飲みながら夜桜を見るのもいいですね。二人とも二十歳になってますし。酔ってる涼司くんも見てみたいかも」
「俺は……そうだな、加夜の魅力に酔っているほうがいいな……って、こういう台詞、俺らしくないか?」
涼司は笑った。そんな茶目っ気だって、やっぱり加夜限定の涼司なのだ。
「いえ、ちょっとくすぐったいけど、嬉しいです」
ねえ、写真撮りません? と加夜は提案した。
「夜桜をバックに、二人並んで」
ケータイ写真だけど……言いながら彼女は、もう自分の携帯電話を出して自分たちに向け、ベストショットを探している。
「別に構わないが」
「はい、撮りますよ。笑って……」
ピロン、と夢の世界でウサギが跳ねるような音がして写真が撮影された。
「良いのが撮れました」
加夜はホログラムで、撮ったばかりの写真を浮かび上がらせる。
はにかんだように笑む加夜、そして、写真を意識してやや硬い笑顔の涼司。
「この写真はお父さんとお母さんに送るつもりです」
唐突に加夜は言った。
「日本でも桜が咲いてるって写真を送ってくれたから、私も送りたくて。……一緒に送られてきたメールに、なかなか帰ってこないからたまには元気な姿の写真を送って欲しいってあったので」
「ちょっと待ってくれ、これ、送るって、本当に?」
「はい。送るためにって言うと涼司くん緊張しそうだから撮った後に言いました」
「お、おいご両親にはどう説明を……」
涼司の言葉は途端にたどたどしくなる。断じてやましい仲ではないとはいえ気恥ずかしい。
慌てる彼に、加夜は別の写真を映して見せた。
「ほらこれ、両親です。違う場所だけど、同じように桜を見てるって思うとなんだか嬉しくなりますね」
面白いことに加夜の両親は、さっき撮影したばかりの加夜と涼司によく似たポーズで映っていた。
桜の木の前で優しく微笑む母と、緊張した面持ちの父。
本当に、よく似ていた。
************************************
懇親会の終了が告げられ、ユマ・ユウヅキも席を立った。
「……終わりましたか」
教導団製の懐中時計を見る。気がつけばこんな時間だ。
なぜだか今日は、あっという間に刻が過ぎたように思う。とりわけ、藤谷天樹に問いかけられて以後は。
「ユマは……これから自身に何を求める?」
天樹の言葉だ。
塵殺寺院の為に生きていた時期がある。任務を果たすことがその頃のすべてだった。
寺院から逃れてからは、自分に良くしてくれた人たち……そしてクランジΘの野心を砕くために生きていたのだと思いたい。人身御供と言われようと、囮を志願したのは誰に命じられたからでもなかった。自主的にそうしたのだ。
けれど、それが終わった今は……?
思考が行き詰まってしまう。
見えない壁に両手を突いて、それを押しのけようとする気持ち。
押しのけられない事実。
そのとき、
「ユマ……少し、いいか?」
彼女は呼び止められ、顔を上げた。
大切な話があるんだ、と告げたのは―――クローラ・テレスコピウムだった。
時間が前後することを許してもらいたい。
ふたたびユマは一人に戻っている。クローラとの話が終わったのだ。
まるでそれを見越していたかのように、彼女の携帯電話が鳴った。
「遅い時間の電話ですまない。懇親会も終わった。もう身体は空いただろうか……良ければ少し会って話しをしよう」
柊 真司(ひいらぎ・しんじ)からの着信だった。
「……はい」
短く返事して、ユマは指定された場所に向かった。