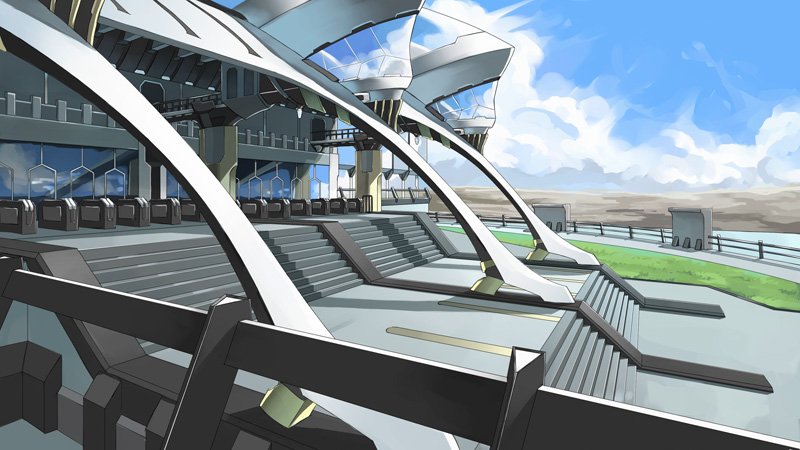リアクション
◇ ――遺跡の内部。後ろで束ねた黒髪を風になびかせながら、一人の男が倒壊して積み上がっている瓦礫を撫でている。 「やけに生活臭漂う遺跡だね。ん……この先は行けそうにないかな?」 周囲の状況をさして気にするでもなく、手馴れた様子で瓦礫に火薬をセットし始める黒崎 天音(くろさき・あまね)を、背後からブルーズ・アッシュワース(ぶるーず・あっしゅわーす)が制止しようと慌てて手を伸ばした。 「天音、どうやらこの遺跡には人が多く集まっているようだぞ。その瓦礫を爆破で排除するのなら、一言断りを入れ……」 言葉半ばの所で、天音が小気味良く指を鳴らした。その瞬間、セットした火薬が小規模な爆発を引き起こす。 掌で目元を覆うブルーズを横目に、飛び散る破片を気にする様子も無く天音は土煙の先を見た。 「……ちょっと、火薬が足りなかったかな?」 「うむ。単純に火力不足だ。加えて言えば、この先も瓦礫が詰まっているだけだがね……と言うよりも、何をしているのかね?」 天音の肩にバールのようなものを乗せる博士に、ブルーズが戦闘態勢を取るが、天音がそっと手を向けてそれを静止した。 今しがた気が付いたように、イロンVと、その周辺の集団に目を向ける。 「遺跡に巨大ロボットに博士に助手か。何となく少し懐かしいシチュエーションだけれど。イロンVの最大の弱点……見切ったよ」 意味深に微笑を浮かべながらイロンVを見上げる天音に、博士が眼鏡の奥から目を細める。 「ほう、興味深いな。是非とも聞いてみたいものだが?」 「まだ――そう、まだその時じゃないよ、博士」 微笑を携えたまま天音は、何故か衣服に付いた砂を掃っている助手に向き直る。 「君は……そうか。あの時と――同じ、なのかな。やっぱり、まだ諦められないんだね」 「な、何の話ですか、突然」 突然話を振られた助手が、僅かに表情を硬くした。天音の只ならぬ雰囲気と、何かを含んだ物言いに、少なくとも心当たりが無いわけではなさそうだ。 そのやり取りを見ていたブルーズが、助手の耳元で、そっと囁く。 「……あまり天音の話を真に受けん方が良い。ともすれば、心を透かされかねん」 言い終わると、赤い双眸で助手の瞳を、真っ直ぐに見つめた。ブルーズの表情には、同情と労いが入り混じったような複雑な表情が浮かんでいた。 何とも言えない表情を浮かべたままの助手の肩に軽く手を置き、天音に向き直る。 「お前が興味を持ったらしいのは分かるが、あまり要らぬちょっかいを出すな。物騒な事に巻き込まれかねん」 一通り満足したのか、遺跡の調査を再開し始めている天音に、ブルーズが声を掛けた。当の天音は、壁面の砂を払いながら、相変わらず顔に微笑を浮かべて軽く目を伏せるだけだった。 いつもの飄々とした態度の天音に、ブルーズが溜息を吐いた頃、その背後では不可思議な物体が蠢いていた。 それは――言い得て妙だが、モザイクだった。よく見れば、メイド服に身を包み、薄茶の髪を揺らす少女に見えなくもないが、注視すればするほどその姿は見えなくなっていく。 何やら黙々と作業を続けているモザイク少女を助手が見つめていると、突然そのモザイクが近づいてきた。 「あ、こんにちはっ。何かお手伝い、ありますか?」 光学モザイクに身を包んだ葉月 可憐(はづき・かれん)が、助手に笑顔で挨拶をする。が、助手には表情の変化は見えなかったらしく、戸惑いを浮かべる。 かろうじて、声色から敵意が無い事を汲み取った助手が、やや硬い笑顔と挨拶を返す。 「えっと、こんにちは。……よく見えませんが、これ、お持ちでしょうか?」 目を細めながら腕章を取り出す助手に「持ってないです!」と可憐が答えると、助手は『53』と書かれたそれを渡した。 その時、手にした腕章がモザイクに飲まれていく様子をしげしげと見ていた助手の視界の隅から、更に別のモザイクが現れた。ふいに、視界を全てモザイクで覆われたような錯覚に襲われる。 「大丈夫? 暑さに中てられたかなぁ?」 軽くかぶりを振る助手に、姿をモザイクで隠したアリス・テスタイン(ありす・てすたいん)が手を伸ばす。 「あ、大丈夫です。えっと、貴女もナンバーお持ちじゃないですよね、多分ですけど」 『54』と書かれた腕章を、モザイクの塊となっているアリスに向けて差し出した。再び、腕章がモザイクの中に飲まれていく。 「……えぇっと、そうですね。52番さんから武装の再整備に関して提案が有ったようなので、お手伝い願えますか?」 何とか、モザイク姿の二人に慣れたらしい助手がバインダーに目を落としながら可憐達の後ろを指差した。 いつの間にか、イロンVの横で52番――未沙と博士が話し込んでいる。 「53番、お手伝いに来ました!」 トテトテ、と駆け寄ってきたモザイクの塊に未沙が片眉を上げる横で、博士は動じる様子も無く一枚のメモを取り出した。 「今日は随分と可愛いお嬢さんが多いな……どれ、これを頼もうか」 「私が、見えるんですか? 凄いですねっ」 「何、単純にやましい映像に取り付くモザイクを見慣れすぎてな、今や自在に脳内補完が出来るだけの事だ」 物凄く駄目な事を平然と言い放つ博士の手から、可憐がメモを受け取る。メモの内容を一読して、可憐が小首をかしげた。 「腕部を曲げた状態で溶接しなおして、ミサイルポッドと機銃を乗せればいいんですか?」 「あぁ、強度を上げられないなら、せめて兵力だけでも、との事なのでな。それぐらいなら、まだ間に合う」 眼鏡の位置を直しながらそう言う博士の横で、未沙が頷く。 続けて、博士が近くにいた作業員を呼んで、適当に指示飛ばしていく中、それをフォローする形で助手が指示に対して細かい説明を加えていった。 その合間に、嬉しそうな声を上げる可憐を見て、アリスが微笑む。 (可憐、凄く楽しそう……と、かくいう私も結構楽しんでるけどねぇ) 周囲を見渡せば、ここに来る時に連れて来たシボラのジャガーが楽しげに作業員にじゃれついている。 通常のジャガーよりも大きなサイズにも拘らず、誰某構わず額を擦り付けるシボラのジャガーに、作業員たちはビクつきながらも顎を撫でていた。満足そうに顎を鳴らす声が聞こえる。 「さて、私も頑張りますかねぇ」 一人そう呟いて、軽く伸びをしたアリスは、遺跡の各所で何やら作業を始めた。 ◇ ――それぞれが、せわしなく作業を進めていく遺跡の片隅で、紫煙が漂う。 壁に背を預けたままの姿で、ノア・レイユェイ(のあ・れいゆぇい)は口元を覆う布の隙間から、シンプルながらも綺麗に作りこまれた銀の煙管に唇を当てた。ゆっくりと煙を吸い込んで、優雅に吐き出す。 「なぁ二クラス……どう思う? ホントにあんな鉄の塊が役に立つと思うかねぇ?」 咄嗟の改修を受けるイロンVを見ながら、ノアは隣にいるニクラス・エアデマトカ(にくらす・えあでまとか)に問いかける。 ニクラスは興味なさそうに、先をカットした葉巻を炙っていたが、やがてつまらなそうに口を開いた。 「役に立たんだろうな……どう考えても」 予想通りの回答に、ノアが苦笑する。半ば強引に、この集団に引き込まれた身の上としては、役に立とうが立たなかろうが面白ければどちらでも構わない――のだが。 「おぬしらにはこのロマンが分からんのか!?」 この男に関しては、そうでもないようだ。 悠々と『我関せず』を貫く二人に、その男――平賀 源内(ひらが・げんない)は銀色の瞳を輝かせながら、握りこんだ拳を向けた。 しかし、相変わらず反応の薄いノア達に源内は片眉を上げる。そして、冷ややかな視線を振り切るようにロングコートをたなびかせて、大げさにイロンVへ振り返った。 「おぉぉ、コレは凄いのぅ……コレが動くところを想像するだけでワクワクするのぅ……!」 両手をこれでもか、と広げながら源内は、感動を身体で表現している。 その姿に、ノアは紫煙と共に溜息を吐き出した。半眼の瞳が、全ての心情を語っている。 葉巻を銜え込んだニクラスの目元はサングラスに覆われている為に見えないが、さして変わりない気持ちだろう。 ふ、と――イロンVの各所を見ては感嘆の声を上げる源内の肩に、手が置かれた。 「いやはや、壮観壮観。やっぱ、巨大ロボって良いもんだぜ」 「そうじゃろう! あぁ、やはりわかるモンにはわかるんじゃな!」 突然声を掛けられたにも拘らず、源内は自らの肩に掛けられた戎 芽衣子(えびす・めいこ)の手をガッチリと掴んだ。 同じ志、同じ思考を持つ者の匂いを嗅ぎ取ったのだろうか。二人はまるで旧来の仲であるかのように頷きあった。 「盛り上がっていらっしゃる所、すみません。えーと、こちらをお持ち下さいね」 手馴れた手付きで、助手が腕章を配る。源内には『55』と番号が書かれた物を。そして、芽衣子には『58』と書かれた腕章が渡される。 遠目でその光景を見ていたノアの頬が、僅かに歪む。腕章を配っていた助手は、何の迷いもなくノアに『56』と書かれた腕章を差し出した。当然のように『57』と番号が振られた腕章が、ニクラスへ向けられる。 「えっと……55番さんの、お知り合いの方、ですよね?」 「知っているか知らないか、と聞かれれば……見知った仲だねぇ」 「一応、決まりなんで、持つだけ持っていて下さい。付けていなくても良いんで」 笑顔でそう言われ、やや深く息を吐きながらもノアは腕章を袖の中へと入れた。 二クラスは受け取らないつもりだったのか、手を伸ばさなかったが、「二クラス」とノアに短く呼ばれてから、やっと腕章に手を伸ばした。 「あ、っと、助手君?」 バインダーに何やらメモを取りながら、その場を離れようとする助手を、芽衣子が呼び止める。 そのまま振り返った助手にスタスタと歩み寄り、肩を掴んだ。 「ちぃっとばかし、頼み事があるんだがよ――フィオナ」 「……イエス、マスター」 そのままの姿勢で、芽衣子は待機させていたフィオナ・グリーン(ふぃおな・ぐりーん)を呼んだ。 豊満な胸をほぼ隠す事なく曝け出したフィオナの姿を見て、目のやり場に困る――よりも、その身体に纏う装甲に視線が移った。 「これは……また、その――凄いですね」 「そうだろう? 巨大ロボに勝るとも劣らない、このロリ巨乳……っと、じゃなくてだな」 コホン、と一つ咳払いをして、芽衣子は助手の耳元に口を近づけた。 「ええと、アレだ。こんなでっかいモン作れるくらいだから、さぞかし資金が豊富なんだろうし……うちのフィオナを立派にしてやっちゃァくれないもんかね」 「……と、申しますと?」 「このままでも十分格好良いし可愛いんだけどさァ、やっぱ改造って浪漫だろ? 好きに弄って良いから……駄目かね?」 その言葉に、助手はやや何かを思案した後――とりあえず、とばかりに『59』と書かれた腕章を芽衣子に渡して、博士を呼んだ。 |
||