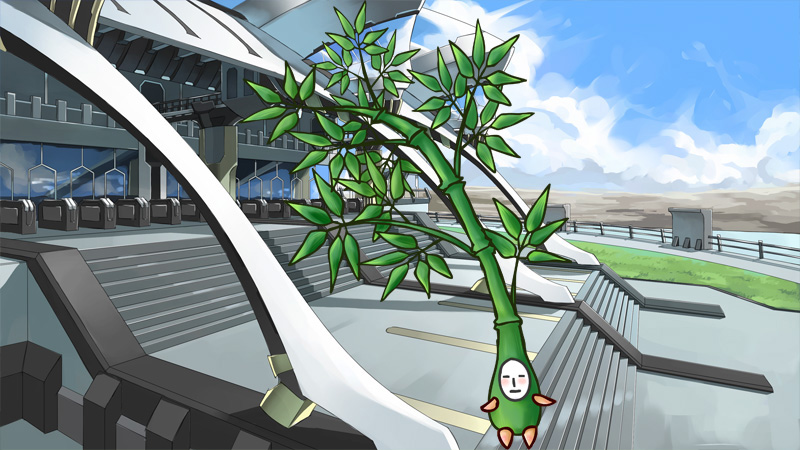リアクション
「あ、戻ってきた」
人混みの中、矢野 佑一(やの・ゆういち)はこちらへ駆け戻ってくるミシェル・シェーンバーグ(みしぇる・しぇーんばーぐ)の姿を見つけて、オープンカフェのテーブルから立ち上がった。
「ただいま、佑一さん、シュヴァルツさんっ」
「お帰り。ちゃんと短冊は渡せた?」
「う、うーん…。あのね、そうしたかったけど、できなかったの。笹飾りくんの近くにファタさんがいて、彼と会う人のこと見てて」
ここで言うファタとはファタ・オルガナ(ふぁた・おるがな)のことである。
15歳以下の少女が大好きと公言してはばからない彼女はミシェルがお気に入りで、会うたび何かとからかってくるのだ。
「女体化薬をもらいに行ったの見つかったら、何に使うのか訊かれちゃうかなぁ、と思って」
「そう」
それは正しい判断だと、佑一も思った。
ミシェルは薬を欲しがったことをからかわれると気にしたみたいだが、ファタはすぐにその薬が何に使用されるのか勘づいてしまっただろう。きっと一目散にこの場から遠ざかってしまったに違いない。
「しかしまいったな……ファタさんがついているとなると、ちょっと薬を手に入れるのは厄介かも」
薬は、できる限り穏便に、平和的に手に入れたかった。笹飾りくんに恨みがあるわけでも何でもないのだから。しかし、ファタに気付かれることなく手に入れるのが絶対条件である以上、こうなったら少々荒っぽくいかざるを得ないかもしれない。
ちら、と席についたままのシュヴァルツ・ヴァルト(しゅう゛ぁるつ・う゛ぁると)と視線を合わせ、お互いその結論に達したのを確認し合ったとき。
「えへへっ。薬はちゃーんと手に入れてきたよ、ほら」
ミシェルが少し得意げに、後ろに回していた手を持ち上げた。その手には、小さな瓶をつるした紐が握られている。
「そばに寄れなかったんじゃなかったの?」
「うん。困ってたら要さんとばったり会ってね、持ってるからってくれたの。自分はいいから、って。あの人、優しいよね」
そう言って、そのときのことを思い出してか、ミシェルは花のように笑った。
「……そう。よかったね」佑一は、頭をなでたくてうずうずしている手をこぶしにして、気付かれないようそっと後ろに回す。「あとで僕からもお礼を言っておくよ」
そのとき、彼の肩越しにシュヴァルツの手が伸びた。
「もらうよ、ミシェル」
「あ、うん」
「ファタは向こうか」
紐を指にからめ、シュヴァルツは独り言のようにつぶやきながらミシェルの来た方へ向かって立ち去った。
「……シュヴァルツさん、あの薬、何に使うのかなぁ」
人波にまぎれていく背を見送りながら、ぽつり言う。
「ひどいことには使わないって言ってたけど。女体化薬って、女の人になる以外、使い道ないよね。それともほかに使い道、あるのかなぁ。ねぇ、佑一さん」
ミシェルは真剣に言ったのだが。これから何が起きるか大体予想がついている佑一は、笑いをかみ殺すのに必死だった。
「まぁ、とりあえず席につこうか。のどは乾いてない? 何か飲み物でも頼もうか」
「はい、佑一さん」
ソーダフロートをかき混ぜながら、ミシェルは向かい側でコーヒーを片手に膝に広げた雑誌を読んでいる佑一をちらちらと盗み見ていた。
佑一との間が、何か、おかしい。ここ最近。
何がおかしいって……うまく言い表せないけど、何かが違うのだ。
さっきも放していてそう思った。あれ? って。あれ? 何かおかしくない? って…。
(でも、それが何かは分からないんだよね…)
普通に話せてるし。特に無視されてるとか、話はずされてるとかじゃないし。
(……う〜〜〜〜っ。こんなのやだよ。なんか、胸の中もやもやする)
もやもやして、なんだか悲しくなるのだ。
怖くてずっと目をそらしてきたけど、いつまでもこのままでいるのもつらすぎる。
そう思い、ミシェルは意を決した。
「佑一さん、なんか、おかしくない? 最近のボクたち。もしかして、ボクに何か怒ってる?」
その言葉に、佑一は持ち上げていたコーヒーカップをそのままソーサーに戻した。
「どうしてそう思うの?」
「だって……だって、おかしいって、感じるから…」
「――ごめん。僕のせいだね」
ついにきたか、そんな諦めが浮かんだ。佑一としては、このまま日が経てばうやむやになって、そのうち以前の自分たちに戻れているんじゃないかと思っていたりしたのだ。そうなることを半ば期待していたというか…。
だけどミシェルはこういう、人との距離感に敏感だから、いずれはこの日が来るんじゃないかとも思っていた。
佑一は覚悟を決めて、正直に話した。
以前、不用意に頬に触れたとき、その手をはずされて、それ以来なんとなく触れるのがためらわれるようになったのだと。
「そんな…っ! あ、あれは……恥ずかしかっただけで……嫌……だったわけじゃ…」
口にした瞬間、そのときのことを思い出して、カッとミシェルの頬が赤らんだ。
「うん、分かってる。ミシェルはそんなことをしないって。あのときも、頭の隅では分かっていたと思う。ただ、自分でも驚くくらいショックだったから。妙にためらってしまうというか……僕の問題なんだよ」
以前は何を考えて、どう思って、ミシェルに触れていたんだろう? それすら思い出せない。
「…………っ……」
ああ、これだったんだ、とミシェルも最近の違和感に思いあたった。
前は普通にあったふれあい――頭をなでてくれる手とか、背中をぽんぽんと叩く手とか、そういうの――が、なくなってしまっていたのだ。
もう二度と、あんなふうにしてもらえないの…?
――そんなの、いやだ。
「……いやだよ……佑一さん……」
「ミシェル?」
パッと席から飛び出したミシェルはそのまま駆けて行こうとし――踏みとどまって、振り返った。
「――ボク……ボクね、佑一さんに触れられるの、全然嫌じゃないよ。だからボクに触れるの、怖がらないで……お願い…」
じんわりと熱を持った目をギュッとつぶり、つぶやいたあと、ミシェルは再び走り出す。どこというあてがあるわけでもなく、ただ、前に走ることだけ考えて。
そして残された佑一は。
「……あー……やばいかも」
テーブルに、突っ伏した。
☆ ☆ ☆
そのころ、
ファタ・オルガナ(ふぁた・おるがな)は。
こちらへと歩み寄ってくる女に気付くと同時に妙な違和感を感じて、目をすがめていた。
乳白金の髪から覗く、銀色の瞳が印象的な女だった。左目は隠れて見えないが、右目だけで十分その意志強さは伝わる。
着ている物は、黒のパンツスーツだ。男物らしい。だから微妙にサイズが合っていないのが違和感の正体だろうか?
不躾ととがめられかねない視線で、ファタは女をきつく見据える。
なに、構いはしない。あきらかに女の目的は自分だ。
間違いなく、女はファタだけを見つめ、まっすぐ歩いていた。
その水晶をはめ込んだような銀の瞳――。
「きさま、シュヴァルツかっ!」
あと5歩も歩けば手が触れ合うという距離で、ファタが叫んだ。
「ほう? よく俺と分かったな」
シュヴァルツの顔が、ほんの少し笑み崩れる。
「う…」
まさか、いつも彼が近づくと起きるざわめきがしたから、などとは言えないファタだった。
まるで数羽の小鳥が下腹部で一斉に羽ばたいたような、なんともおちつかないざわめき。
それを隠そうとファタは両手を腰にあて、ことさらわざとらしくため息をついてあきれを表現して見せた。
「まったく……なんじゃ? その姿は」
効果的になるよう、頭の先からつま先までジロジロ見て、フンと鼻で笑う。
「まさかおぬしに女体化願望があったとはなぁ。夢にも思わなかったぞ。どうじゃ? その姿、記念に写真でも撮っておくか?」
携帯ならここにあるぞ、ほれほれ。
ケケケっと意地悪く笑って、手の中のそれをプラプラ見せる。
だが、ファタの主導権もここまで。
ふいとそむけたすぐ鼻先に、シュヴァルツがいきなり左手をついた。
「!」
反対側に右手もついており、気付けば彼の腕の中に閉じ込められてしまっている。
「ち、近いぞ、おまえ」
豊満な女の双丘が、ファタのすぐ目の前に迫っていた。
「うれしくないのか? 女が好きなのだろう、おまえは。あいにくとあの薬は女体化はしても幼女化はしないようで、少女にはなれなかったが」
壁に、肘までつけたシュヴァルツは、ここぞとばかりにファタの耳元で深くささやく。
必死に顔をそむけ、できる限り距離をとろうとしていたファタは、その言葉の意味を理解した瞬間、距離をとろうとしていたことも忘れてパッと彼に向き直った。
「……まさか、わしのためじゃと?」
わしが少女が好きと知って、二度と男の体に戻れない薬を飲んだのか?
ファタ自身、気付いているのかいないのか。一切の仮面がはがれ落ちたその顔に、フッとシュヴァルツの目がなごむ。
「なに、心配するな。この姿でも十分おまえを満足させられる」
……そんな心配なぞだれがするかーーーーッ!!
そうしかりつけようとしたファタだったが、あいにくそれはかなわなかった。
シュヴァルツの唇がふさぎ、言葉を吸い取ってしまったからだ。
やわらかさが意外だった。今は女の唇だから当然なのかもしれないが。
なだめるように両手が脇に触れ、なでさすっているのも心地いい。くやしいが、どうみてもシュヴァルツは女の扱いに慣れていた。
しかしかといってこのまま流されて、おめおめと主導権を奪われ続けるつもりもない。
「!」
シュヴァルツは閉じていた目を開くと唐突にキスをやめた。
口端からたらりと血が流れる。
「やはり、おまえはとんだ山猫だ」
「……ふん。痛い目にあいたくなくば、二度とこんなことはせぬことじゃ」
ここぞとばかりに冥府の瘴気を発動させ、威嚇を図るファタ。しかしシュヴァルツはどこ吹く風とばかりに受け流した。
「どうかな? 舌に噛みつかれなかったことは、十分脈ありだと俺は思うのだが」
「次は噛みちぎってやるわ!」
「次か。では、試してみよう」
もう一度。
近づく唇を受け入れるべく、ファタが口を開く。2人の唇が再び重なりかけた、そのとき――。
「ミシェル!?」
ぐきっと音がするくらい、ファタはシュヴァルツの顔を右にずらした。
「……なんだ? ファタ」
「今そこの路地を、ミシェルが向こうへ走り抜けて行ったのじゃ。泣いておるようじゃった」
そしてファタは走り出した。もちろん行く先は、ミシェルの消えた路地だ。シュヴァルツのことはすっかり頭から抜けてしまったのか、振り返りもしない。
「やれやれ。これでもまだミシェルが上か」
ふーっと息を吐き出したあと。
シュヴァルツもまた、ファタのあとを追って走り出したのだった。