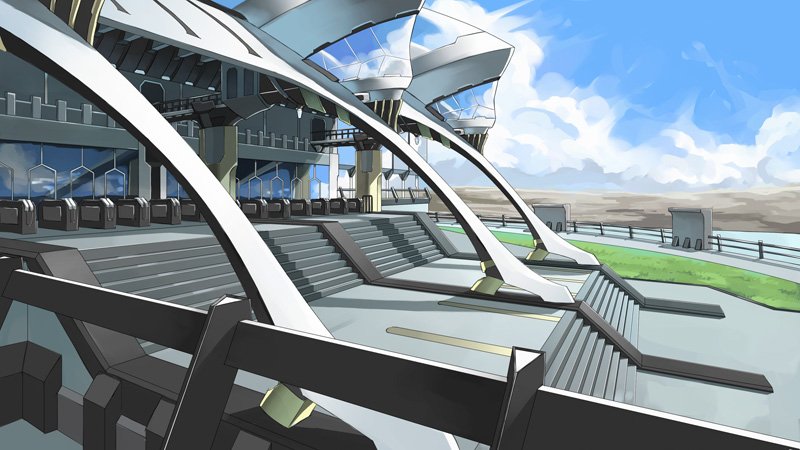リアクション
● 茂みに隠れながら標的を待つ気分というのは、猟犬のそれを想像させた。 「おい、まだかよ」 草木にカモフラージュした迷彩塗装のマントを上から被った京太郎が、政敏に訊く。 「まー、待ってろって」 彼は不敵な笑みを浮かべながら、そう答えた。 すると間もなく、森の暗がりから人影が二つほど見えてくる。最初はぼやけた影だったものの、こちらに近づいてきているのだろう。次第に影ははっきりとしてきた。 「こ、怖いわねー、真人……」 「そうですね」 セルファ・オルドリン(せるふぁ・おるどりん)と御凪 真人(みなぎ・まこと)だった。 二人は互いに微妙な距離感で、つかず離れずに歩いている。真人は平然としてスタスタと歩いているが、セルファはそうではない。その手を彼の腕に伸ばそうとして、しかし顔を紅潮させて諦める、といったことを、たどたどしく繰り返していた。 「……はー…………罪作りな男だねぇ」 狐のように目を細くした京太郎が、小馬鹿にした態度で言った。 「でも、あれでいてモテるんやで、あいつ」 それに対し、社が補足する。 「なに? 世間じゃあ、あんなのがモテるってのか? どう考えても、オレのほうが良い男だろ、おい」 京太郎は本気でそう信じているようだ。 政敏は呆れた目を彼に向けた。 「お前がそれで良い男だったら、俺はもうハーレムになってるよなー」 「てめ、それどういう意味だよっ!」 「いい加減にしときなさいって、あんたたち。ほら、もうあの二人組、行っちゃうわよ」 身を乗りだした京太郎を中心になだめるように、まゆりが二人の間に割って入った。 二人も状況も把握して、とりあえずその場は落ち着きを取り戻す。 「このやろー、絶対にオレのほうがモテるって証明してやるぜ。今度はナンパで勝負だ、ナンパで」 「望むところ……って言っとけばいいか?」 「……いちいち熱を冷ますなよ、お前」 言いあいながらも、真人たちからバレないように茂みを移動する二人。 それを後ろから見ながら、カチェアはくすくすと笑っていた。 「どうしたの、カチェア?」 まゆりが訊く。 「いえ、青春だなぁって思って」 カチェアの目は、まるで子を見守る母親のようだった。 (うーん……この娘はこれが活動写真みたいなものって信じてるのよね) そう考えると、後ろめたく思わなくはない。 ただまゆりは、そんなことを真剣に悩むような女ではなかった。むしろそのほうが、彼女の好奇心や喜びを増長させるものとなる。 (ふふふ〜……おもしろくなりそう) いやにやと笑うまゆりに、カチェアが首をかしげた。 「まゆりさん、どうかしましたか?」 「なんでもないわよ〜、なんでも〜」 そうこうしているうちに、すでに京太郎たちは準備を進めていた。 カメラを彼らが用意すると、セルファたちの前にお化けが現れる。 「きゃああぁぁ!」 セルファが可愛らしい悲鳴をあげておののくと、そのスカートがひらりとはためいた。茂みの中からカメラだけをのぞかせて、ファインダー越しに彼女の下着を狙う。 ――パシャッと、音が鳴った。 「ばかっ、シャッター音ぐらい消しとけ!」 京太郎が仲間の男子生徒を叱責する。 男子生徒は慌ててシャッター音を消して、再び撮影に戻った。 なにせセルファはその性格上からも、人気が高い。この場でたくさん撮影しておけば、後々にいい稼ぎとなるだろう。 「お化けに驚く少女! そんな時だからこそ起こるハプニング! 微かに見える聖域! はい!戴きました! ありがとうございます! 刻ませて戴きましたよ! 俺の心のハードディスクに!」 社が興奮して叫ぶ。 なんでも彼のポリシーか、カメラではなく直視してセルファのチラリズムを鑑賞しようとしているようだった。 「だああぁっ、お前もうるさい!」 「そう言わんといてや、京太郎。ちゃんと写真は撮れとるんやろ?」 「枚数は多いにこしたことはないからな」 「お化けにも頑張ってもらいたいところだぜ」 と、そんなことを話しながら、次々と写真を撮っていたそのときだった。 「うんうん、楽しめましたか?」 「ああ、もちろん――」 会話のなかに見知らぬ声が混じっているのに、京太郎は気づいた。 恐る恐る振り返ると、そこに腰を落とす一人の少女がいた。にこにこと笑顔を浮かべて、ほふく前進状態で撮影している京太郎や政敏たちを見おろしている。 年は12歳程度といったところか。幼い子供に見えるその少女はしかし、どことなく妖艶な光を瞳に湛えていた。 首からさがっているのは金の十字架である。そのことから、少女がシスターであることを京太郎は悟る。が、政敏が、彼女を見て頬を引きつらせていた。 「せ、先生……」 「ど〜も〜。こんなところで何やってるんですか? 政敏さん」 「いや、別に……」 政敏は誤魔化すように顔を逸らす。が、もちろん、そんなことで少女が誤魔化されるはずもなかった。 彼女は坂上 来栖(さかがみ・くるす)。少女のなりをしているが、イルミンスールでスクールカウンセラーをしている、れっきとした大人なのだから。 「皆で楽しい事したいってのは素晴らしい、セクハラも……まぁ良しとしましょう。だから『先生』は見なかった事にしようと思ってます」 来栖は理解のある先生口調で告げた。 ついでに言えば、彼女は元々、男性であった契約者だ。死の間際、契約者となって生き延びたわけだが、何の手違いか女体化してしまったことで今に至る。そのため、確かに彼女は彼らの気持ちが理解できるのだった。 しかし―― 「でも、だ。話は変わるけどあなた達はお化けじゃん? 私は先生の前に『えくそしすと』じゃん?」 それとこれとは話は別とばかりに、来栖はすっくと立ち上がった。その胸の十字架が、森に挿しこむ月の明かりを受けて、静かに煌めく。 笑みの奥に、底冷えする気迫を感じた。 「……あとは分かるな? さ、鬼ごっこでもしましょうか」 「…………」 京太郎は政敏と目配せした。 こんなところで終わるわけにはいかない。それは、他の男子生徒たちも同じだ。瞬時に、彼らの意思が一つの共同体となる。 「うらぁっ!」 「へ…………」 瞬間、京太郎が来栖のスカートをめくり上げていた。 「きゃあっ!」 先ほどまでの殺気にも似た迫力からは想像できない、可愛らしい声を来栖があげる。 「いまだ、逃げろ!」 その隙に、京太郎たちは茂みから飛び出していた。 「どこに逃げられるおつもりですか?」 「げっ、真人……」 だがそれを、いつの間にか脅かし役のお化けを退治していた真人がふさいだ。彼は杖を掲げ、問答無用とばかりに天のいかづちを放ってくる。 なんとかそれを避けたが、逆側の脱出路をセルファがふさいでいた。 「あんたたちねぇ…………」 彼女はいまにも爆発しそうなほど顔を赤くして、怒りに燃えていた。その手に握られているのは一つのカメラ。足元には気絶している工作員。 どうやら、悪事はすべてバレたらしかった。 「当然、ボコボコにされる覚悟は出来てるんでしょうね!」 「どわあああああぁぁ!」 強化光翼の翼を生やしたセルファが、剣を振りかざす。その剣線を避けて、京太郎たちはなんとか暗がりのなかへ逃げこんだ。 「まったく、夢安は反省の色がまるでないですね」 「あいつは一度、海の底に沈めたほうがいいのよ。…………ってか、あたしの写真を抹消させないといけないわ。ひとのパパ……パンツ撮ったこと、後悔させてやる!」 「……撮られたんですか?」 「そこは気にしないでよ!」 背後から真人たちの声が聞こえてくる。 しかも、いまさらになってであったが、森のあちこちから悲鳴や怒号が聞こえてきた。女性たちに追いかけられている仲間の姿を遠くに見る。 どうやらバレたのは真人たちに、だけではないようだ。 「くそ……どうするよ?」 「どうするって、そりゃ……」 人目につかないように出来るだけ遠くへ逃げようと、京太郎たちは考える。 だが、そんな提案は虚しく霧消した。仲間の工作員たちが、こちらに向かって逃げて来たのだ。 「たいちょう〜〜〜〜!!」 「おまえら……こっち来るなよ!」 しかも、隊長などと言っているため、京太郎が首謀者であることはすぐに分かった。 女性たちは狙いを京太郎へシフトチェンジして追いかけてくる。もちろん、京太郎たちはその前に脱兎のごとく逃げ出していた。 「夢安、こっちだ!」 政敏の指示に従って、彼が事前に用意していた逃走ルートを駆けてゆく。 すると、やがて見えてきたのはある一定の高さに集中して枝が生えている場所だった。 「飛べ!」 一斉に地を蹴る京太郎たち。 と――直前に京太郎たちを見ていたため、枝が見えていなかった女性たちは、その枝に思い切り服を引っかかった。 「な、なによこれ〜〜っ!!」 「この時を待っていた!」 「うおおおおおおぉぉぉ!」 枝には水気を含ませてあったのだ。 無数の枝に引っかかってなかなか動けない上に、服は破けるは濡れてスケスケになるわで、女性たちにとっては散々であった。当然、男性陣にとっては眼福に他ならない。無事だった数少ないカメラで、頬を赤らめている恥ずかしい姿を写真に収めた。 しかし、彼女たちがその罠から脱出するのも時間の問題だろう。 「夢安……」 「な、なんだよ」 彼は普段からは見られない真剣な顔で京太郎を見つめた。 「俺はお前を守る盾になる。いいか。お前だけでも絶対に生き残るんだ。俺たちの、男たちの夢を、決して諦めるんじゃない!」 「政敏……」 政敏はそう言って、京太郎にカメラを手渡した。 彼は女性陣を見つめる。まさか、と京太郎が思ったが、そのまさかを政敏はやろうとしているのだ。 「吾輩も……吾輩たちも……政敏殿に続くであります!」 「ふっ……この俺様自身の写真を守るためなら、命も惜しくはない!」 ノールと変熊が、それに賛同して、京太郎を守るように前に進み出た。 「いくぞおおおおぉぉ!」 そして彼らは、女性陣へと突貫する。 水で濡れて、服もところどころが破れた女性たちは、男どもが入ってきたことで羞恥に顔を真っ赤にする。それは恥ずかしさと、そして怒りも含まれていた。 「きゃあああああぁぁ!」 「なにすんのよ、あんたたち!」 右ストレートからアッパーにひざ蹴りまで、政敏たちはボカスカと殴られる。 だが女性たちと身体が密着して、彼らは心なしか、だらしない笑みを浮かべていた。ノールに至っては、殴られていることに快感を覚えているらしく、恍惚に表情が歪んでいた。 (あいつら――) 京太郎はその場から背を向けて、彼らの思いを背負ったように走り去った。 その胸にあるのは一つの思い。 (なんて、なんて羨ましいことを!!) 自分もあの中に混じって乳を堪能したかった。 と、思いながら――京太郎は仲間たちと別れたのだった。 ● |
||