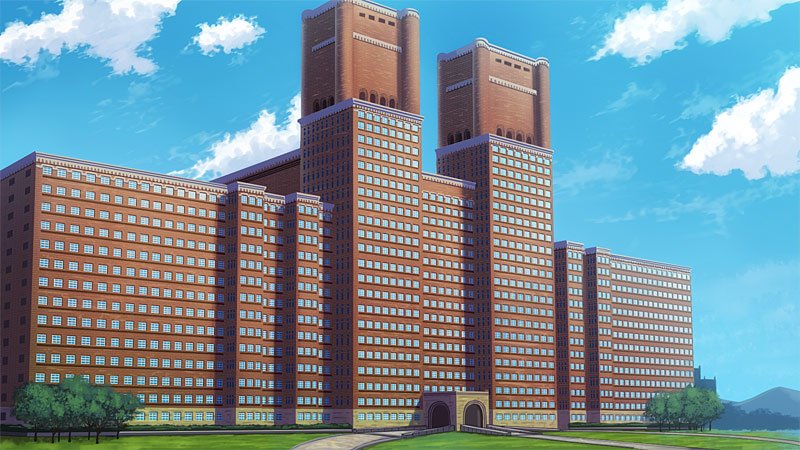リアクション
************************************ 楽しい夜桜だが、楽しむ者ばかりではない。 人をふと感傷的な気分にさせるものだ。夜の桜は。 (「……駄目だ、見つめていると、辛い」) 樹月 刀真(きづき・とうま)は桜から視線を外した。一時は咲き誇ってもやがて散る……この花の宿命を思うと、胸にナイフを突き刺されたような気持ちになる。 この夜、刀真は半ば強引に漆髪 月夜(うるしがみ・つくよ)に連れられ懇親会の会場にあった。 居場所がない――彼はそう感じている。 桜を眺めれば心が痛み、かといって他の来客と会話を交わすような気にもなれない。ここにいる意味を見いだせないのだ。 仕方がなく手持ち無沙汰で、魂の抜け殻のようになった身を桜の下に置いている。片手には銀の杯があり清酒で満たされているが、それを呑むでもなく、ただ掌で温めているような状態だ。そして彼は、他に向けるところがない、という理由だけで月夜のほうを見ていた。 「どうしたの?」 なにか考え事? と月夜が問うた。 何も、と回答しても良かったが、それはあまりに冷たい気がして、 「酒のつまみ……」 作ったのか、と、酒瓶と共にならぶ一品料理を刀真は指した。いずれも酒によく合うものばかりだ。オクラのなめたけ乗せ、山椒豆腐、あぶりサーモンにマグロの中おち、ジャガバター等々。 「料理が下手な私だけじゃ難しいから、白花と一緒に作ったんだよ」 月夜は告げた。封印の巫女 白花(ふういんのみこ・びゃっか)については花見に行くこと自体も誘ったのだが、二人だけでいってらっしゃい、と断られたのだった。その際月夜は、「頑張って」とも言われた。 (「気を遣ってくれるのは嬉しいけれど……」) 本当は、まだ二人きりになれる自信は月夜にはなかった。 「刀真!」 月夜は彼の腕を取った。刀真を強引に振り向かせると、彼のネクタイをぐいとつかみ自分の顔に急接近させた。 そして、刀真と唇を重ねた。 「……! 何を!」 熟睡中に揺り起こされた男のように、刀真は唇を離すとまばたきした。 今初めて、そこに彼女がいることに気づいたかのように…… 魍魎島の決戦、その場の勢いで月夜は刀真にキスをした。 島から帰還して以後現在まで、刀真はそのことを一度も口にしなかった。 けれど月夜は、意識してしまう。むしろ刀真が何も言わないだけに気になった。どうしても、二人きりだと緊張してしまうのである。 会話が途切れ生まれた空白を埋めるように、月夜は杯を重ねた。成人ではあるがそれほど飲めるほうではない。だけど今は酒の力を借りたかった。 「……あれ?」 見上げた桜の枝が二重に見える。いや三重だ。ぼやけて揺れている。 もう、どうとでもなれ。 「刀真ぁ〜」 我知らず甘えた声で月夜は刀真に抱きついていた。 どうした、と告げた刀真は、月夜の体温を感じてたじろいだ。 接して思い出したというのか、脳裏に、魍魎島での口づけの記憶が蘇ったのである。あのとき確かに月夜は、『剣』ではなく『女』だった。 生温かい風が心をかき乱すのか、それともこれは春の夢か。 (「剣は剣士の命だ、だから剣そのものである月夜は、俺の命かそれ以上のものだと言い切れる。……でも、それは剣士としての俺で、男としての俺は?」) 刀真の腕は、いつの間にか月夜の背中にまわされている。 誰も見ていない。周囲には誰一人いない。 ここで彼が獣に帰したとて、誰がそれを責められよう。 (「しかし」) つまみの由来を聞くべきではなかったかもしれない。いや、そのおかげと言うべきだろうか。 刀真はこのとき、もう一人の剣の花嫁……白花のことを思い浮かべたのだった。 すると急速に、刀真をまどわせていたものは萎んでいった。 「刀真……?」 月夜はこのとき、彼に頭を撫でられていることに気づいた。それが徐々に穏やかな気分を招き、いつしか月夜の瞼はぴたりと閉じられたのである。 (「気持ちが良いから……このまま寝ちゃおう……」) 今の月夜には無理な話だった。「頑張って」と伝えたときの白花の気持ちを推し量るのは。 『初めて会った時から刀真さんの隣には月夜さんがいました、二人はいつも一緒でお互いを信頼し合って戦っていました』 このとき白花の眼はそう訴えていたのだ。 『刀真さんを欲しいと思ったことが無いと言えば、嘘です……でも二人の間に割り込みたいとは思いません』 その意思があっての「頑張って」だったのである。 けれどそこまで酌み取れというのは、今の月夜には難しい話だ。 |
||