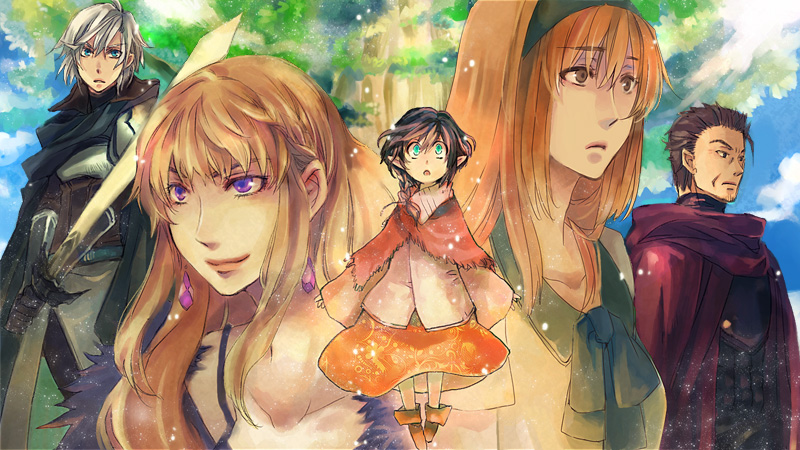リアクション
◇ ◇ ◇ 天井が砕ける。 遺跡の内部が崩れるという寸前、ヴリドラは、強引に尋人を突破し、リューリクの元へ戻った。 そしてリューリクとトゥプシマティを連れ、崩れる遺跡から、弾丸の如く一気に上昇する。 天井からなだれ込む大量の水。 柱は押し潰されて次々に折れ、遺跡はあっという間に水で埋まった。 ――遺跡の水没に飲まれたと思っていたのに、気がつけば、水面にいた。 『門の遺跡』の全ての舞台は、何と水に浮くようになっていて、それに押し上げられて、水面まで脱出できたのだ。 内海の下にあることで、ドワーフは最初から、もしもの水没の備えをしていたのだろう。 この分なら、遺跡からドワーフ坑道に水が流れ込まないような備えくらいは当然してありそうである。 凄まじい速さで、ドワーフ坑道入口から飛んで来たヴリドラに、リューリクの援護を契約者達に阻まれていた一体が合流する。 張り付いていたエヴァルト・マルトリッツを払い落とすと、合体して三頭龍となる。 だが、既に遅かった。 腰が抜けている。 全ての力をあの一撃で使い果たし、水没から引き上げられて、意識があるのが不思議だった。 同じ舞台の上に、リューリクがいる。 空から、別の舞台から、自分に向かって来る周囲を見渡して彼女は笑う。 「今度は思い切りいけそうね」 水圧が塊のように落ちてくる水没の中でも決して自分を放さなかったカサンドロスが、動けない自分の前を、動かない。 「ジール!」 誰かが自分に何かを叫ぶのが聞こえたが、何と言っているのか解らなかった。 「立ちなさい、ジール。 誰も殺したくないのなら」 放たれたその声は、不思議な程身体の中に響いた。 固まった手に、添えられる手。 固まっても尚、離さなかった剣を、その手が握る。 怪訝そうに、リューリクが自分を見た。 ジールは、両手で剣を握り締めた。 「――我が名に於いて請う。 己が羨慕せしものを悉く凍て付かせ我が物とせん――此処に謹んで御名を呼び奉る」 リューリクの立つ背後の舞台から、エレナ・リューリクの呪文の詠唱が終了する。 「リヴァイアサン!」 召喚された竜が、リューリクの全身に氷のブレスを吐いた。 トゥプシマティが防御を張って、それを防ぐ。 「人に護られることに慣れているわけね……狙いを変更すべきかしら」 それを見た佐那が呟いた。 リューリクは自分を護らない。それは護衛の仕事だからだ。 ならばリューリクとトゥプシマティを引き離し、リューリクを孤立させれば。 同様に、この時点で未だ一頭龍のヴリドラも、他の契約者達が間に入り、分断させようとする。 リューリクがヴリドラを気にした瞬間を狙い、背後の死角から、熾天使化によって三対の光の翼を持ったコハク・ソーロッド(こはく・そーろっど)が飛び込んだ。 リューリクは、ヒュッと剣を振る。 攻撃を受ける為の動作ではない。コハクの槍先は、何か、突破できない絶対的な力のようなものに弾かれた。 「わたしを貫ける刃など、存在しないわ」 「そう、かな」 元より、コハクの攻撃は、リューリクに届くことを始めから想定していなかった。 コハクの一撃は、リューリクを倒す為ではなく、隙を作る為のもの。 ただ死角を狙ったのではなく、ジールがリューリクの死角になるように誘う、それはジールの一撃に繋げる為のものだった。 はっ、とリューリクは振り返る。 それでも、その剣は、リューリクの身になど、届かないはずだった。 ――お願い。 半ば目を閉じ、感覚だけで走りながら、ジールは剣に祈った。 この人を、ここに呼んでしまったのは私なの。 だからお願い。どうかこの人を殺さないで。 剣が、リューリクの身体を貫く。 「リュ……!!」 がば、とトゥプシマティが走り寄ろうとして阻まれる。 「リューリク様っ!」 がく、とリューリクは膝をつく。 その身体から、血潮が溢れない。ただ硬直して動けない。 「あなた、何者」 ジール達に問いかける。そしてふと笑った。 目を閉じ、倒れる。 エレナが、横たわるリューリクに歩み寄る。 「……もしも、わたくしが貴女のようであったなら、わたくしは己が国を繁栄に導くことが出来たやもしれません。 ……ですが、苛烈なのは、わたくしの性に合いませんわ」 同じ名前を持ち、けれどこんなにも、自分とは違う。 リューリクが生きている内にこの言葉を投げかけたなら、彼女は何と返して来たろうか。 半ば放心に近く、リューリクを見下ろしていたジールが、その身を貫く剣に手を伸ばす。 「抜いてはならぬ」 カサンドロスがその手を止めた。 「で、も」 「今は、この剣の力が、皇帝陛下の周りを覆って抑えている。抜けばこの方は復活する」 目を見開いて、ジールはリューリクを見る。 「で、でもそれじゃ、どうしたらいいの? このまま?」 美羽が言った時、頭上から影がさした。 ◇ ◇ ◇ 何故か彼女の龍は、ドワーフの坑道入口ではなく、その場所に直接空から向かおうとした。 龍が自分には解らない何かを感じ取り、勝手に動こうとする時、それが自分の為にならないことであるはずがないことを、龍騎士達は知っている。 なので手綱を引かずに任せてみれば、『門の遺跡』は破壊され、残骸が水面を漂って尚続くリューリク帝達の激闘が、今リアンノンの眼下でついに決着がつこうとしていたのだった。 意外な人物を見て、トゥレンが驚いた。 「リアンノン?」 黒龍が水面近くに下降し、リアンノンが飛び降りる。 リアンノンを下ろした黒龍は、一旦上空へ舞い上がった。 「リューリク様をお迎えに参上した」 短く言えば、カサンドロスやトゥレンは、すぐに納得する。 倒れるリューリクの手に、リアンノンは指輪を嵌めた。 その瞬間、リューリクの姿が消滅する。 指輪だけが、ころりと地に転がった。 「リューリク様!」 トゥプシマティが悲鳴を上げた。 リューリクが消滅した。 絶望に、がくりと両膝をついて崩れ込む。 ――――――「そう。記憶が無いのね」 真っ白になっていく意識の中で甦る、一番初めの記憶。 ――――――「これからは、わたしの為に在り、わたしの運命となりなさい」 あの方の存在そのものが、私の命の指針となった 私はあの方の為だけに生き、私の全ての能力を、あの方に捧げた 私の身は、砕けた石版の、その欠片のひとつしか残されていなかったけれど リューリクが消滅した今、トゥプシマティもまた、生きる理由を失った。 意識の糸が途切れて、トゥプシマティは倒れる。 助け起こした呼雪が、息があるのを見てほっとした。 「リューリク帝は、どうなったの?」 ヘルが訊ねる。 「リューリク様は、自らの力によって、その姿を実体化させていた。 力を封じたので、実体化も無くなったのだ。今はこの指輪の中に封印されている」 「そっか……」 リアンノンの答えに安堵する。 姿が消えたことで、トゥプシマティは存在が消滅したと勘違いしたようだが、完全に消滅したわけではなかった。 「リューリク様にお戻りいただかなければならない。 私はこれで失礼する。また改めて、御礼に伺わせて頂く」 アンドヴァリは、この封印の力がどれくらいもつか解らないと言った。急がなければならない。 リアンノンは手短に挨拶すると、黒龍に乗って霊峰オリュンポスへ向けて飛び立つ。 「やれやれ。ひとつ解決と」 はあ、とトゥレンが息を吐く。 カサンドロスは、無言のまま、ジールを見た。 |
||