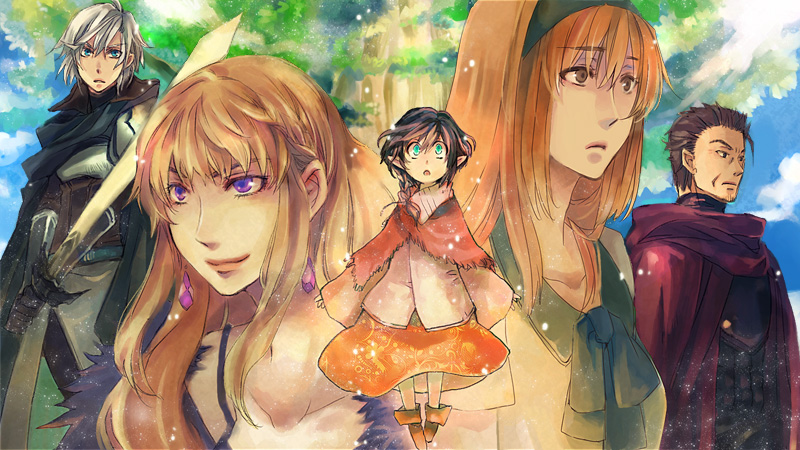リアクション
第15章 絶対なる隔絶
死の門からナラカへと進む者達を見送って、小鳥遊 美羽(たかなし・みわ)達は、パラミタに残った。
巨人アルゴスの死骸を、そのまま放置して行くことが、美羽にはできなかったのだ。
「アルゴスを埋葬してあげたいの。手伝ってくれる?」
パートナーのコハク・ソーロッド(こはく・そーろっど)やベアトリーチェ・アイブリンガー(べあとりーちぇ・あいぶりんがー)は勿論、トオルや磯城(シキ)にも声を掛ける。
漆髪 月夜(うるしがみ・つくよ)を背後に背負って、ハルカは表情を曇らせた。
「此処に、なのです?」
「駄目かな? 最期の場所に埋めてあげたいから、この近くに……」
「……此処、は、ちょっと、怖いのです」
躊躇いながら、ハルカがそう言うのに首を傾げる。
「怖い?」
此処に来る時、ハルカは特に怯えてはいなかったはずなのに。
「うまく、言えないのです」
「そうだな。この場所への埋葬を認めるわけには行かぬ」
割って入った声に振り向けば、黒龍騎士リアンノンが立っている。
「此処は、エリュシオン皇帝の墓所。
彼には敬意を表するが、それでも、この地に皇帝以外の者の埋葬を許すわけにはいかない」
「じゃあ、どこならいいの?」
「墓所の外であれば、何処でも」
「美羽、森林地帯まで降りてはどうでしょうか。
最期の場所からは少し離れてしまいますが、景色が美しいところに埋葬してあげたいです」
「……うん、そうだね」
ベアトリーチェの提案に、美羽も頷いた。
「埋葬もよろしいですけど、ハルカはすぐにでも、病院に行くべきだと思いますわ」
御神楽 陽太(みかぐら・ようた)のパートナー、エリシア・ボック(えりしあ・ぼっく)がそう言った。
「蘇生に成功はしましたけれど、体が二つになりかけていましたのよ。
一度ちゃんと、お医者様に診て貰うべきですわ」
「それはそうだね」
美羽や、樹月 刀真(きづき・とうま)らも頷く。
「ハルカも、巨人さんを埋めてあげたいのです」
「力仕事だもん。……ちゃんと回復したら、改めて皆で、お墓参りに来ようよ」
ね、と美羽は笑いかける。はい、とハルカは頷いた。
ところで、と、エリシアはハルカを見た。
正しくは、ハルカの頭の上。突っ込むべきなのかどうか、実はずっと迷っていたのだが。
「そのおんぶお化けは何ですの」
月夜は、ずっとハルカを背後から抱きしめていた。
「……だって」
月夜は拗ねたように、キュッ、とハルカに回す手に力を込める。
「つくよさん、ハルカはもう大丈夫なのです」
ごめんなさい、ありがとう、と言うハルカに、うん、と頷く。
出会った頃に比べれば、もうハルカも大きくなったのだし、子供扱いみたいなのはよくないかなとは思うのだけど、でも、とても怖かったのだ。だから仕方ない、そう決めた。
ハルカは月夜のするがままにさせていて、呆れた顔をしたエリシアも、無理に離れろとは言わなかった。
皇帝の墓場から暫くは、岩石地帯が続くが、その下は森林地帯となっている。
見晴らしの良い場所を選んで、美羽達は、巨人アルゴスを埋葬した。
墓標の代わりには、彼の武器だった槌を使った。名前を刻む必要は無いだろう。
「ありがとう、アルゴス……」
ハルカを助けてくれたアルゴスに、美羽は感謝してもしきれない。
友達を、失わずに済んだ。
けれどその代償はとても大きいものだったと解っている。
丁重に葬り、皆で摘んで来た花を供えた。
車両の駆動音が聞こえた。
道に戻ると、丁度世 羅儀(せい・らぎ)の運転する装輪装甲通信車が通りかかるところだった。
美羽達の姿を見つけて、羅儀は車を止める。
「どうしたんですか」
と、窓から顔を出して、叶 白竜(よう・ぱいろん)が訊ねた。
白竜と並んで、墓前で敬礼し、黙祷を捧げながら、最後の巨人の死に、羅儀はショックを受けていた。
ちらりと横を見れば、表情には出さないが、白竜からも、静かな怒りが伝わって来る。
「……代償が、多すぎます」
此処に来るまでに、天音とのテレパシーでのやり取りで、大体の状況は把握していた。
ニキータが、教導団から聖剣を帯出したことも聞いている。
何か補佐に回れることがあればと此処へ来たのだが、いきなりの悲報と出くわしてしまった。
(今は、聖剣アトリムパスが無事に正しく使われるのを祈るしかないが……)
「……『死の門』に向かいます。
得られる情報があるか確認しつつ、そこで待機」
白竜の言葉に従い、後に続いて歩きながら、羅儀は最後にもう一度巨人の墓を振り返る。
「……なんていうか……本当の意味での騎士だったんだな」
呟きに、白竜は応えを返さなかった。
埋葬に加わらなかったポータラカ人の三毛猫タマが、拘束された朝永真深の側で丸くなっている。
一緒に車に乗ってきたトオルがタマに「見張りご苦労さん」と労う横で、白竜は猫の振りをしているタマを抱き上げ、「状況は?」と訊ねた。
死の門の前に、黒龍騎士リアンノンが立っている。
彼女は特に害成すことをしなければ、契約者達が此処に留まっていることをとりあえず黙認しているようで、口出しはして来ない。
トオル達が此処に戻って来たのは、アルゴス埋葬の間、この場に待たせていた朝永真深を回収する為で、一旦この場を後にするつもりだった。
「君が、『死の門』の管理の責任者ですか」
「そうだ」
白竜の問いに答えるリアンノンには念の為、自分がこの門を通る意志が無いことを伝えておく。
「私は、犠牲にできる命というものは一つも持っていません。
……自分の命が、何かの代償になるほどの価値など」
その言葉に、リアンノンはふと微笑んだ。
「僭越なことを言わせて頂くが、貴殿の命の価値を決めるのは、貴殿ではない」
「……」
「それは、貴殿の隣にいる彼であったり、友人であったり、貴殿に関わる人々が決めるものではないのか」
白竜の隣で、羅儀が肩を竦める。
じろ、と一瞬そちらへ視線をやってから、白竜はもう一度リアンノンを見た。
「……それでは、君は……この門は、どうなのです?」
◇ ◇ ◇
『死の門』の前。
巨人アルゴスの死後、ニキータのパートナーが聖剣を運んで来るのを待つ間で、
大熊 丈二(おおぐま・じょうじ)は、新たに門番となったリアンノンに、話を聞いてみた。
「死の門について、幾つか話をしてくださいましたが」
リアンノンは、丈二の疑問に幾つかは答えたが、最も重要な点については秘して語らなかった。
「テオフィロス殿と都築中佐が、強制的に死の門を潜らされたのであれば、生を取り戻すには、死の門を逆から出る必要があるのでは、と愚考します。
この考えは、正しいでしょうか?」
リアンノンは、いいや、と首を横に振った。丈二は、ぎゅ、と拳を握る。
「……では、死の門の秘密とは何でありますか。
自分は、二人を生還させたく思うのであります。
もしも、秘密を知ることで、二人を生還させる手段を得られるなら、また、聞くことで、自分が所属を離脱する必要がないなら、そして、彼等を救出に行くことを阻まれないのであれば、秘密を教えていただけませんか」
リアンノンは、丈二の話を聞き、ゆっくりと溜息を吐いた。
「貴殿が、彼等を救う為にそれを知りたいと言うのなら、話す必要は無いと考える。
『死の門』の秘密を知ることで、彼等を救う術にはならないからだ」
丈二は言葉を失った。
「だが、個人的に、貴殿に礼を言わせて欲しい。
テオフィロスの為に、親身になってくれて感謝する」
はっ、と丈二はリアンノンを見た。
同じ龍騎士、二人は知り合いだったのだろうか。
「貴殿の誠意を信用し、口を滑らせよう。
就任間もなく、私は、未だ門番としては未熟なので」
そう苦笑すると、リアンノンは背後にする門を見た。
あちこちにヒビの入った門は、後ほど、ドワーフに修繕を依頼するのだという。
「先刻私が言ったことは、偽りではないが、真実でもなかった」
その言葉に、丈二は瞬く。
「死の門の門番は、特例的に、何を必要ともせずに門を開ける力を得る。
だがこの力を行使することは禁じられている。私も名誉にかけて、絶対に使うことはない」
驚く丈二の表情を受けながら、リアンノンは説明の言葉を探す。
「……まず、この門を開くには、正しくは、『命』を必要とするのではなく、『死』を必要とする。
この違いが解るか」
丈二は頷いた。
つまり、此処にいる全員の魂を少しずつ集めて鍵にする、というのは不可能、ということだろう。
「死は覆せるものではない。
高貴なる者も下賤なる者も、死は等しい。実は、死す者の貴賤など関係ない」
「では何故、死の門を開けるには、高貴なる魂が必要だと謳うのでありますか」
「無論、門を使わせない為。
死の門の門番の務めは、その開閉ではない。決して開けさせないようにすることなのだ」
『死』とは、絶対の隔絶である。
生の世界と死の世界は行き交えるものではない。
行く者にも、残る者にも、二度と戻れないという覚悟が必要な、それが『死』だ。
「門は、ナラカ側に扉は無い。一方通行なのだ。
こちらから開けても、向こう側から開かれる道はない。行けば、戻ることは出来ない。
ナラカとは本来、そういう場所だ」
現在、パラミタ地表から、ナラカへ至れる穴が存在するが、可能な限り早急に、塞ぐ手段を講じる必要があるだろう。そうリアンノンは続ける。
「この地はナラカに近過ぎる。
この門も、元来はそうした穴を塞ぐ為に作られたものという。
完全に遮断することは、巨人族の技を以ってしてもできなかった。
故に、門と成して番人を立て、更に歴代の皇帝によって永遠に護られる聖地となったのだ」
「では、この門からナラカに行った彼等は、生きていても、戻る術は無いということでありますか」
「本来であれば。
現在は、フマナとシボラにナラカに通じる穴がある。
だが、そうしてナラカと繋がっていることは危うい。
交わるべきでない世界と交わることは、世界を滅ぼす」
「世界が滅ぶ?」
「死の力は強大だ。
パラミタとナラカが容易に繋がれば、パラミタはナラカに侵食されて行き、やがてナラカに沈むだろう。
死の世界を望み、徒に門を開けることで、ナラカに侵食されるのを阻止することが、死の門の門番の務めなのだ」
故に、『死』によって門が開かれることは秘せられた。
識る者は、黒龍騎士とユグドラシル、門の修繕を専門とする一部のドワーフの他は、ほんの一握りだ。
選帝神もその一握りの中には入らず、皇帝すら、未熟な内、就任してすぐにはそれを知ることはないのだった。