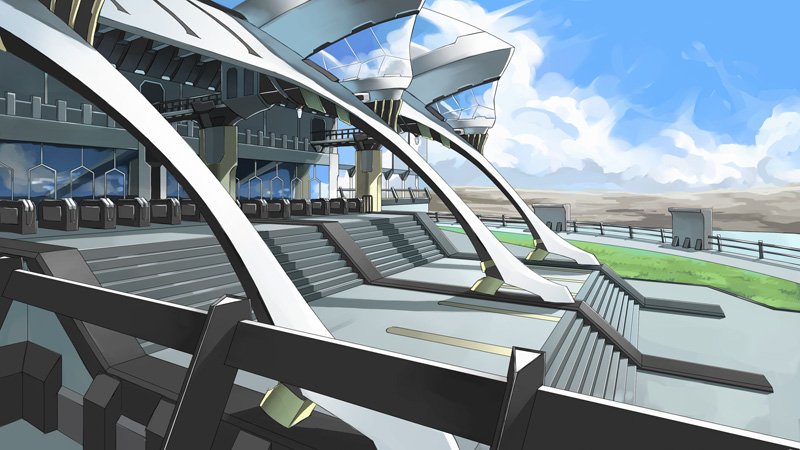リアクション
● 瞬撃。 そう言って過言ではない攻撃が、白銀 昶(しろがね・あきら)に迫る。 昶はしかし、ギリギリまで目を逸らさなかった。引き付けて、引き付けて、相手がかわせないような位置にきたとき、初めて動きを開始する。 シャギーのかかった黒髪。生意気そうな、強気で吊り上がった瞳。頭から生えた、ピンと尖った黒狼の耳。まさしく狼の獣人。 クオルヴェルの集落出身ではないが、昶は狼の獣人そのものだった。 ゆえに、そのスピードも驚異的だ。攻撃を仕掛けてきた相手にも、負けず劣らない。敵の眼前で、昶は相手を飛び越えて背後に回った。 振り抜かれた刃は、昶の影を斬り裂くのみ。 しかし、敵はそれに動揺を走らせることなく、冷静に状況を見極めて、体をくるっと一回転させた。 そしてスタッと、スマートに地に降り立つ。 「…………」 白い髪。白い戦闘服。そして、白い仮面。すべてを純白で覆った男だった。 頭からは、やはり白い狼の耳が生えている。この男も、獣人。ただし、昶とは耳も髪も、衣服の色さえも正反対だった。 武器は刀。 「……やるな」 ひと振りの長刀を手に、男は冷然とした声を発した。 「おまえもな」 二人は互いを見つめ合う。 だが、そこに憎悪や殺意はなかった。むしろ、どこか心地好い感覚のする、高揚感が支配している。自然と、口角が持ち上がり、笑みを作るほどに。 「昶……」 二人の空間から少し離れている位置で、清泉 北都(いずみ・ほくと)が声をかけた。 実際の歳よりも幼く見えそうな、小柄な少年。昶とパートナー契約を交わした契約者だった。 「手出しは無用だぜ、北都。手を出しちまったら、『狼の試練』じゃねえ」 「別に手は出さないけどさ。無茶だけはしないようにね。後始末が大変だから」 「後始末かよ。ちったぁ、他人の心配を……」 「よそ見をしている暇はあるのか?」 「!?」 聞こえたのは、すぐ傍だった。 とっさに身をかわさなければ、おそらくは当たっていただろう。 振り抜かれた刃が、その衝撃波で大地をえぐった。飛沫のように散った土が、昶の頭を打つ。 「ったぁ……くそっ! いきなりなんてひどいじゃねぇかっ!」 「油断大敵、という言葉を知らないのか」 「うっせぇっ! そっちがその気なら、こっちだってなぁっ!」 本気を出す――と言いたいのか。 昶は二刀の刀を構えた。西シャンバラ代王理子の名が銘打たれた刀である。片手で持つにはちょうどよい、軽さと強固さを兼ね備えた武器。 男の刀をひと振りで受け止めると、もうひと振りでその側面から応酬をかけた。 「っ!」 「どーだぁっ、らぁっ!」 金剛力の力が、軽い刃であっても桁違いのパワーを生み出す。 男は刃を受け止めるが、そのパワーに押し切られるまま、吹き飛ばされた。さらに、スピードに乗って昶の攻撃は続く。 男の速さと反応速度も大したものだ。昶の二刀流の軌道を的確に読み取り、そのすべてをたった一刀で受け止めていく。 すげぇ。すげぇぜ……。 昶の心臓がバクバクと脈打った。激しく、鼓動を繰り返す。血液が沸騰するように滾る。熱い。なにもかもが。視界も、刀を振るこの指先さえも。 これが、狼の血の成せる技か。 徐々に高揚感が熱湯のごとく沸き立ち、昶を包み込んでいく。 しかし、男がぎらりと眼光を光らせた。 「なっ!?」 次の瞬間には、昶の刀はその一本を弾き飛ばされていた。 それがきっかけとなる。昶の心臓が少し落ち着いてきた。 やばいところだった。このままだと、血に溺れちまうところだった。 獣人は常人よりもはるかに高い身体能力やスピードを有しているが、それは自分の中の獣の血が成せるもの。血に溺れてしまうと、獣に心を支配されてしまうのだ。 「…………」 「え?」 勝負を続けようとした昶の前で、男は刀を鞘に戻した。 「ちょ、お、おいっ! なんでだよっ! まだ勝負は……」 「勝負はついている。お前は、自分の血に勝ったのだ」 「…………血、に……?」 「そうだ。俺の役目はそこまでだ。これ以上は無益な戦い。そして、俺の魂はそれを望んではいない」 「…………」 男の声音は有無を言わさぬものだった。 いや、仮面の奥から覗く眼光すらも、昶にそれ以上の言葉を継がせない。 「いけ、狼よ。お前の試練はまだ先がある」 「でもこれ以上は……」 「それはこの『狼の試練』とは限らん。お前には、お前の道がある。それが試練。それが、お前の歩む試練の道だ」 男はそれだけ言うと、言い残すことはないというように踵を返した。 だが、昶は、 「あ、あのよっ」 その背中を呼び止めた。 振り返ったその表情は、仮面に隠れて読み取れない。だが、それは昶にとってさして重要ではなかった。ただ、聞きたいことがあったのだ。 「名前。……名前は?」 「…………ファラン」 それだけ言うと、男は――ファランはその大広間の部屋を出て行った。 しばらく待って、 「終わった?」 北都が聞く。 「ああ。終わった」 昶は、弾き飛ばされた一本の刀を拾って、そう答えた。 ● 「お、こんな所に封印されている入り口があるぞ。入ってみるか」 きっかけはそんな一言だった。 それがこんな形で厄介事を巻き込むなんて、佐々木 弥十郎(ささき・やじゅうろう)は思っていなかった。 「うおおおおぉぉっ!」 気合いの入った雄叫びをあげて、飛びかかってきたのは数名の獣人たち。 みな、そこらの獣人には負けず劣らない猛者ばかりだった。武器もそれぞれ。戦斧、長剣、槍、鞭、弓矢、あげくに棍棒やモーニングスターまで持ち出す輩もいる。 「来い。相手にとって不足なしだ」 そんな猛者たちの勝負を受けるのは、佐々木 八雲(ささき・やくも)。 弥十郎の兄であり、強化人間でもあり、パートナー契約を交わした相手でもある男だった。 ぼさぼさの銀髪。鍛え抜かれ、引き締まった肉体。端整な顔立ち。とある過去の事件から、左眼は失っているが、その鋭い目つきは依然として健在である。 八雲は容赦しない。 『正々堂々』と戦う事は信条かつモットーとして掲げているが、手加減をするつもりは毛頭なかった。 真澄のマシンガンを片手に、 「はああぁっ!」 獣人たちの咆吼さえも吹き飛ばす叫び声で、引き金をひく。 降り注ぐ弾丸の嵐。獣人たちは撃ち抜かれて倒れる者もいるが、武器を巧みに使って弾をはじき、接近してくる者もいる。強さもそれぞれ。格好もそれぞれ。 八雲は敵の刃を避け、マシンガンに次なる弾薬を詰め込んで、再び撃ちまくった。 「弥十郎。さぼるなよ」 「わ、分かってるよ……」 兄から叱咤を受けて、弥十郎も戦闘に加わる。 全能龍、妖艶龍、勇猛龍、清純龍、無垢龍。五匹のドラゴンを巧みに操って、彼は自分の手は汚さずに敵と戦った。ただ、もちろん攻撃は避けねばならないため、動き回るのは必至なのだが。 そのうち、しばらく戦い続けて――。 どれくらいの時間が経っただろう。 弥十郎は精神感応で兄に話しかけた。 『今ので何戦目くらいだっけ?(ゴアアァツ、とドラゴンが吠える声)』 『1、2、3、……いっぱい。忘れた(だだんっ、だんっ、とサブマシンガンの音)』 『兄さん、頭まで筋肉になった?』 『いやいや、女の子なら覚えるんだけどな』 『そう言ってたら、なんか強そうな女性がでてきたよぉ』 『ははは……これは。情熱的だな。口説いてくれるなら嬉しいが』 女戦士さえも現れて、戦闘は混戦にもつれ込んだ。 さすがに八雲たちも疲れてくる。もう、勘弁してくれと、思い始めた。 そして――よく見ると、獣人たちがかすかに透けていることにも、八雲は気づき始めた。 ははぁ、なるほど、と彼は一人で納得する。 だから彼は、次に挑んできた相手に対して、 「そっち霊体じゃん。こっちはまだ生身なんだから、少し休ませてよ」 そう言って、休憩を要望した。 「元気でたら、相手すっからさ」 「……なにを身勝手なことを」 これまであまり喋らなかった獣人たちが、そうやってぼやくように口を開く。 ただ、八雲だって馬鹿ではなく、言い返すべき言葉はあった。 「あんたも、若い時そう言われたんじゃない?」 「…………」 「ね、だからお願い。ここは一つな」 「……はぁ」 獣人たちはみな座り込み、八雲が持ってきた休憩セットでお茶に甘んじた。 幽霊のくせにお茶が飲めるのか、と八雲は思ったが、どうやら幽霊とはまるで構造が違うらしい。普通に物にも触れられるとのこと。 茶が美味いと、爺さんみたいなことまで言い出す始末だった。 おなじくお茶を飲みながら、弥十郎が聞く。 「兄さん、ところで帰り道は?」 「わからん」 自信満々に、八雲は言いのけた。 |
||