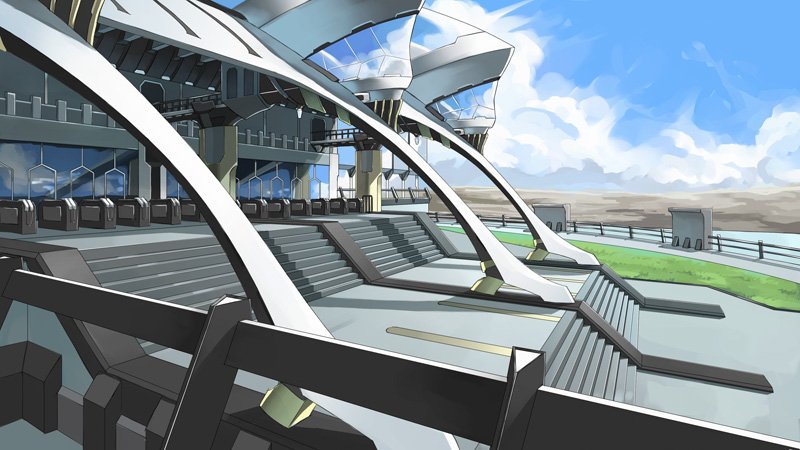リアクション
第1章 キノコ狩りツアーは各所開催中? 2
「くんくんくん……くんくんくん」
「わんわん……はっはっはっ……わんっ!」
「こうしてると、なんだか犬の散歩みたいだねー」
「そうですね……ここ掘れワンワン、でしょうか?」
のんびりとした少女たちの声が、サンドワームの巣の中で響いた。一人は眼鏡をかけた知的な娘。もう一人は小柄で大きな藍色の瞳を輝かせる娘だった。
スパッツに通常よりも短いミニスカートという、脚線美を存分にあらわにした姿の小柄な少女は、歩くたびにツインテールをぴょこぴょこと揺らしてる。
そんな少女に、目の前で犬耳……ではなく、狼耳を生やした少年が振り返った。
「散歩じゃなくて、探索だっての」
「そうそう。キノコなら、匂いもあるんじゃないかなぁ、てね」
狼耳の少年につられて、犬耳の少年も振り返った。こうして見ると、まるで兄弟のようにも見えるのだから微笑ましいところである。
小柄な少女は笑いながら少年たちに答えた。
「大丈夫、大丈夫。ちゃんと分かってるもん。伝説と言われる「太陽のキノコ」を手に入れるために、超感覚で獣耳を生やして探してる。もちろんちゃーんと分かってるよー」
「本当か? 散歩散歩って、楽しんでるようにしか見えねぇけどな」
「……それもあるけど」
「おい」
「きゃー、男は狼なのよー、昶っち」
「本物の狼獣人に言うか、それ」
少女――小鳥遊 美羽(たかなし・みわ)と白銀 昶(しろがね・あきら)のそんな無駄な掛け合いを見ながら、犬耳の清泉 北都(いずみ・ほくと)とベアトリーチェ・アイブリンガー(べあとりーちぇ・あいぶりんがー)は微笑ましそうに笑っていた。
どんな場でも明るくできるのは、ある意味で美羽の長所であった。もちろん、その原動力が楽しいこと大好き! で動いているのは否定できないところであるが。
そして、往々にしてそれらに付き合わされるのはベアトリーチェ、といったところなのですが、今回は少しばかり事情が違っていた。
「それにしても、その情報って本当なのか? 眉唾もんって気もしないではないけど」
「ふふーん、これでも、情報提供者のことは知ってるつもりだもん。お金のために嘘をつくような人ではあるけど、悪い嘘はつかないよ」
「……と、いうわけなので、ぜひともその『太陽のキノコ』を調理したいのです!」
怪訝そうに尋ねた昶に、美羽とベアトリーチェは自信満々に答えた。美羽が普段から得意げなのは不思議でないとして、どうやら今回、気合を入れているのはベアトリーチェのようだ。
「伝説……伝説の食材……ふ、ふふふ……腕がなりますよ〜」
「手に入れたら、ぜひ佐々木さんにも調理してもらいたいところだね」
「みんなで料理したら、ぜったい楽しいよー!」
ベアトリーチェは怪しそうな恍惚の顔を浮かべ、今から調理のことを楽しみにするメンバー。はたと、そこで北都が足を止めた。
「くんくん……これ、もしかして」
「キノコの匂い、見つけたの!」
「うん、多分、これだと……」
と、北都の声が遮られたのはそのときだった。
地響きにも似た振動が起こり、足場がぐらつく。それは、どうやら前方からやってくる巨大な影が起こしているようだった。
「げえっ……サ、サンドワーム!?」
やはり、というべきか。それは地中を這う巨大生物であった。
まるで北都たちの道を遮るように、ずずずずと音を立てて進行してくる巨大生物。予想はしていたが、どう対応しようかと北都は思考を巡らせた。が、その横で、不気味な音が聞こえてきた。
「え、カチャ……って」
「ふ、ふふ……そうですか。私の料理を邪魔しようと言うのですか」
眼鏡の奥の両目が不気味に光り、両手に握られるは魔道銃が二丁。笑みを浮かべるのは、あの大人しく知的なベアトリーチェ・アイブリンガーであった。
「そのようなことは、させません!」
普段から想像もつかぬほど、ベアトリーチェは果敢にサンドワームへと立ち向かった。敵の突進を避けて、横に飛ぶベアトリーチェ。引き金が絞られると同時に、雨のような散弾がサンドワームの体躯を穿つ。
「私も、まっけないんだから〜!」
ベアトリーチェに続いて、美羽は光条兵器を手の内に生みだした。飛び上がった彼女は、刃渡り2メートルはあろうかというほどの巨大な大剣を握って、サンドワームへと頭上から振り降ろす。
サンドワームは、まるで暴走するホースのようにばたばたと暴れまわり、美羽たちを吹き飛ばさんとしてきた。だが、連続して放たれる剣撃とベアトリーチェの銃弾に、敵を更に追い詰める。
そうこうしているうちに、たび重なる傷を与えられて、さすがにサンドワームも疲弊してきたのだろう。美羽たちから背を向けると、敵は逃げ去っていった。
「私の料理魂を邪魔しておいて、その程度で済むとでも……」
「お、おちついてベトリーチェちゃん! 追いかけなくていいんだってばっ」
いつもははしゃぐ美羽がベアトリーチェを必死でなだめる姿は、ひどく珍しい光景だった。
「昶……ベアトリーチェさんに対する料理の話題は、気をつけようか」
「同感」
今後のための教訓として、二人は肝に銘じた。
●
キノコといえば、古来より滋養強壮その他もろもろ……人体に影響を与える代物として有名であろう。そのせいかどうかは分からないが、誰が言い出したか、パラミタでは「伝説のキノコを食べれば身体は大きくなる」という噂が立っている。恐らくは、地球のとあるゲームの影響もあるのであろうが、真偽のところは分からなかった。とはいえ、真偽の云々は関係なくとも、その効果に引き寄せられる者は少なからずいる。
サンドワームの巣の中で、やる気に満ちて探索をしている
雨宮 七日(あめみや・なのか)も、そんな噂に誘われた一人であった。
「ふふふ、ようやく……さんざん人の事をちっぱいだの板胸だの蔑んできた連中を見返す機会が巡って来ましたよ……!」
「気合入ってるなぁ」
「あったりまえです! 何としてでも身体の大きくなるキノコを手に入れ、ぼんきゅっぼんのないすばでーに!」
のんびりと感想を漏らしたパートナー、
日比谷 皐月(ひびや・さつき)にそう言い放って、七日はずんずんと先に進んだ。使い魔のコウモリや使役されるアンデットたちがキノコを探す姿は、なかなかにシュールだ。
先を歩く七日の、白に近い鮮やかな銀の髪はひらひらと靡き、もともと紅玉のように赤かった瞳が、炎を灯して更に熱を増している。そして、その身体に目を移せば、彼女の言うように残念な体つきをしているのがすぐに分かった。
身長もさほど高いとはいえず、どちらかと言えば低いほうだ。無論、胸は自分でも言うとおり大きくなく、むしろ、本当にあるのか、と疑問に思うほど平板な胸だった。
「にしても……ちっせーのって、んな気にする事なのかね」
七日に聞こえないほどの声で、皐月はぼそりと呟いた。
確かに、七日の身体は年頃の娘としたら残念な方ではある。とはいうものの、決してそれが魅力的でないとは直結しないと皐月は思っていた。むしろ、その珠のように白く透き通った肌や、華奢な体つきは、可愛らしさと相まってとても魅力的である。少なくとも、皐月はそう思っていた。
もちろん、それを口に出すことはないが。
「ん……なんですか、皐月」
「いや、なんでもねーよ」
「……なんでもないって顔じゃないですね、それは」
皐月の視線に気づいて、七日はじっと彼を見つめ返した。こういうとき、無駄に鋭いのは七日の困ったところだ。
「ふん、どうせ、何をそんな、無駄なことを気にしてるんだって思ってるんでしょう? これだから女心の分からない皐月は。……あ、ちなみに皐月と書いてスペシャルクズと読みます」
「スペシャルいらなくないか……?」
皐月のツッコミを気にすることなく、七日は言葉をつづけた。
「いいですか。女であればやっぱりせっくしぃ〜な身体を欲しいと思うのは当然なのです。それに、先ほども言いましたが、ちっぱいだの板胸だの、馬鹿にした連中を見返さなくては」
「そういうもんか?」
「そういうもんです」
あまりにも自信満々に言われて、皐月はそれ以上は何も言わなかった。所詮、男である。女の七日が言うのであれば、そういうものなのだろう。
すると、ふいに七日は顔色を陰らせた。
「それに……寂しいんですよ」
「寂しい?」
「パラミタに来た1年で皐月は背も伸びたと言うのに……私は、生まれた時からこのままですし。…………置いてけぼりは、御免です」
静かな口調でそうつぶやく七日は、少しだけ哀しそうだった。
普段はあまりこういった寂しげな顔を見せない彼女だ。皐月は何も言えず、彼女を見つめ続ける。やがて、彼女は少しだけ朱に染まった顔を隠すように、いたずらな笑みを浮かべた。
「だ、だから、ぼんきゅっぼんっになって、皐月を誘惑してやるのです! ふふふ……見とれてしまっても、知りませんよ」
「……ま、期待しとくかな」
「あ、その顔は信じてない顔ですね! まったく、低能はこれだから……」
それからもぶつぶつと自分を罵る七日を見ながら、皐月は気づかれないような薄い微笑を浮かべていた。今でも見とれてるんだけど……という言葉は、今は、口にしないようにしておこう。
それにしても、である。
「オレの聞いた話だと、ここにあるのは太陽のキノコだったと思うんだけどな」
恐らくは七日の探しているものは見つからない宝探しだと思うが、それはそれで構わない。気が済むまで、付き合ってやる覚悟だった。パートナー契約をしたときから、それはきっと、変わらない。
「皐月、何をぐずぐずしてるんですか。早く行きますよ」
「ああ、今いく」
皐月は、きっとこれからも変わらない、毒舌で小さくて華奢な少女の背中を追いかけた。
●