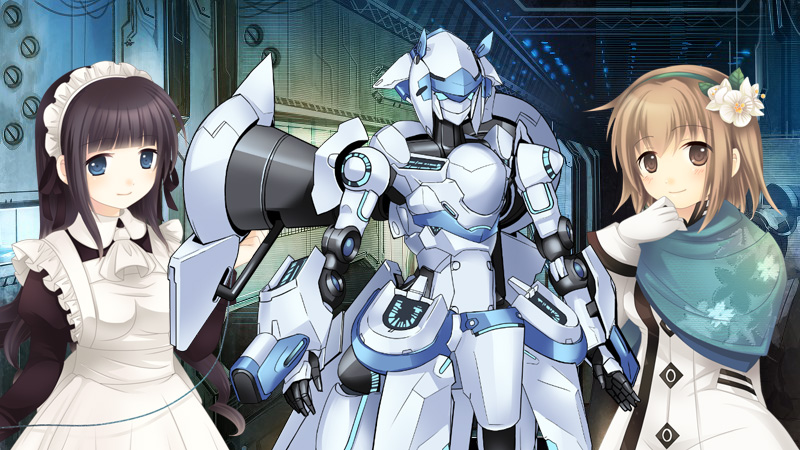リアクション
* * * (ここからゲーム開始……だな) シャンバラの学生が出たところで、校長と二人きりになる。 「なぜ俺がロイヤルガードって分かった?」 「あれ、そうだったの? 別に、ただの『例え』として出してみただけなのに」 「…………っ!」 「ふふ、『ゲーム』はあなたとあたしが出会ったときからもう始まっているのよ」 互いの「利用価値」を見極めるためには、まず相手のことを知らなければならない。そこからもう駆け引きは始まっているのだ。 「じゃあ、アカデミーを一通り案内するわね。このままお茶したいのなら、そっちでもいいけど」 「いや、ちゃんとこの目で見ておきたいからな。説明は頼むよ、エルザ校長」 今度はこっちの番だ。 「さっきの子は、F.R.A.G.の一員だよな?」 「あの目がキリってして背筋がすっとしてる子がロンドンで話したダリアちゃん。第一部隊の隊長よ」 天学高等部の生徒と同じくらいの年齢だろうか。 それが隊長とは。 「見えるかしら?」 窓の外を見ると、地中海上空を飛び交うクルキアータの姿があった。 「あの山の向こう側が、F.R.A.G.の本部よ。この島には、アカデミーの生徒とF.R.A.G.のパイロット達しかいないわ」 「枢機卿は?」 「マヌエル君はヴァチカンから指示を出すくらいで、滅多に来ないわ。第二特務が彼の秘書を兼任しているから、彼女が連絡役になってくれてる」 「第二特務?」 「特務というのは、F.R.A.G.の中で自由行動権を持つ――言ってみれば諜報員よ」 ということは、シャンバラに潜入している、あるいはしたことがある者がいるのかもしれない。 「あら、聞きたいことがあったら遠慮なく聞いていいのよ?」 不敵に微笑んだまま、正悟を見上げてくる。 本当に、読めない女だ。 外へ視線を向けると、紫や赤ではない、白のクルキアータの姿が見えた。 「ふふ、お出かけかしらね?」 「あの白い機体は何だ? 明らかに他の機体とは違うが」 「第一特務ミス・アンブレラ専用機、【アスモデウス】。『七つの大罪』と呼ばれる、クルキアータのカスタム機よ」 「特務に、七つの大罪か……面白いじゃないか」 「ふふ、興味津々ご様子ね。だけど、まだ七機全部は運用してないのよ」 エルザがただ淡々と説明を続ける。 「七つの大罪を扱えるパイロットがまだいないのよね。ダリアちゃんだって、まだ完全に性能を引き出してはいないんじゃないかしら。あの【アスモデウス】だけよ、100%の性能を発揮しているのは」 「そんなことべらべら喋っていいのか?」 「知られたからと言って、困るようなことじゃないわ。それに……あたしが言っていることの全部が、本当だとは限らないわよ」 「分かってるさ」 出会ったときから「ゲーム」は始まっている。ならば、その時点から疑ってかからなければならない。 だが、それ自体がエルザの狙いかもしれない。だから、「確実な情報」だけは携帯電話からインターネット経由で調べてある。 「その上で聞く。あんたは何者だ? いや、聞き方を変えよう。十人評議会のメンバーか?」 これは、正悟からのカマ掛けだ。 何も知らなければ、そもそも「評議会って何?」と聞いてくるはず。それに、ここで「はい、そうです」とも答えないだろう。「違う」と答えたなら、評議会なる存在を噂だろうと何だろうと、多少は知っていることになる。 さあ、どう出るか。 「そう、あたしこそ十人評議会の第四席、『観察者』シスター・エルザよ」 「本当か?」 「さあ、どうかしらね? 仮に、その十人評議会なる組織、あるいは集団が存在していると仮定しましょう。その構成員が、果たして自由に『私はその一員です』なんて自由に言えると思うかしら? これまでにも、『自称評議会メンバー』は何人もいたのではないかしら」 それと、と付け加える。 「仮に坊やは、あたしが『十人評議会って何?』と聞き返すと想定していたとするわ。けれど、あなたが『評議会』の『メンバー』はと聞いた時点で、少なくとも『人を単位とする』『組織だったもの』とあたしは推測出来る。十人評議会という単語に聞き覚えがなくとも、『はい』か『いいえ』で答えられてしまうのよ。その評議会とやらは、質問してきている時点であなたが教えてくれているのだから」 正悟は直感した。この女は危険だと。 「話を戻すようで悪いが、それなら俺が本当はロイヤルガードではなく、ただの一学生に過ぎないかもしれないよ? その理由はさっき、あんた自身が言ってただろう」 「ふふ、よく気付いたわね。あたしと同様に、坊やの言っていることが本当だとは限らない」 「今、この場ではお互いの素性などどうでもいい。それ自体に大した意味はない。見破る術がない以上、憶測だけで話を進めたところで意味はない」 「そういうことよ。だけど、それだとゲームとしてお面白みに欠けるわ。ここからは、あたしが評議会のメンバー、坊やがロイヤルガードと『仮定』して話しましょう」 口先ではそう言っているが、この女は正悟の正体を確信している。なぜなら、ロイヤルガードはシャンバラ王国の公的組織。十人評議会と違って調べれば分かることだからだ。 「実際のところ、地球人にシャンバラへの反発感情はほとんどないわ」 「だとすると、『反シャンバラ』と呼ばれることはないはずだ」 「そう思い込んでいる時点で、あなたは既に踊らされているのよ。地球にあるのは学校勢力に対する反発。それだけよ。学校勢力はあまりにシャンバラに肩入れし過ぎた。挙句、地球には一切目を向けず、パラミタの他国との戦争に学生を送り込む始末。なぜ、パラミタの国家間同士の問題に、地球人がそこまで乗り出す必要があるのか? もっとやるべきことがあるでしょう? そういった声を全て『反シャンバラ』にまとめ上げているのが、あなた達学校勢力なのよ。嘘だと思うなら、新聞を適当に読みなさい。あたしの言葉だけでは信じられないでしょうが、こればかりは事実よ」 「だとすると、俺はその腐った学校勢力の犬ってわけだ。そして学校勢力に歯向かうアカデミーと通じていたとすれば、ロイヤルガードの資格は剥奪され、学校からも追放される。あとは『うちの学生をそそのかした』と言いがかりをつければはい、戦争。となるわけか」 「何にせよ、ウクライナの件は、そっちに戦争を起こしたがっている人間がいることを十分裏付けるわね。事故だろうとなんだろうと、聖戦宣言の手前、地球サイドはシャンバラに宣戦布告せざるを得なくなる。今の緊張状態はある意味理想だと思うけど、十人評議会には『これ以上学校勢力が愚かなことをしないように』、現体制を破壊しなければならないと考えている者だっているわ。もっとも、きっとそいつの裏には個人的な思惑があるのでしょうけど」 「国家単位で見れば衝突を避けるのは難しい。けれど、もっとミクロな単位で考えれば協力し合うことも可能、ということか」 「少なくとも、シャンバラの中でも中立に近い学校と姉妹校協定を結べれば、この学校がシャンバラへの抑止力になれる」 「協定を結んだ学校ごと排除しかねないな、今のシャンバラなら」 「期待はしていないわ。あくまで可能性の話よ。あなたがロイヤルガードなら、それこそ上手く取り計れるかもしれないし」 「ロイヤルガードって言ってもただの公務員だよ。そんなに偉くはない」 実際は軍の左官待遇な上、権限も色々と与えられる身だが、そこは伏せる。 (しかし、敵とも味方とも取り難い女だ) どこまでが建前で、どこまでが本音か一切分からない。 「まあ、あたしとしては戦争になろうが協定を結ぼうがどっちでもいいことよ。どっちに転んでも面白そうだしね」 見透かしたように正悟と目を合わせてくる。 「このシスター・エルザ。誰の敵でも、味方でもないわ。単にこっち側にいるのは、こっちの方が色々と面白いものが見れるから。まあ、たまにこうやって手伝ったりはするけど、基本はただの傍観者よ。その上で、聞いておくけど……」 再び正悟に選択を迫ってきた。 「あなたはどっち側から世界に関わりたい? 『目的』がある以上、あなたは傍観者にはなれないわ。ああ、答えなくていいわよ。坊やが行動を起こせば、それが答えになるのだから」 このまま残るか、それともシャンバラに戻るか。 残ったとしたら次は何をやるか。戻ったとしたら何をすべきか。 幼い姿のシスターは、葛藤する正悟をただニヤニヤしながら見つめていた。 |
||