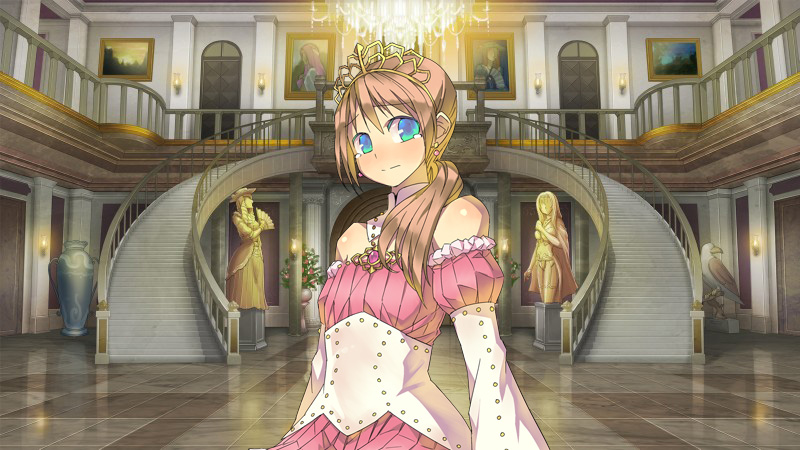リアクション
* 「故障がない……そうか、予想通りだな」 フランセット・ドゥラクロワ(ふらんせっと・どぅらくろわ)は難しい顔をして部下の報告を聞いていたが、ふうと息を吐き出した。 「船の無事は嬉しいが、今度はこういった事態にも対応しなければな」 椅子から立ち上がると船長室を出て、船内の喧騒を後ろに甲板に上がっていく。 あれほどの豪雨が船を手荒に洗ったというのに、今では太陽はさんさんと降り注ぎ船体をせっせと乾かしている。 頬を撫でる風は心地良く吹き、明るい青い空をゆったりと流れる白い雲が清々しい。 「……全く、冒険をしてくれと言わんばかりだな」 厳しい顔を崩して笑いながら、やれやれと言ったようにどっかりと樽に腰かけると、側の袋からおもむろに干し肉を取り出してもぐもぐと食べ始める。 天候は勿論予測していた。急に――本当に前触れもなく急に暴風雨が襲ったのは、探検家の日記の記述から言っても、何らかの力が働いたとしか思えない。 「何らかの力……“何らか”のね。“魔法の”……?」 何もわからない自分を自嘲するように呟いて、食べ慣れた塩辛い肉を咀嚼する。 絶対に故障していないとは言い切れないが、ほぼ確実にそうだろう。機晶石やら船のシステムやらから、携帯まで調子が悪くなっている。おまけに契約者の力が使えない、ときている。 契約者だけでない、さっきメイドが魔法の炎が弱くなってるとかなんとか騒いでいた。 「――何してるのですかフラン様!」 などと彼女が考えていると、運悪くそのメイドのヴィオレッタ……菫の花を頭に咲かせた花妖精が、両手にいっぱいの荷物を抱えて通りかかった。 「お食事は、きちんとテーブルとイスで食べるのです! しかもそんな干し肉だけ! 栄養バランスが悪すぎます!」 憤慨したようにヴィオレッタは言うと、母親のように口うるさくあれこれと叱った。ひとしきり言いたいことを言うと気が済んだのか、 「……ともかく、お忙しいのは分りますが、人前でそんなことしないのですよ」 と言い残すと、荷物を側にいた契約者たちに渡し、またシャキシャキと船倉へ戻っていった。 小さい体に大きな荷物を抱えて往復するのはさぞ重労働だろうと思ったが、それよりも自分の主人がだらしない方がおおごとらしい。 フランセットは口に干し肉の欠片を押し込むと、水を飲み下し、再び立ち上がって周囲の捜索に当たる者たちの処へ向かった。 海軍と契約者の混合部隊――というほど大層なものではなかったが――の中から、一人の美しい女性が進み出た。 「どのような状況でしょうか……?」 フィリシア・バウアー(ふぃりしあ・ばうあー)の問いかけに、フランセットは軽く説明をした。 嵐の状況や沖の方まで小舟を出した結果から、島を中心におおよそ円形に、何らかの力が働いているであろうこと。機晶石の調子は悪いが、帆船でもあり、力が及ばない範囲まで船を出すことができること。 「今は探検の準備を優先させているが、出航しようと思えばいつでもできる状況にしておく」 「それを聞いて安心したぜ」 フィリシアの後から隣に並んだジェイコブ・バウアー(じぇいこぶ・ばうあー)が胸元を叩く。美女と野獣といった感のあるパートナーであったが、同姓であることからも分かるように二人は夫婦だ。 「どれくらい島にいなきゃいけないか考えてたからな……まぁ、食料を無差別に食べ尽くすんじゃなけりゃ、この島じゃ少なくとも飢えて死ぬようなことはなさそうだが」 「皆の食欲のほどは把握しているつもりだが、冒険したら腹も空くからな。あるに越したことはないな」 ジェイコブはフランセットからの報告を待つ間、試しに作ってみた手製の石の刃の出来具合を眺めすがめつ、 「武器がなくなったら、これも使えると思うぜ」 「頼もしいな。では、よろしく頼む」 ジェイコブらは、同行する探検隊から、バッグパックに冒険(キャンプ)用品を詰め込み、水筒やマントロープ等冒険用品一式を受け取ると、林の中を進んだ。 穏やかな気候に、程よい密度の林。葉に日差しが遮られて若干薄暗いが、景色もシャンバラとそう変わらない。陽の登っているうちは(契約者ではない身には)冒険にうってつけの林だった。 ただ唯一シャンバラと違うところがあるとすれば、訪れる者がいないためか、道がないに等しいということくらいだろうか。 リスが木の幹を伝って枝先まで来ると、くりくりとした物珍しげな目をこちらに向けてきた。 「クマ避けの鈴を鳴らした方がいいですかね? それともない方が?」 探検隊の一人がジェイコブを振り返る。 彼はさっきの石の刃に切り出した枝をロープで結びつけた手製の斧を片手に、サバイバルを決め込んだ風だった。確かに武器も有限の可能性があり、銃器もうまく働かない以上、それは大事なことだったが……、 「猛獣が襲って来たなら迎撃する。食べられるようなら肉にするぜ。襲ってこないならそれはそれでいい」 「無理はいけませんわ、いつものわたくしたちではありませんから」 諌めたのはフィリシアだった。こちらは文明的に、紙とペンを持って先程からメモを取っている。 「それに、肉ばかりが食料ではありませんわ」 ほら、と樹上を差した。そこにはパラミタ内海で良く見かける果物や木の実がなっている。幸い「ここだけにしか生えていない奇妙な植物」やらはなさそうだ。 「持っていきましょう」 彼らは木の実を採取し、時に獣を追い払ったりしながら城へのルート周辺を中心に探索し、簡単な地図を作っていく。そして日が暮れる前には船へと戻っていった。 「おい、いいのか?」 城門に入ったかと思うとパートナーが間もなく方向転換したので、ブルーズ・アッシュワース(ぶるーず・あっしゅわーす)は首を傾げた。 「うん、古城への道も確認できたし、話も聞けたからね」 やや勾配のきつい坂を降りながら、黒崎 天音(くろさき・あまね)は見事に人の形に潰された花と、城を探索しに行ったかと思うと外に出されてしまった校長たちの背中を思い浮かべる。 「お城に何かあるのは確かだろうけど、他に人もいるしね。広域に影響があるなら、及ぼすなりの何かが島のどこかにあるかもしれないよ」 「ふむ」 ブルーズは一言返事をするだけで、納得したのかまた視線を落とした。彼は先ほどから腕に付けたHCをいじっていたが、天音がどう、と訊ねると、 「……通信だけではなく、オートマッピング機能もうまく作動しないようだ」 「それでいてパートナー間通話の遣り取りが出来るって事は、『コントラクト』自体に影響する秘宝ではないって事かな。別の目的のものが、僕らの能力の一部に影響してる感じ?」 坂を下りるとブルーズが潔くアナログな手段、つまりペンと紙とを荷物満載のバッグパックから取り出した。天音はそれを受け取って、紙の端にコンパスを置き、中心にさらさらと古城を書き記す。 それから再び歩き出し、よそ見をして小石に躓きかけ、唇の端を上げる。 「それにしても、こういうの新鮮だよね。何か無いなら無いで、この状態で探検も面白そうだしね」 「荷物の殆どを我に持たせているから、そうだろうな」 「ブルーズが心配性なんだよ」 再び、船への道を戻る。道は確保され、木々に印、そしてところどころに海軍の兵士が立っていた。 船の前まで戻ると、天音たちは今度は砂浜を海に沿って歩き始めた。 「裸足で歩きたくなるね。……見てブルーズ、あそこにヒトデがいるよ」 見通しが良い砂浜は明るく、青い海に白く泡立つ波が昨夜とは全く違う顔を見せてくれていた。 天音はここに来る前、「冒険家が日記に残さなかった島の全貌を明らかにしてみるのも、楽しそうじゃない?」と言い、ブルーズは「危険な生物の目撃情報は無いが、あまり気楽に考えるのもどうかと思うぞ」と、お小言を言ったものだが……、天音は砂浜の景色を楽しみ、出会った小川では耐えられずに靴を脱いで足を浸し、 (探検というより、散歩だな) 困らないようにと持てるだけの荷物を持ってきて、如意棒で草むらをつつき、藪を払い、話に聞いていた泉の深水を如意棒で計って慎重にことを進める(そうだ、これは探検なのだ)ブルーズとはえらい違いだ。 「……ふむ、これなら溺れることはそうないか」 「ブルーズ、こっちに誰か来るよ。何だか邪魔しちゃ悪いみたいだから、僕たちはさっきの川の上流でお昼にしよう」 透き通った泉の反対側で天音が手招きするので、ブルーズは大人しく従った。 そして景色のいい場所で、ブルーズは天音が遊びがてら捕った沢蟹や野草、ブルーズが獲った赤い林檎のような木の実でささっと食事を作る。作りながら、思う。 さほど危険なことはないと言えど、狼などもいるだろう。考えてみたら、人間の天音より、ドラゴニュートのブルーズの皮膚の方がずっと厚いのだ。 「ブルーズは真面目だね」 出来たそばからつまみ食いして、美味しいと顔をほころばすパートナー。 「ん、食べないの?」 それを羨ましくも心配にも思いながら、彼は食事の前に、探索や今作った食事のことをノートに書き込んでいた。 「すぐに終わる」 時折試したが、HCは起動したり起動しなかったりした。半周ほどしたが、どうも島の外周の一定距離ごとに強くなったり弱くなったりと、妨げる何かがあるようだ。島自体に魔方陣的なものが施されているのだろうか。 「……おい、我の分は残しておけ」 はっと気づいて、ブルーズは果物のパンケーキの最後の一枚を、自分のお皿に確保した。 「ねぇ、今度はあっちに行ってみましょうよ!」 セレンフィリティ・シャーレット(せれんふぃりてぃ・しゃーれっと)はパートナーであり恋人でもあるセレアナ・ミアキス(せれあな・みあきす)に腕を絡めつつ、引っ張るように歩いていた。 葉を踏むリズムと一緒に長いツインテールが揺れて流れ、横顔が見える。 その顔がとても楽しそうで、同時ににやけているので、セレアナはああやっぱり……、と思うのだった。 「何があるの?」 「泉があるって言ってたじゃない」 「方向が違うような気がするわよ」 「あの岩、面白い形をしてるでしょ? あそこを探検してからよ」 さっきからずっとこの調子だ。セレンフィリティはおよそ教導団の中尉とは思えないような行き当たりばったりさで、セレアナをあちこち連れまわしていた。 しかも中尉になってからやっととれた休みということもあるのだろうが、船の中から今まで、人前であろうがなかろうが抱き付いたり、キスしたりしている。 セレアナが「人前でやめてよ」と言っても、「いいじゃない」と意に介さない。……全く気にしていないわけではなくて――考えていることは理解しているが、別に喧嘩するような悪いことじゃない、互いに愛し合ってるんだから見せつけるくらい、と反省しないだけである。 「そんなに適当で大丈夫なの?」 「適当じゃないわよ、ちゃんと考えてるんだから。あたし、財宝を発見した探検家は古城からは運び出せたかもしれないがその途中で放棄せざるを得なかったんじゃないか……って考えてるの。だからね、放棄するような何かが島にはあるんじゃない?」 テキトーな推測だが、セレンフィリティとしてはそれで構わなかった。 ガサガサと目の前の茂みが動けば……、 「キャー、怪物!」 ぎゅっとセレアナに抱き付けば、彼女は呆れたように前方を指さした。 「……ただの兎よ」 面白そうな岩場に乗ってバランスを取ったり、穴を覗き込んだり、そうこうするうちにやっと目的地の泉に辿り着く。 事前に報告されたように、泉の水は澄み、周囲には気持ちの良い草地が取り囲んでいた。太陽で温まった草の上に素足を置いて感触を楽しんでから、コートを脱ぎ捨てると、セレンフィリティは泉に足を浸した。 まさかこんな時のために水着で過ごしているわけではないが、二人ともロングコートの下はビキニとレオタードだけだ。 「気持ちいいわよ、セレアナも来なさいよ」 言っている側から腰まで浸かり、パシャパシャと水を跳ね上げたり、岸の方へかけてくる。セレアナはやっぱりねと思いつつ、付き合って足を踏み入れたが、 「ほら、早く!」 「きゃっ!?」 手を掴まれたと思ったら、頭まで水の中に引き込まれていた。 水面に顔を出すと、セレンフィリティは無邪気に(いや、邪気たっぷりで?)笑いながら水をかけてくる。セレアナもやめてと言いつつ笑って水をかけ合っていると、つい足が滑り、二人は倒れ込んでしまった。 「……」 セレアナの手の下には、セレンの掌があり、身体の下にはセレンの身体があり……。 「……もう少し、こうしていようか?」 微笑むセレンに答えず、セレアナは手を合わせて暫く二人で水に浮かんでいた。 契約者たちが探索や遊びに励む一方で、古城との道を地道に往復している者もいる。 城やジェイコブたちからの報告を受けた、荷物運びの部隊だ。 その中でもフランセットの船では家畜の飼育を担当しているという獣人の少女は、黒髪をひっ詰めて、物資ではち切れそうなバッグパックを背中に、口を一文字に引き結んでいた。 「……大丈夫ですか?」 同行しているロザリンド・セリナ(ろざりんど・せりな)が声をかけると、彼女はこくりと頷いた。 ロザリンド自身の荷物も、運び続けられるように小分けにしている。小麦粉などの粉や、パスタや野菜の乾物を適度に詰め込んだバッグパックは、それでも想像よりは重かった。これに万一のために盾を加える。しかし何かあっても背負ったまま岩に飛乗ったり、全力で走るとはいかない重さだ。前なら軽々と運べる量なのに。 (力が出ませんね……これが本来なのかもしれませんが) 戦闘という面以外でも、契約者としての力に助けられていたのだなと感じる。 「やはり城が活動拠点になりそうでしょうか。城に何があるかにもよりますが、食料はあまりなさそうですよね」 「ええ、それでも船より城内に拠点があった方が効率がいいもの。その城が……探索者たちをすべて喰らう魔物だったり、暗い過去があって自殺したくなる呪われた城じゃなければね」 ロザリンドは、急に彼女が口を開いたのでちょっとびっくりする。 ……といっても、中に入っていった者たちは危険には一言も触れなかったし、トラップからも殺意を感じられない。 (ジョーク……なんでしょうか) 何日探検するかにもよるが、大勢の人間が滞在するのだがら、あれこれと物入りになるだろう。ロザリンドの提案もあり、食料、生活用品のタオル、調理器具、掃除用具、シーツなどを何往復もして運んでいく。 獣人の少女は時折手からにょきっと長く鋭い爪を出して木の幹に印を付けたり、足で地面を踏み固めたり、蛇を追い払ったりしていた。 ロザリンドは時折鉈で藪を払いながら、道を作っていった。これで往復もだいぶ楽になるし、道に迷うことも減るだろう。 居館の一階で荷物を渡すと、城門の下に腰を下ろして汗を拭いながら、彼女は来た道を眺めて地図を描いた。 「悪いんですけど、今度はトイレットペーパーかその代りになるモノ運んできてくれませんかー?」 城門の上からいつぞやの海兵隊の少年が顔を出して叫んだ。 「あと、ランタンか松明と、油の追加もお願いしますー」 「わかりましたー」 ロザリンドも答えると、再び眼下の林を目指して歩いていった。 太陽はまだ高いが、あれが水平線に沈む頃までにはひと仕事を終えなければならなかった。 |
||