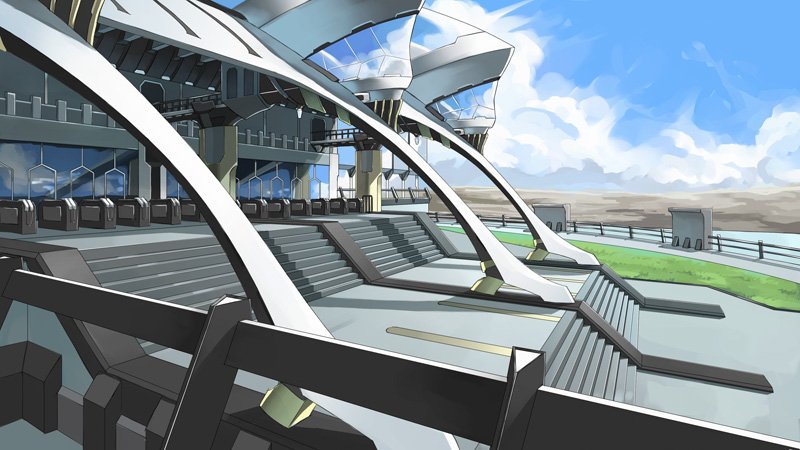First Previous |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Next Last
リアクション
第1章 キノコ狩りツアーは各所開催中? 4
伝説のキノコともなれば、やはり興味を引かれるのはただの冒険者だけではないわけで。
「サンドワームの巣……と言っても、まるで洞窟みたいですね」
「それだけ巨大なモンスターということでしょうか。飲み込まれないように気をつけないといけませんね」
「そ、そんな笑顔で言わないで下さいよー」
サンドワームに飲み込まれそうになるところを想像して震えた茅野瀬 衿栖(ちのせ・えりす)に、ランツェレット・ハンマーシュミット(らんつぇれっと・はんまーしゅみっと)がくすくすと笑った。
「まあ、冗談はこのぐらいにしておいて……サンドワームが巨大だっていうのも、もしかしたら太陽のキノコが関係しているのかもしれませんね」
「食べたら、巨大化でもするのか?」
「太陽のキノコさえ食べれば、ワタシも少しは大きく……」
ランツェレットに問いかけるレオン・カシミール(れおん・かしみーる)の横で、何やら期待を込めた顔で自分の胸をさするアルメリア・アーミテージ(あるめりあ・あーみてーじ)。残念なことに、その胸はあまり目立っているとは言えなかった。
レオンは訝しげにしているが、ランツェレットと衿栖は女性同士の勘でどことなく彼女の意図に気付いたようである。
「まあ、可能性はなくはない、というところですね」
インスミール考古学財団に所属するランツェレットが言うと、妙に説得力のある話であった。そもそも、彼女は今回、考古学財団の依頼でキノコの採取へと赴いているのであった。その途中で出会った衿栖たちと行動をともにしているものの、最終的な目的は太陽のキノコの研究である。
彼女曰く――
「もしかしたら太陽のキノコは、漢方薬というか生薬として使えるんではないでしょうか。あるいは、魔法的な何かが影響しているのかもしれません」
「……だから、あれだけキノコにこだわってたのか」
ランツェレットの説明を受けて、レオンがようやく合点がいったというような顔を衿栖に向けた。図星をつかれた彼女は、どぎまぎしながらなぜか怒ったように反論する。
「い、いいじゃないですかっ。いっつも自己管理がちゃんとしてない人なんですから。か、勘違いしないでくださいね! また倒れられちゃうと私が大変なんですから! 私のために取りに行くんですから」
「私に言ってもしょうがないだろ、それは」
何やら世間一般ではこういうのをツンデレとか言うらしいが、レオンにとってはただの衿栖の暴走である。こうして、毎度のごとく無理やり付き合わされるわけだ。とはいえ、ため息を禁じ得なくとも、最後まで付き合うのが彼らの関係ではあるのだが。
「あ」
自分の関係を思い返していたレオンの耳に、アルメリアの唖然とした声が届いた。
「どうした?」
「あ、あれ、見て」
彼女の指さす方角に目をやる三人。そこには、二、三匹のいかにもなぬめりけを持った生物が、もぞもぞと動いていた。
「あれって、もしかしなくても……」
「サンドワーム、ですね」
つとめて冷静に、ランツェレットがアルメリアに返答した。
資料を確認してその容貌は知っていたものの、実際に本物を目の前にするとその大きさは圧巻であった。それに、なんというかおぞましい風体である。地球のミミズを巨大化すれば、大体このようになるのだろうか。
そんなサンドワームに目を奪われる彼女たちであったが、アルメリアの声が当初の予定を思い出させた。
「衿栖ちゃん、衿栖ちゃん、アレ、アレ使わないと」
「あ、そ、そうでした。えーと…………たらりらったら〜。ふうりん〜」
「……なにやってるの?」
「……お約束かなーって」
地球の某猫型人形の真似をして風鈴を取り出した衿栖に、アルメリアの冷たい視線が注がれる。さすがに恥ずかしくなって、朱色の頬でごまかすように笑う衿栖。だったら初めからやるな、という皆の視線は正論すぎた。
「え、えーと、こほん。では、いきます」
気を取り直して、衿栖は目を瞑って集中し、サイコキネシスを発動させた。
身体の内側から徐々に生気があふれるような感覚とともに、超能力は風鈴を徐々に意志あるものかのよう、動かし始める。それまでかたかたと揺れるだけだった風鈴が、ある一定の力を込められるとともに、ふわ……と浮かびあがった。
そして、風鈴はサンドワームの傍でちりんちりんと軽やかな音を立てた。
地をならすように動いて、サンドワームは風鈴に反応する。どうやら、ランツェレットの見立て通り、サンドワームは音に反応するようだ。いや、正確には、空気の振動であり光の動きというべきか。器官という器官をもたないサンドワームは、圧倒的に振動や光を感じる体表細胞に長けているらしい。だからこその風鈴であり、それを操るということは、すなわちサンドワームの動きをコントロールすることにも繋がった。
「鬼さんこちら〜です」
風鈴がふわふわと揺れながらサンドワームから遠ざかると、彼らは餌につられる魚のように、地を這って動き出した。目的は、もちろん風鈴である。
「さ、今の内ね」
そうしてサンドワームが動いているうちに、ランツェレットたちはその場を過ぎ去った。
あとは、風鈴のサイコキネシスを解いても問題ないところまできて落ち着くだけだ。見つかるかもしれない緊張から解き放たれて、衿栖が笑った
「なんかスパイみたいで面白かったですね」
「出来れば御遠慮ねがいたいところですけど」
くすっと笑ってみせるランツェレット。
これからは、またキノコ探しの再開である。
「伝説っていうくらいだから、そう簡単には見つからないわよねぇ」
「そうですね……何か手掛かりでもあるといいんですが」
「大丈夫、レオンさんなら知ってますよ!」
アルメリアとランツェレット、そして衿栖の視線が、無責任な一言で一点に集中した。
「ん……?」
その先にいたのは、ただ唯一の男レオン。どうやら、その手掛かりとやらが何かないか、レオンに期待しているようである。無茶苦茶なことを言うな、という視線を衿栖に送るが、彼女はなぜか絶対的な自信を持っているようであった。
仕方なく、彼は自分なりの予想を口にした。
「そうだな。太陽のっていうくらいだから、巣の中にに光が差し込む場所があって、そこにわずかな数のキノコが生えてる……とか」
彼からすれば、それなりに推理に基づいた意見を言っているつもりであったが、なぜか女性陣は感嘆したような声を漏らし、やがて呟いた。
「レオンさん、ロマンチックなんですね」
「…………」
言わなければよかった、と彼が後悔したのは言うまでもなかった。
●
犬が相対する別の犬に警戒の唸りをあげるように、高みを目指す者にとって同種の存在というものは、興味を引かれる対象であるとともに、言いようのない高揚やライバル心を抱くものであった。
そして言うなれば、
アシャンテ・グルームエッジ(あしゃんて・ぐるーむえっじ)にとって今こそがまさにそのときであった。
「…………」
目の前に悠然と立つ若者――女性らしくもあるが――は、ユニコーンの角らしきものを加工して作ってる槍を手に、先刻倒したばかりのワームの傍でアシャンテを見返してきた。
出来る。
アシャンテがそう確信したのは間違いなかった。これまでも、目の前の若者とは幾度かともに行動する機会もあったが、改めて彼の実力を知ったのは初めてであった。
そして、敵の急所を狙ったのを贔屓目に見ても、わずか数撃でこれだけの巨体を倒したのは恐ろしくも感じる。敵になったときを想像すると、自然と冷や汗もかくものであった。
無論――アシャンテはそのようなことはおくびにも出さぬが。
それまで、ワームを倒したばかりの殺気と冷厳を放っていた若者は、自然と穏やかな笑顔になってアシャンテに声をかけてきた。
「お久しぶりです。お元気そうでなによりです」
「ああ……そちらもな……
ウィング・ヴォルフリート(うぃんぐ・う゛ぉるふりーと)」
名前を呼ばれて、ウィングは改めて笑顔を浮かべなおした。
「それなりには。ところで、こんな場所でなにをしているんですか? あまり人が訪れるような場所ではないと思うんですが」
「……修行だ。サンドワームと戦って、自分の腕を磨いていた。……それを言うなら、そちらもだろう?」
「私は、ちょっとした依頼です」
「依頼?」
アシャンテのいぶかしい声に、ウィングは自分がここまでやってきた経緯を話した。細かいところはかいつまみ、それでいて要点はしっかりと述べるその様は、まさに考古学者でもある証拠かと思われた。
「周囲の村からか」
「ええ。これ以上、サンドワームが増え続けて地盤が悪くなったら困りますしね。サンドワームには申し訳ないですが、個体数を減らさせていただこうかと」
それを軽々しく言うところが、彼のすごいところでもあった。
自然と、アシャンテの腕が自らの刀に伸びようとしていた。マントの下でうずくその腕は食い止めたものの、心は素直なものだ。
いつか、手合わせを願おう。
二人は、同時に心にそう刻み込んでいた。
First Previous |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Next Last