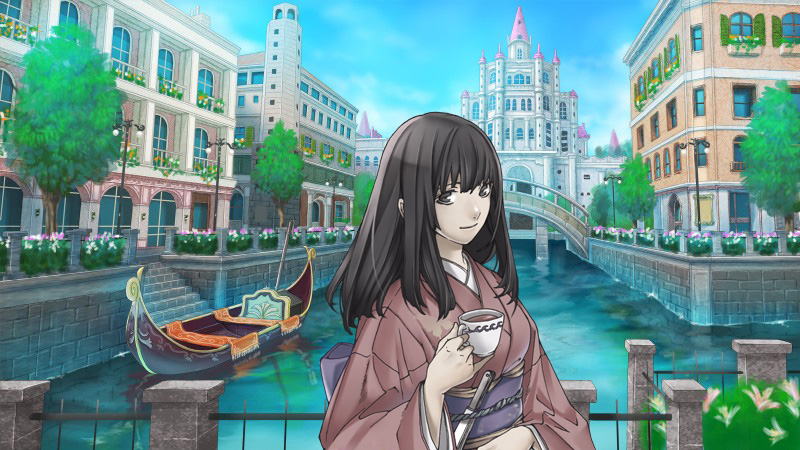リアクション
* 「……つ、疲れた〜」 携帯電話をテーブルに放り出し、思わず両手を上げて大きな伸びをしたレキ・フォートアウフ(れき・ふぉーとあうふ)の前に、 「お疲れ様」 の声とともに、オレンジジュースのグラスが置かれた。 「あ、校長先生。ありがとうございます」 グラスを置いた人物──百合園校長桜井静香(さくらい・しずか)に、椅子に座ったままレキはぴょこんと頭を下げた。 ジュースをちゅるると吸い上げて一気に飲み干す。 それからノートパソコンと分厚い本の山、ルーズリーフ、ボールペンの散らばったテーブルをぱたぱたと積み上げて、テーブルの天板をあらかた発掘すると、立ち上がった。ぴきぴきっと背筋が、膝の裏が伸びる感触は気持ちがいい。 「僕が言えることじゃないかもしれないけど……もう少し、ゆっくりしていってもいいんだよ?」 「ありがとうございます。でも、動いてる方がボクには合ってるんですよね。──チムチム、行こう!」 「チムチムがんばるアル! 校長先生もビデオを楽しみに待っててくださいアル」 「二人とも、気を付けてね」 静香の声を背に、飛び出すようにホテルを出たレキを、彼女のパートナー・もふもふ黒猫ゆる族のチムチム・リー(ちむちむ・りー)がとっとこ追った。 二人が向かう先は、件の百合園女学院周辺だ。 ──2022年1月7日。時間は、お昼過ぎ。 三が日が終わって七草粥を食べ、でも成人式の前で、まだお正月気分がそこかしこのドアのしめ飾りと一緒に残っている、そんな空気の日本と新百合ヶ丘。 学生にとっては、クリスマス後で気分も良いうちに年越しそば食べてゴロ寝して、お年玉も入って、まだまだ続けていたい遊んでいたい、名残惜しい冬休みの終り頃。 「……だからなのかぁ」 レキは商店街を歩きながら、何もない空間──“光学迷彩”で姿を消しながらビデオを構えているチムチム──に話しかけた。 「黒史病なら見たことあるけど、前より患者さんが増えてて、病気が重くなってるような気がするんだよね」 もしかしたらその時よりあの子の力が増大したのかもしれないけどね、とレキは呟く。 あの子。それは原因となった人物のこと。黒史病は、名前こそ病気と付いているが、実はれっきとした(?)魔道書の魔法によるものだ、ということは、前回のパラミタランドで起きた事件で判明していた。 「黒史病にはまだまだ謎が多いアル。しっかり記録するアル。そうそう、生徒会長さんの晴れ姿もしっかり撮影するアルよ!」 「晴れ姿?」 「いつもツンツンしているから、逆にこういう風にはっちゃけた姿を見せれば、百合園だけでなく他校生からも親しみのある生徒会長だと写るんじゃないアルか? ああ、あれも撮っておくアルよ。前回一部女子に好評だったアル」 チムチムのカメラが捕えた映像は、フェルナン・シャントルイユ(ふぇるなん・しゃんとるいゆ)が早速、病気に罹った少年と対峙しているところだった。 「よし、ボクも頑張ろう! 『ああ、この世界はどうなってしまうの?お助け下さい、巫女様ぁぁ!!』」 レキは巫女に救いを求めている一般人のフリをして、巫女王の陣営──ユーフォルビア(に認定されたアナスタシア)へと近づく努力をするのだった。 「残念ですが、今日の私は余り機嫌が良くないのです」 フェルナン・シャントルイユ(ふぇるなん・しゃんとるいゆ)は、素でそんな中学二年生みたいなことを言った。 それは演技か本心か、ただいつも微笑を浮かべているその目に、口元にそれはない。 服も普段着ているあの青い、貴族のような衣装ではなく、セーターと細身のデニムの上から黒いピーコートをラフに着ていた。 「ですから、被害者の方に大変申し訳ありませんが、拒否権はありません」 百合園の本校を訪れた後、彼はパートナーの村上 琴理(むらかみ・ことり)やヴァイシャリーから連れてきた魔術師・技術者らと共に日本やヴェネツィアの建築技術を視察して回ることになっていた。パラミタ内海で暮らす、ハーララという族長が治めるイルカ獣人の部族、彼らの土地が沈みかけているため、それを救うためだった。 それから、姉三人から頼まれた地球土産リストを埋めるため、スケジュールがぎっしり詰まっていた。 イライラの元は、だが、本当はそれではなかった。 今、地球とパラミタで盛り上がっている話題──“新世界”ニルヴァーナへの道のことだ。盛り上がっている原因が、パラミタが滅びに瀕しているからだなどと考えたくもなかった。 (内海どころか、パラミタもヴァイシャリーも滅びる。おそらくその前に、人を救うためにニルヴァーナに移住する。 でも、ニルヴァーナにも住人がいて生活があるでしょう。 俺は地球人をヴァイシャリーに受け入れたかった、けれど……逆の立場になってみれば、俺や大勢の人間がニルヴァーナに行って、受け入れてもらえる確証はありません。そしてそれは、侵略にならないのでしょうか。 移住後だって、地球に琴理さんは、百合園や他校の友人たちは、また今までのように時折は帰れるのでしょうか。地球へ戻るのでしょうか。それとも、契約者たちは故郷と永遠の別れを──) だから、フェルナンには、病気とはいえその本の設定があまりに不謹慎に思えていた。自身の勝手な感情だということを理解してもいたけれど。 「拒否権がないだと? その物言いは、まさか貴様魔族の魔術師──」 「遊びに付き合っている暇がないのです。速やかにおいでいただけないのであれば、こちらを」 いきり立つ少年の目の前に、フェルナンは透明の小瓶を差し出し、蓋を開けた。 すると。すぐさま「うっ」、とうめいて、少年は地面に倒れた。 フェルナンは彼を肩に背負うと、近くのベンチに座らせた。これで一人解決だ。 「……すごいな、それは」 鼻を摘まみながら感心したのは、彼の隣にいたエヴァルト・マルトリッツ(えう゛ぁると・まるとりっつ)だった。 エヴァルトは、フェルナンが瓶の蓋を閉めたのを確認して、やっと手を離す。 「どういう仕組みなんだ?」 「黒史病から目覚めさせる方法は幾つかあります。まずは魔法的な影響を取り除くため、魔法や魔法の薬を用いる方法。ですが、限りがありますし、校長たちのいるホテルに置いてありますので……」 本来ならそこで手当てをして、怪我や後遺症の有無を調べた方がいいのだが、いちいち運ぶ手間もある。 「うむ」 「そしてもう一つ。嗅覚は他の五感と違い、記憶を司る脳に直結すると言われているそうです。たとえば、ある香水の香りがある女性を思い出させたり、パンの焼ける香りで実家の朝食を思い出したりしますよね。そして食べ物の腐敗を調べるときにも使います。つまりそれだけ本来の記憶や本能に近いというわけです。実はこれは」 フェルナンは、手にしていた鞄から一つの缶詰を取り出した。 「一部では化学兵器・戦略物資だと噂の『シュール・レミングス』という、魚の発酵食品です。匂いが半径10メートルの人類の嗅覚を数日間再起不能にするそうで──」 缶の中央に「飛び込むうまさ!」というキャッチコピーが躍っていて、ふわふわ毛皮のネズミ(これがレミングだろう)が魚を求めて、絶壁から海に飛び込んでいる。 「そうか……もっとマイルドな匂いなら使ってみたいが」 「これは如何でしょう」 それは、ドロップの缶詰だった。蓋を取ってガラガラ掌に振るタイプのものだ。表面に、やけに見覚えのある逆三角形をした緑色の小さな虫が描かれている。 「一粒で効き目絶大だそうですよ」 「……カメムシ味……いや、やめておこう」 エヴァルトが首を振ると、では何かあったら遠慮なくホテルか私にご連絡ください、とフェルナンは再び他の患者を探しに歩いて行った。 そう、エヴァルトは旅行で地球を訪れていて、車窓から眺めた新百合ヶ丘駅のホームで、良く知っている顔にものすごく良く似た人物を見つけた、ような気がして。嫌な記憶と共に降り立った新百合ヶ丘駅で、フェルナンから事情を聞かされて。 だから大勢の患者の中で、ただ一人の人物を探していたのだ。嫌な予感に突き動かされて──。 |
||