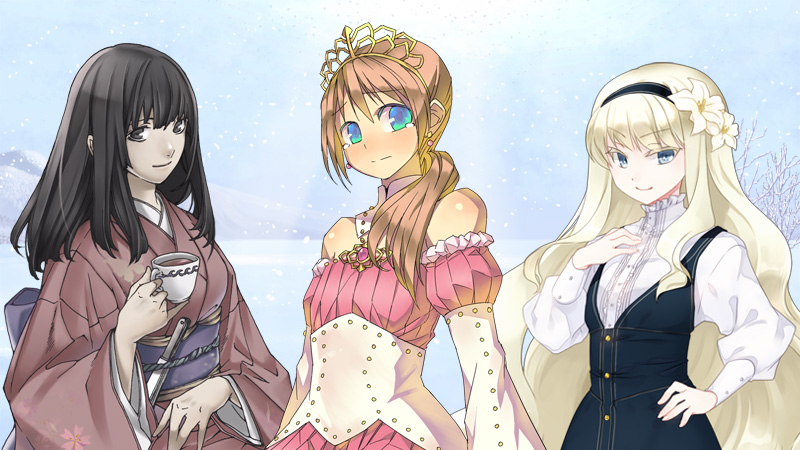リアクション
* 時はさかのぼって――遭難三日目の朝。 山中の山小屋、ロビーの大テーブルの上には、倉庫から桜井 静香(さくらい・しずか)が山小屋の女主人・ベルと共に運び出した食料品や必要だと思われる品々が並べられていた。 「隠してるって思われるのもイヤだしねぇ。もう『いかにも足りない』って感じだけどさ、本当にこれくらいしかないんだよ」 米が一食分、薄力粉と強力粉が少し、野菜幾らかと、バターやオリーブオイルなどの調味料と、それから缶詰少々。 冬で本来山小屋が閉っている時期だ。夫妻二人だけならもうそろそろ買い出しに行かなくちゃといったところで――実際に夫が買い出しに行っているのだが。 急にやって来た、食べ盛りの大勢の生徒たちの食事を賄うには心もとない。 「分けていただいて申し訳ありません」 静香が何度目か頭を下げると、彼女はいいんだよ、と手を横に振った。 「冬山じゃないけど、道に迷って遭難しかけたこともあったからね。それに山小屋やってれば、こういうのは付きものさ。……そっちこそ、もう何も持ってきてないのかい?」 生徒会が少し多めに持って来た行動食も、初日のうちに皆のお腹に治まった。それも一食分にしかならない。 「皆の非常食はもう食べちゃったしね……吹雪が止むまでの『何日か』は、もう三日目だよね」 静香は少ない食料を前に考え込む。 運が良ければ今日明日中に吹雪が止むだろう。しかし、止まなかったら? 「食事はなるべく節約した方がいいな。いざとなったら砂糖を雪に溶かして……」 「食べ過ぎには注意だよ。ビタミンを消費するからね」 「はい。……僕、まだ火があるうちに料理してきます」 ベルに頷くと、静香は暖炉に渡した棒に鍋をかけて、砂糖と塩を溶かし込んだ経口補水液を作っていった。以前、熱が出た時などに作ったことがある。 彼は倉庫に転がっていた水筒に温かいそれを詰めて、外に行く生徒たちに渡していった。 「こんなことくらいしかできないけど、気を付けてね」 「ありがとうございます。校長は、皆をお願いしますね。……会長を特に。何をしだすか分かりませんから」 村上 琴理(むらかみ・ことり)が言うと、静香は笑いながら頷いた。 「無茶しないか見ておくよ。村上さんも、レキさんも、遠野さんたちも気を付けて行ってきてね。絶対に無理しちゃだめだよ」 見送られたレキ・フォートアウフ(れき・ふぉーとあうふ)は静香に元気に手を振った。 「うん、二人一組になったし大丈夫だよ。ボクには“目”もあるしね」 二組の生徒……斧を携えた琴理とレキは薪拾いに、遠野 歌菜(とおの・かな)と月崎 羽純(つきざき・はすみ)は食料を探しに行く。 風圧で重い扉を開けると、冷たい空気が室内にひゅるんと入り込んだ。レキは急いで背中に体重をかけてドアを閉める。 それでも雪が舞い込んでこなかったのは、一昨日からの雪かきと、扉の近くに白い塀ができていたからだった。 フェルナン・シャントルイユ(ふぇるなん・しゃんとるいゆ)は昨日から休み休み、周囲に雪で作ったブロックを積み上げて塀を作っていた。崩れないように“氷術”で補強している。指先がすぐさま凍えそうな寒さも“アイスプロテクト”の加護が少しは守ってくれているようだ。 「風が軽減してくれるといいのですが……専門家ではないのでどれくらい効果があるか」 そう言う顔は寒さに少し青ざめていたが、元気ではあるようだ。 お嬢様学校のレジャーという性質上、男の自分が頑張らなくてはと思っているのだろう。彼は琴理の手元の斧を見て、 「私も行きましょうか?」 と言ったが、彼女は首を振って断った。 「心配しないで、小屋が見える範囲に留めるから。私もたまには力仕事をしなくちゃね。春になったら後輩も入ってくることだし、少し先輩らしくならなくちゃ」 新しい年を迎え、初詣に行き、一年の事を考えて。そして今年は、成人式をした。 今更だけどね、と琴理は苦笑すると、レキを追うように雪の中に足を踏み出していった。 一歩一歩、転倒しないようにと雪を踏みしめて進む度に、分厚い靴底を通して雪の冷たさが足に染み込んでくる。 「今は風が少し弱くなって、良かったですね。吹雪が言い伝えの雪猫の仕業だとしたら、通り道になるほど強くなるということでしょうか」 「そういえば雪の精霊が居るって話だったよね」 レキは“ホークアイ”の両目を雪の中に凝らして、近くの木立を見ながら答える。 「猫の姿か……もふもふしてるのかな。会えたら触ってみたいな。もふもふ〜」 「もふもふ……ですか。もふもふは私も好きですよ。雪の精霊なら、冷たそうですけどね」 「ああでも、この吹雪を起こしてるのがその精霊さんなら、人間は嫌いなのかもしれないね。襲われる可能性もあるから気をつけないと」 耳をすませば、吹きつけてくる風の中にかすかに、猫の低いうなり声が混じっているような気がした。 伝承にのみ知られ、存在するかどうかも不明の雪猫だったが、ベルの言うようにこの山に普段、こんな吹雪が起きる事が無いとしたら……これは木のせいでも幻聴ではなく、本当の声なのだろうか? 「吹雪の中では、こちらも避けようとしても避けようがないかもしれませんね」 「……誰がどういう仕組みでしてるのかは分からないけど、これ見てよ」 レキは指で頭上を示す。 風が少し弱くなって。そう琴理は言ったが、正確にはレキの近くの吹雪が弱まっていたのだ。 「ボクたちを“幻獣の加護”が守ってくれてる……自然現象じゃなくて、魔法的な力でこの吹雪を起こしてるっていう証拠になるんじゃないかな」 そうですね、と琴理は頷く。 話しているうちに木立に辿り着く。吹雪のカーテンの向こうに、ぼんやりと小屋の影が見えていた。 琴理は手頃な木を見付けると、早速斧を振り上げて伐採に取り掛かる。 鈍い手応えと共に木の幹に深い傷が刻まれる。何度かコーンと音を響かせると、細い木は倒れていった。いつもは生徒会室でペンを握っているが、契約者の一人ではあった。 「かまくらで暮らして山小屋を燃やす、なんてことにならないといいですね。せっぱ詰れば、小屋でなくとも机や椅子を燃やさなくてはならないかもしれませんけど……」 「別荘で楽しむ筈が遭難だなんてね。でも一人じゃないし、皆で力を合わせれば生き延びられると信じてる。 ……ボクは薪と食料をこの辺で拾ってみるね。ナナカマドの木でなければ燃えるよね。多分」 レジャーであれば木の種類によって燃えやすいとか、生えにくいから伐らないでおこう、とかできるのかも知れないが、遭難でしかも数日のこと。選んでいられない。 「木の実……とか、キノコ……」 レキは雪の上に転がる枝や、小さな木の実を腰をかがめて拾いながら、周囲の木の洞から、リスだろうか、動物の貯めた木の実を「ちょっと借り」たりして集めていく。 選んでいられない……とはいえ、じっくり見て記憶の中の植物図鑑をひっくり返すのには理由がある。 「うっかり毒のあるのを食べちゃったら、ボクが犯人になっちゃうよ。アナスタシアさんに『犯人は貴女ですわ!』と言われたり……」 二人で想像する。アナスタシア・ヤグディン(あなすたしあ・やぐでぃん)がふんぞり返って、びしっとレキに指を突きつける様を。 「……うわぁ、超ありそうな展開」 「ありそうですね。……あ、この樹は伐らないでおきますね。燃やしたら煙で中毒を起こします。きっと、大量殺人犯にされちゃいます」 「うん、ありそうありそう」 山小屋ではそんな会話に、誰かがくしゃみをしたとかしないとか。 雪山に出て行ったもう一組の夫妻はといえば、雪山デートが遭難という事態になっても、熱々でした。 「“トリップ・ザ・ワールド”! 羽純くん、私にぴったり付いて来てね。絶対に離れちゃ駄目だよ?」 歌菜は、半径一メートルに展開した夢の空間に羽純を呼ぶ。 「ああ、大丈夫だ」 応えた羽純の言葉は、ただ了承しただけではなかった。 展開したフィールドの半径と、吹雪の視界の悪さと。そして羽純を心配する歌菜と……その歌菜の不安を打ち消すように近寄り、手をぎゅっと握る。 「こうすれば離れない」 「だねっ。……皆で絶対に生き残ろうね!」 「ああ」 歌菜の顔に笑顔が戻ったのを見て羽純も微笑み返すと、吹雪の中歩みをゆっくりと進める。 集中が必要な“トリップ・ザ・ワールド”を維持する歌菜の代わりに、羽純は強い風にともすれば飛ばされそうになる歌菜を時に支えながら、“ホークアイ”で周囲を見渡し、進行方向を彼女に伝えた。 「……木立か。薪割りに行ったのはあっちで……俺たちはもう少し南に行ってみよう」 “テレパシー”でレキや静香と位置の連絡を取り合いながら、探索位置が重ならないように木立に入る。入ると、木々に遮られて風が大分弱まったように感じた。 「一旦、解除するね」 断ってからフィールドを解除した歌菜の頭に、銀狼の耳と尻尾がぴょこんっと生えた。 「こっちにある気がするわ」 “超感覚”に導かれて木の根元に行ってみると、木に小さなさくらんぼほどの赤い実が点々と付いていた。とても小さくてみんなのおやつにはならなそうだったが、こんな時だからとてもありがたく思えた。 「それからここも」 歌菜の示した地面を、羽純が威力を弱めた“ショックウェーブ”でざっと吹き飛ばすと、その下には春を待つ草たちの緑が見えていた。 歌菜は思わず屈んで、そっと、白い産毛に包まれた柔らかな葉と芽に触れながら羽純を振り返る。 「こんな寒い中、がんばって実を結んで、生きてくれてる……感謝だね! 有り難く頂戴しましょう」 二人は優しく、木の芽や木の実を摘み取ると、また別の樹を探して、木の実を取っていった。背中の袋に半分ほど溜まったところで、凍えそうになってきたので、二人は道を戻る。 戻ったかと思うと、歌菜は「採って来たよー!」と袋を開けて報告すると、早速濡れた服を脱いで、昼食のスープ作りに取り掛かっていた。 彼女の濡れて重くなったレインウェアを自分の分と一緒に干しながら、羽純はその背中を見守った。自分も冷静なつもりでいても、焦ることもある。 「ありがとう、この木の実も入れていい?」 「これはパンにしましょうか、こっちは入れた方が美味しそうですね」 レキや琴理が、拾ってきた薪の燃え方に悪戦苦闘しながら、キッチンのかまどに火を入れた。 歌菜が明るく前向きだから、羽純も心を穏やかに居られる。食料さえあれば何とかなる、探しに二人で雪の中を進んでいける。そうして実際に、食料を見つけることもできた。 「はい、羽純くんも」 お玉を持った歌菜の周りに、生徒たちがお手伝いや、お腹を空かして集まっていた。 歌菜は羽純のついたテーブルの前に、木の器をことりと置いた。薄い色の、具のあまり入っていないスープ。でも木の実や木の芽の色が鮮やかで、湯気が立って、とても美味しそうだった。 (きっと、何とかなる) 羽純は、できたての暖かなスープを歌菜の思いと一緒に、味わいながら。お腹と心が満たされていくのを感じた。 |
||