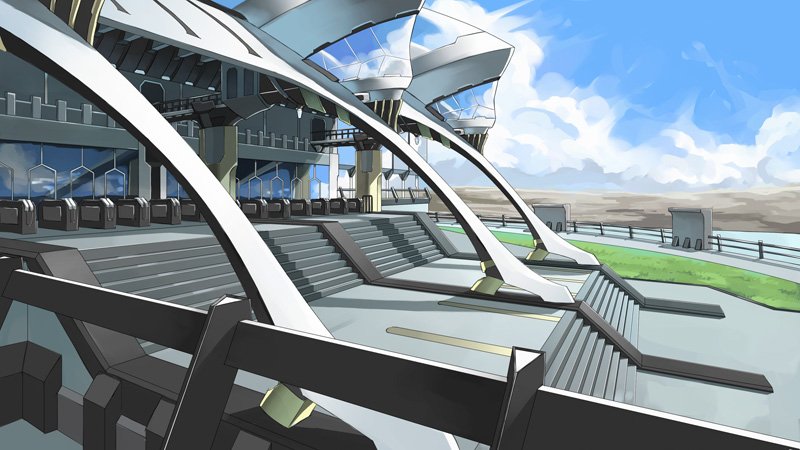リアクション
● 鬱蒼とした森の茂みの奥で、虎の唸り声のようなものを聞く。それから間もなく、不気味な風のようなものが吹いてきたと思ったら、突然、闇のなかに青白い影が浮かび上がった。 肝試しにお化け役として参加しているラムズ・シュリュズベリィ(らむず・しゅりゅずべりぃ)である。 参加者は彼を見た途端に悲鳴をあげ、コースを逃げるように去っていった。その直前に、シャッター音が鳴る。 満足そうに参加者を見届けたラムズの横で、ラヴィニア・ウェイトリー(らびにあ・うぇいとりー)がカメラを確認していた。 「うーん……ちゃんと映ったかな?」 ラヴィニアは、デジタル画面をのぞきこむように見た。 カモフラージュ等で誤魔化したおかげで、写真には恐怖におののく参加者と一緒に、それっぽい幽霊が映っている。 これを上手く使えば、神主紹介の仲介料でも取れるだろう。小銭稼ぎにはなるかな、と、ラヴィニアは意地の悪い浮かべた。 「へぇ、そうなんですか」 隣では、いつの間にかラムズが誰かと話している。 ラヴィニアは彼のほうを振り返ったが、その視界にはラムズしか映らなかった。 「ラムズ、誰と話してんの?」 「え? 見えませんか?」 ラムズはきょとんとして、ラヴィニアを見返した。 「見えるか……って、誰もいないじゃん」 「おや? 変ですね。一緒に驚かそうと誘われたのですが……」 どうやら、いまはラムズにも見えなくなっているらしい。あるいはどこかに去っていったか。 彼はきょろきょろと辺りを見回した。 怪訝そうに、しかし一つの心当たりを感じて、ラヴィニアは聞いた。 「……ラムズ、それってどんな人だった?」 「まだ小さな子供でしたね。ああ、そういえば浴衣姿なのに素足でしたね。鼻緒でも切ったんでしょうか?」 当然、そんな奴は今回の肝試しに参加していない。 そういえば、この森のなかでは様々な幽霊の噂も存在する。そのために今回の肝試しの舞台に選ばれたのだ。 そして和装の少年の幽霊も、噂の一つだった。 (やっべ、マジだコイツ) 彼女は心のなかで毒づいた。 「……いい病院、紹介するよ」 「え、それってどういう意味です?」 ラムズはまったく理解できないようで、首をかしげていた。だが、ラヴィニアはあえてそれ以上、彼に返答することはなかった。 彼女の撮った写真に映る幽霊もまた、少年に見えなくもない霊だった。 ● 黒崎 竜斗(くろさき・りゅうと)は無事に肝試しが終わればいいが、と考えていた。 自分たちではない。主に、脅かす側が、だ。 「ひ……やあああああぁぁぁ!」 「げぶううぅぅっ!?」 行く先々で出てくるお化けにパニックになって、ユリナ・エメリー(ゆりな・えめりー)がサイコキネシスを発動する。 お化けは飛んできた大岩や大木に叩きのめされていた。ただの男性生徒が扮している偽物であることは言うまでもない。そう考えると、不憫なことこの上なかった。 「おい、ユリナ、落ち着けって」 「う、うう……だ、だって、だって……」 ユリナも理屈ではお化けが偽物だと分かっている。だが、理性と本能は別物だ。気づいたら恐怖心が彼女を突き動かしているのだった。 「ううぅ……苦手を克服するのは大事ですけど……こ、こんな本格的なんて聞いてないですぅ」 ユリナと同じように、お化けが嫌いな御劒 史織(みつるぎ・しおり)がぷるぷる震えながら言った。 いっそのこと魔道書に戻って、竜斗に運んでもらおうか。そんなことを考える。だが、彼女は頭を振った。苦手を克服するために参加したというのに、それでは意味がない。 (が、がんばるですぅ) 心のなかで自分を激励して、彼女はぐっと両手を握った。 だが。 「…………くすくす」 背後から近づく不穏な影。 「わっ!」 「きゃううううぅぅんっ!」 耳元で大声を出されて、史織は飛びあがった。ペタンと膝をついた彼女は振り返る。 そこでは、セレン・ヴァーミリオン(せれん・ゔぁーみりおん)がくすくすと彼女を笑っていた。 「うう……セ、セレン様……」 史織はそうつぶやいて、竜斗のもとに逃げ去った。 「いやー、シオは脅かしがいがあるなぁ」 竜斗の後ろに隠れた史織を見ながら、セレンはケラケラと笑う。 「……お前が脅かしてどうするよ」 竜斗はそれを呆れた目で見やった。 セレンは剣の花嫁だというのに、まったくおしとやかの欠片もない。それが彼女の良いところでもあるが、こうしてたまに調子に乗るときがある。じゃれていると言えば聞こえはいいが、ただの退屈しのぎだと、竜斗は分かっていた。 「って、おい史織?」 いつの間にか魔道書姿に戻ってしまっていた史織が、竜斗の手のなかにあった。 彼はセレンにジト、とした、非難めいた視線を送る。彼女は誤魔化すように歯を見せて笑うだけだった。 竜斗は諦めたようにため息をついた。 心なしか、魔道書はツンとふてくされたような空気を発しているようだった。 「んじゃ、先に行くか…………って、ユリナ?」 竜斗は、ユリナがある一角で何かと対峙しているのを見た。 彼女のもとに向かう。そこにいたのは、明らかにお化けと思しき、一つ目の小僧。 ユリナが小僧を見て硬直していた。肩が震えている。 (あ、やばい) そう感じて、逃げ出そうとしたのもつかの間。 「い…………いやああああああぁぁぁ!!」 ユリナのサイコキネシスが、周囲の土や石を巻きこんで、竜巻のような旋風を巻き起こした。 「どあああああぁぁぁ!」 竜斗はサイコキネシスに引きずり込まれ、お化けともどもそこら中に体のあちこちをぶつけた。 唯一、危険を察知して逃れていたセレンが、面白そうにそれを見つめている。 「セ、セレ……たすけ……痛っ! 痛い痛い痛い!」 エレナのパニックが収まるまで、竜斗はしばらく、念力で身体中を叩きつけられていた。 ● |
||