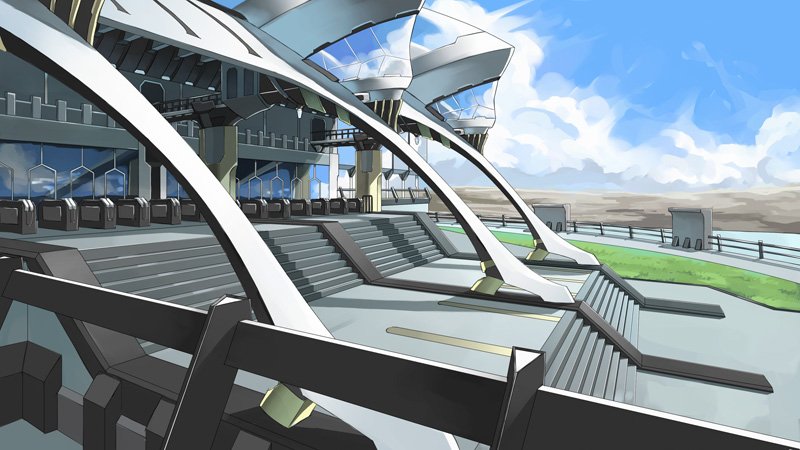リアクション
● 肉体の視覚的差異にどれだけの違いがあろうか。たとえ布切れ一枚であったとしても、それを纏う肉体には、言わば存在そのものが宿っていると言って過言ではない。人は生まれもった姿というものがある。ならば――それを追い求めることは真理であり道理ではないだろうか。理由などあるはずもない。ただ、求める。求めることによって“彼”は、自分という意識を再確認するのである。 ……と、ゆーわけで。 「よぉーしっ! 今回の目標はでっけー鳥だってな! また一歩強くなるために強敵と戦えるってもんだぁ!!!」 白髪鬼という言葉が相応しい、鬼気迫るような精悍な顔立ちの男――天空寺 鬼羅(てんくうじ・きら)は、山岳の中腹で、自分を鼓舞するように叫んでいた。 ……全裸で。 彼曰く、通常裸装備というやつだ。 なにが『通常』でなにが『装備』なのかは分からぬが、本人はいたって大真面目である。彼は何かに気づいたようで、なにやら中空に向けて目を向けた。 「制限時間は50分……上等だぁっ!」 他人が見ればもしもーし、大丈夫ですかぁ? と声をかけたくなること必至――その前に補導されるであろうが――の行動を起こして一人煮えたぎる情熱を吐き出す鬼羅。幻覚か、幻想か、現実か。真実はさておき、どうやら彼の視界には、某――モンスターを狩りまくる、いい加減にもう平和になっただろなゲーム画面が浮かんでいるようだ。 ガタン、ガタン――という音とともに、なにやら猫らしき生物が誰かを運んでいるが、なに、気のせいだろう。鬼羅はそう自分に言い聞かせた。 ということで。 某ゲームよろしくばりに、鬼羅はとりあえず目標を探すべく駆け出した。 「いくぜおらぁ!」 ――全裸で。 ● 山道を走るのは、一機のサイドカー式軍用バイクだった。 ガタッ、ガタッ――と、無骨なフォルムのそれは、山道をまるで悪態でもつくかのごとく揺れながら進んでいたが、それでもまだ普通のバイクよりかは遥かに安定した走りを見せていた。幅と重量のある側車式だからということも、その要因の一つではあるが。 「はあ……行っても行っても木や花や草や葉っぱだらけ……まったく、変わり映えしない風景だよな」 「すぐにそれもなくなります。もうすぐ中腹に差し掛かりますので」 運転席でぼやく、見た目に軽そうな青年に向けて、銃型HCを操る男が声だけを返した。 叶 白竜(よう・ぱいろん)――シャンバラ教導団士官候補生の男は、モニタから視線を外さない。絶えずなにやら画面をいじり、複雑そうな情報にアクセスしている。時々視線を外すことはあっても、それも周囲の様子を確認するためであって決して青年に向けられるものではなかった。HCを操りつつも、手元の手帳や地図になにやらペンで文字や線を書き込んでいっている。 どうやら――山の状況を調べているようだった。 青年の運転を止めさせて、白竜はサイドカーを降りた。明らかに――人の手によるものであろう煙草が棄てられている。半ば嫌悪感を隠し切れない表情で、白竜はくしゃ……と煙草を握りしめた。 それでも、律儀に情報素材として懐にしまうところは実に彼らしい。そんな風に思いながら、運転席の青年は退屈そうなため息をこぼした。 「はあ…………なあ白竜。そんなことちまちまとしたことばっかりやっててもしょうがなくないか?」 「これも仕事の一環ですよ、羅儀。最近頻繁になってきた山岳方面での事件や蛮族問題。実地調査を任された私たちの役目は、山岳地帯全域の実体を明らかにすることです。情報は常に意識へ。……心がけなくては」 白竜の声を聞きながら、羅儀と呼ばれた青年――教導団歩兵科所属の世 羅儀(せい・らぎ)は、自分もバイクを降りて、木の実なんぞを食べていた。 気分はハイキング、といったところか。 「オレはそんな地味な仕事よりも派手にやりたいがねー……山にいる蛮族たちを一掃すれば済むことじゃんか」 「避けられる争いはできるだけ避けるに越したことはありません。いまは調査に専念すべきでしょう」 羅儀は決して納得させられたわけではないものの、なるほどね、とひとまずは頷いていた。別に無理に逆らう必要もなかろう。彼と自分はパートナーだ。なら――パートナーらしく、大人しく木の実でも嗜んでおくか。 再びバイクに乗り込む二人。と――白竜のHCに通信連絡が入ったのはそのときだった。 「どうした?」 「これは……」 ある意味でそれは、最も有益たる情報だったのかもしれない。 ● |
||