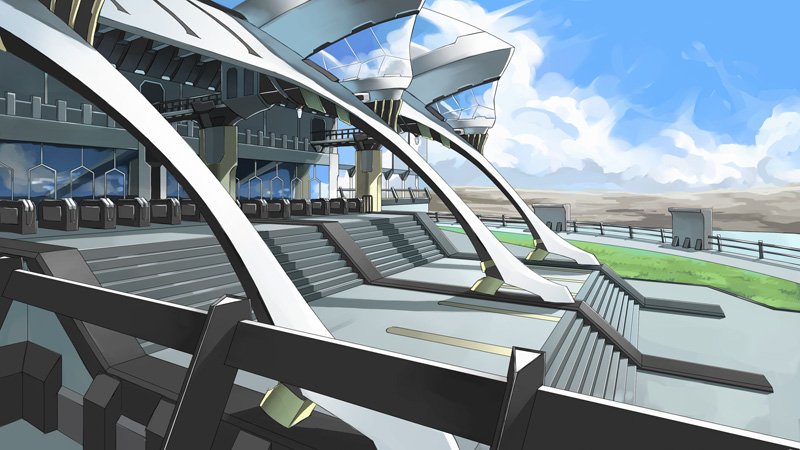リアクション
● 「ほんっと、あんたみたいな腕の良い医者が来てくれて助かった。礼を言うよ」 集落の隅に構えた簡易医療所の中。一人の老人が、年若い女性から傷の手当てをしてもらっていた。 「ははは……私はまだ見習いですから、たいしたことは出来ませんけど」 女性は――九条 ジェライザ・ローズ(くじょう・じぇらいざろーず)は、苦笑しながらそう言った。 とても穏やかな笑みを浮かべる娘だった。黒髪を頭の横で一本に束ねている。瞳の色は青。深い海の色が、老人を優しく見つめた。 本人がいうように、ローズはまだ見習いの医師である。つまり、正式な医者ではない。それでも集落のためになにかしたいという意思があって、こうして村長から許可を得て、簡易医療所を開いているところだった。 窓の外から、楽しげな声が聞こえてくる。 それは子ども声と、ローズにとっては馴染みのあるパートナーの声だった。 「レオンー。あまり激しく遊びすぎて、怪我しないようにね」 「うん、わかってるよー、ロゼ」 獅子の耳と尻尾を生やした少年が答える。 九条 レオン(くじょう・れおん)。ローズのパートナーで、まだ幼い獣人だ。 同年代の子どもたちと、アスレチックごっこをして遊んでいる。大木の枝にくくりつけられたロープを掴んで、きゃっきゃと騒ぎ立てていた。 その様子を見て、よかった……と、ローズは胸をなで下ろした。 レオンは普段から人見知りの子どもである。もともと外界になれてないということもあったからだろうが、ローズと一緒に外の世界に赴いても、彼女の傍をなかなか離れようとはしないのだった。 そんなレオンが、はじめて勇気をもって声をかけた子どもたち。 集落の子どもたちはみんな良い子ばかりで、レオンを快く受け入れてくれた。それがなにより、ローズにとっては喜ばしいことだった。 「ははっ、ケミルたち、とても楽しそうだの」 子どもたちの中には、老人の孫もいるのだろう。 優しげに目を細めて、彼も外の光景を見つめていた。 「ええ、ほんとに」 リーズや、そのほかの契約者が試練から帰ってきたら、その治療もしよう。 元々、そのためにローズはやってきたのである。 ただ、またどこかで暇と時間を得られたら、遊びに来てもいいかもしれない。レオンもきっと友達に会いたいだろう。それに自分も、、この森の中の景色が少しだけ隙になってきたから。 「ん、どうした、お医者さん?」 「いえ、なんでも……」 答えて、ローズは静かに笑みを浮かべた。 ● 「んー、良い景色ねぇ」 集落の隅っこで、女性が絵を描いている筆を止めた。 なめらかな黒髪。垂れ目がちな銀の瞳。はかなげな雰囲気をかもしている絵描きの娘は、ぐーっと伸びをする。 それは、師王 アスカ(しおう・あすか)という名の契約者だった。 彼女は旅に出るときには、スケッチブックとペンを必ず持っていく。絵と冒険をこよなく愛しているのだ。夢はパラミタ一の絵描きになること。 夢はでっかく果てしなく。ただいま各地で自分の作品を展示しつつ、様々な土地を旅しているところだった。 で、集落の風景。これがまた良いという評判で、その噂を聞きつけた彼女はさっそくやって来たというわけであった。 村の戦士たちの修行風景・子供たちの遊んでいる姿・家の外観。まあ、描いていると飽きないものだ。本当は旅から集落に戻ってきたというリーズも描きたかったのだが、ただいま戦士の通過儀礼の最中だという。 彼女が帰ってくるまで、こうして筆を走らせて気長に待つつもりだった。 「でも、そろそろ別のことも面白そうよねぇ」 「……?」 なにげなくつぶやくアスカ。その頭の上で、ちっちゃな影が首をかしげた。 ラルム・リースフラワー(らるむ・りーすふらわー)という、わずか30センチ程度の花妖精の少女である。アスカに懐いていて、彼女の頭の上にいることがほとんどだった。 ついつい触りたくなるような、愛おしい可愛さオーラを全身からかもす少女は、アスカの言葉に興味津々のようだった。 ラルムに軽く目をやって、 「例えば、アレなんかね」 と、アスカは指をさした。 そこにあったのは、なにやら子どもたちにお話を聞かせている老婆と子どもたちの姿。森の薄暗がりの中で、蝋燭の火を頼りに老婆の話を聞き込んでいるようだった。 アスカは絵描き道具をリュックにしまうと、興味をそそられるまま、老婆たちのもとに向かっていった。 そこで話されていたのは、『狼の試練』についての話である。 だが、いかにもホラーめいた話し方で、死んだ魂たちがいるというくだりに、子供らはみな怯えていた。 ははぁ、と、アスカがにやりと笑う。 こそこそっと、彼女は老婆の後ろから話しかけた。 「蝋燭の角度はこっちのほうがいいんじゃない?」 「お、そうかい? こりゃ旅の人、すまんね」 「いえいえ〜。なんだったら、こないだ特殊メイクの練習で作ったこんなマスクが……」 「おお、こりゃ使えそうだ。ひひひっ、これなら子どもたちをもっと怖がらせる事もできるぞ」 「ぬふふ……」 はかなげな少女のなりをひそめ、アスカは老婆と意気投合した。実に楽しげである。 それからしばらくして―― 子どもたちのわめき声や泣き叫ぶ声や絶叫が、森の中にこだましたのは言うまでもない。 声を聞いて、ルーツ・アトマイス(るーつ・あとまいす)が慌てて駆け寄ってきた。 ぼさぼさの乳白金の髪。端整な顔立ちに優しげな雰囲気がある青年。彼の顔は、いまやびっくりして目を見開くばかりだった。 「い、いったい、何があったんだっ?」 「いやー、ちょっと驚かせすぎちゃって……」 苦笑するアスカを見つけて、ルーツは苦々しい顔になった。 「アスカ……また君か……」 彼女がいることで、大体何があったか察したらしい。 それだけ、アスカの普段の行動パターンを熟知しているということである。 はぁっとため息をひとつついて、ルーツは子どもたちに持ってきていたデザートを分け与えた。ひんやりと冷えた、果物の入ったゼリーである。その甘い匂いや美味しさで、少しずつ動揺も引いたようだった。 「ちょっと、なんてそんなデザートなんて持ってるの?」 「予想してたわけじゃないが、何かあったときのためにな。まさかこんなことに使うとは思ってなかったが」 「私もほーしーいー」 「わ、わかったから、物欲しそうな目で見るな」 ルーツはアスカにもデザートを分ける。 ようやく落ち着きを取り戻した子どもたちは、ラルムに興味を持ち始めた。ラルムも、子どもたちをじっと見つめる。 ほんの少し涙目になりながら、 「……いぢめる?」 慌てて、ぶんぶんっと顔を横に振った子どもたち。 それを見て、ラルムはにこっと笑った。 ● リーズが帰ってくる前に極上の料理を用意しよう。 柳玄 氷藍(りゅうげん・ひょうらん)がそう思い立ったのが、数十分前のことである。それから彼女は色々と準備に手を回した。リーズの好みを調査し、何の料理がいいかなーと考える。 そうして考えに考えて至った結論が、肉料理を作ろう! であった。 そんなわけで、氷藍は九尾の狐の背中に乗って、ただいま集落の中の露店を散策中である。 ちなみに狐の正体は、彼女のパートナーである皇 玉藻(すめらぎ・たまも)だった。 黄金色の美しい毛並み。文字通り九つある尻尾。人が乗っても問題ないぐらいの大きさで、実にていよく使われている状態。 「まったく、私は乗り物じゃないんだけどな……」 玉藻は不満げにつぶやいた。 「まーまー、固いこと言うな。それより、どこか良い店はないのか?」 氷藍は笑いながら言う。 ロングの黒髪。黒曜石のような深い黒色の瞳。狐に乗ってることもあって、実に和風のイメージが定着する姿である。 元々は男だったらしいが、今となっては配偶者もいるし、女としての生活を謳歌しているようだった。 「良い店ねぇ……。で、何が必要なんだっけ?」 「特上の肉と、添え物の野菜と、それから香辛料に調味料と……って、玉?」 いつの間にか玉藻の足が止まっている。 しかも、彼女はある一点を見ているようだった。 「なにか気になるものでもあった?」 「ん、あ、いや……」 彼女は歯切れ悪く答える。 しばらく、頭をひねったり、尻尾を振ったりして時間を過ごすと、彼女はついにその場所に向けて歩きだした。 「すまん、氷藍。少し寄る」 「お、おお」 のしのしと歩いていって、玉藻はついにある店の前で足を止める。 眼前にいたのは、グリフォンの姿をした獣人だった。 「もしかしてそこの君、ナウファル君?」 「あれ、玉藻……さん?」 「ああ、やっぱりナウファル君かっ。久しぶりだなぁ!」 玉藻はグリフォンの獣人との邂逅を喜んだ。 どうやらこのグリフォンの獣人、玉藻の旧い友達らしい。名前はナウファル・アサド(なうふぁる・あさど)というそうだ。玉藻いわく、このナウファルという青年は、獣人であるにもかかわらず普通のグリフォンに紛れてくらしていたのだそうだ。 しかし、あるとき置いてけぼりを食らってしまった。 それを見つけた玉藻が、彼に獣人生活のイロハを教えたということだった。 まあ、どういう関係かは分かった。 だが、どうしてグリフォンの獣人が狼獣人の集落に? その疑問は、彼自身が教えてくれた。 店に並ぶ商品を見ればわかるように、彼は商人であって、香辛料を売って暮らしているのだそうだ。長年旅を続けていたが、旅費が底を尽きてしまって、この集落に身を寄せるようになったという――。 なんとも、涙を誘うお話だった。 「ううっ、苦労してるんだなー」 「いえ、それほどでは……」 「おお、そうだ、氷藍。もしよかったら、彼と契約してあげてくれないかな?」 「え」 唐突な話で、氷藍だけではなくナウファルもびっくりしていた。 「これでも商人だしな。ついでに買い物を手伝ってもらったらいいじゃないか」 「ああ、なるほど」 「一理ありますね……」 うなずく二人。 「まあ、俺は構わないかな。その代わり、アンタのしってるとびっきり良い店を紹介してくれよ」 「はい、分かりました。これでも商人の端くれです。任せといてください」 「よーし、話はまとまったね」 玉藻はそう言って締めくくる。 軽く言った話だったが、彼女は内心では安堵しているところだった。このままナウファルがここで身を寄せたまま終わるのは、彼の為にはならないだろう。ナウファルはそれだけで終わるちっぽけな男ではない。広い世界を見るために、契約者と契約するのは彼のためになると玉藻は思っていた。 まあ、それに―― 「ナウファル君を食べれるなら、一石二鳥か」 「ぼ、僕は食べても美味しくないですよ玉藻さん!?」 ぼそっとつぶやいた玉藻の言葉に、ナウファルが驚いた。 別にそこまでストレートな意味ではなかったのだが。玉藻は苦笑いしながら、ナウファルの案内に従って、次の店に向かった。 ● |
||