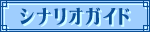 |
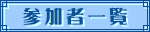 |
リアクション
・会議開始(全校イコン)
プラント内の一室を使い、第二世代機開発プロジェクトの会議が始まる。
こちらは、全校イコンに関するものだ。
「まずは案出しからだな」
声を発したのは、雨月 晴人(うづき・はると)だ。天学生として、この場の進行役を務める。
「ハルトと私、この前、カナンに行ってきた。カナンのイコン、アンズーを取ってきたの。機体を調べた人、古代の匠の技が詰まった名機だって言ってた。今頃、シャンバラで解析されて、量産型を作る準備、進んでるみたい。応用出来る部分あれば、新型の量産機開発に活かせればいいと思うの」
アンジェラ・クラウディ(あんじぇら・くらうでぃ)が口を開く。
「まあ、そのためにはまずデータが出揃わないといけないんだけどな」
今回の会議では、まだ使えそうにない。
「あと、エネルギーコンバーターがあっても、やっぱり量産機は機晶技術ベースの方がいいと思うの。量産や整備がしやすいから」
その辺も、ここでの意見次第だろう。
「各々、どんな機体がいいか考えてきたと思う。順番にそれを説明してくれ」
話し合うために、一人ずつ意見を聞いていこうという流れだ。
「まずは、イコン単体での性能の前に『運用』『拡張』『パイロット』についての考えから述べるが、宜しいか?」
クレア・シュミット(くれあ・しゅみっと)が本題に入る前の前提として、その三つについて言及する。
「『運用』について。イコンを作戦投入するに当たって、『作戦地域までどうやってイコンを持っていくか』という問題がある。基地防衛はまだしも、『攻めていきました、着いた時点でエネルギー切れになりました』では話にならない」
シャンバラにはまだ、学校を含め満足にイコンを整備する場所がほとんどない。ヒラニプラでさえ、設備では天御柱学院に劣るほどだ。
「現状、海京方面では母艦として空母が使われたり、飛行空母の構想もあるようだが、そうなると飛行能力は欲しいところだ。海にしろ空にしろ、母艦が着陸・接岸しないとせいぜい甲板にしかイコンを展開出来ないとなると、移動中が手薄になる。とはいえ、ここで言う飛行の機能は『移動・展開』のために考慮するものであって、必ずしもイーグリットに挙げられるような高速空中戦を企図するものではない」
次に、
「『拡張』について。換装パーツで補えるものは、必ずしも基本性能に組み込む必要はないと言える。現状で手薄なのは水中への対応だが、使い勝手がいいのは空中仕様。換装によって何が補え何が出来ないのかも把握しておく必要があるだろう」
そして、
「『パイロット』について。例えば四人乗りの機体を作って三人乗った場合、二人乗りの機体に二人乗った場合に比べてどうなのか。何人でどれだけ性能を引き出せるのかも検討しておかねばならない」
そこまで踏まえた上で、ハンス・ティーレマン(はんす・てぃーれまん)が全校用イコンへの言及を始める。
「ベースにはコームラントを推します。イーグリットよりは空戦能力は劣りますが、移動・展開は十分と考え、装甲面など水中戦への対応の可能性を考慮しました。性能は機動より装甲重視。取り回しのいい汎用機としてパワーより照準重視が良いかと。搭乗人数は効率次第になりますが、四人搭乗が前提となると厳しいかとも思いますので、二人乗りです」
以上で、彼女達の案出しが終わる。
「飛行能力については、たしかに必須だな」
クレア達の次は、湊川 亮一(みなとがわ・りょういち)が説明を始める。
「第二世代機に必要な要素を挙げてみよう。飛行は出ているとして、量産性、汎用性、そして第一世代機を凌駕する戦闘力。この辺りは必要だ」
特に量産、汎用性についてを念押しする。現在の量産機であるクェイル、センチネルの上位互換となれば恩の字だ。
「俺はコームラントではなく、ベースにはイーグリットを使うことを提案する。現行量産機のクェイルはイーグリットの簡易型だ。強化するなら、元のイーグリットをベースにした方が手っ取り早い」
そこからは具体案に移る。
「クェイルやイーグリット・アサルト開発時のデータを元に、性能を維持した上で構造を簡易化し量産性を確保。さらに、第二世代機用のジェネレーターに換装することによって得られる余剰出力を使い、各部の強化を図る。強化方針は運動性→装甲→攻撃力だ。また、全校イコンである以上、天御柱学院のような正式な訓練を受けたパイロットでなければ扱えない機体となってはならない。初心者が乗ることも考慮に入れ、『敵中で大暴れする機体』よりは『落とされ難い機体』をコンセプトとする。加えて、今後開発される新装備の搭載も念頭に置き、ある程度の拡張性、発展性を確保する。拡張性については先ほども提案があったな。そして生産性確保の観点から、飛行、覚醒能力以外の特殊能力はあえて搭載しない」
初心者から上級者まで、それぞれに合わせて運用可能な機体。それが亮一の提案するものだ。
「機体試案としては次の通り」
と、プレゼン用のスクリーンに仕様が表示される。
機体名:クェイルMk―2
サイズ:M
HP:420
EN:200
パワー:150
照準:140
機動:170
機甲:140
誘爆:8
追加回避:18
追加防御:0
センサー:10
定員:2
移動:空
武装スロット4
アクセスロット2
「以上だ」
亮一の発表が終了した。
「さて、次は私達ですね」
セイル・ウィルテンバーグ(せいる・うぃるてんばーぐ)の番だ。
廿日 千結(はつか・ちゆ)が、彼女とともに設計した図面をスクリーンに投影する。
「私達が考えてきたのは、イーグリット・アサルトをベースとした『四人乗り』の機体です。サイズは一回り大きくなったLサイズで、飛行機能は搭載。スペックそのものは現行のイーグリットより少々性能が上がった程度です。しかし、操縦や火気管制を四人で行うことで、二人乗り以上の性能を引き出すことが可能となります」
万が一、鏖殺寺院が覚醒のような力を使ってきた場合、他校生では苦戦を強いられるのは必至。
だから四人の力を合わせることで補おうというのである。
「デフォルト武装は大型ビームサーベル。カラーリングは白を基調したもので、外装はイーグリット・アサルトの装甲増しのような感じですね」
イメージ図を表示する。
「イーグリットの機動性を殺さないために、背面には大型ブースターを装着しています。拡張性については、これまでの二人乗りイコンの武器との互換性を維持出来るような機構とします。
欠点としては、四人で操縦を行うため各員の連携が必要となり、一定以上の操縦技能を有していないと運用が難しいということですね」
この点が、量産するに当たっての一番のネックとなる。
今のところの意見を考慮するならば、四人搭乗前提というよりは、四人搭乗可の方が検討の余地があるだろう。
「私の番ですね」
志方 綾乃(しかた・あやの)が説明を始める。
「私は、全校イコンへのアイデアとして、『イコンの小型化』を提案します。先程は四人乗りの一回り大きいイコンについての言及がありましたが、それとは別方向からのアプローチであるとお考え下さい」
今はまだ案を出し合っている状態だ。綾乃の主張の本旨は、何人で乗るかということではなく、あくまでイコンのサイズ問題についての言及である。
「現状のイコンの最大の問題は『大き過ぎる』点にあると思います。これによって『ほぼ戦闘用途にしか使えない』『保有運用に潤沢な資金や多数の専門スタッフが必要』といった事態が生じていると思います。そのため、現状の十メートルクラスの機体を、八メートルサイズまで縮小すべきであると考えます。小型化によって調達・整備コストが削減出来るのはもちろんのこと、現状の十メートル級イコンでは実用的でなかった『市街地戦や遺跡・施設内部での戦闘』や『土木作業・人命救助といった民生用途』の他『より多くの地形、特に二階建て一般家屋を目隠しに利用』『現状の輸送機関の流用』など、イコンに新たな可能性を与えることが出来ます」
二メートルの違いは大きい。そうなると問題はどうやって小型化するのか、ということになる。
それを、袁紹 本初(えんしょう・ほんしょ)が話す。
「ベース機としては元々小型で、さらに生産性に優れる『喪悲漢・離偉漸屠』タイプを流用し、そこにクェイルの部材を利用して機体性能を確保するのじゃ。『頭と胴体が一体化した人面ボディ』という特徴的構造も、破損しやすい頭部そのものを排し、センサーを機体各部に分散することで目潰し防止などや合理化を図れるのじゃ。絶対見てくれはダサいがの」
機能性が重要、ということらしい。
「量産可能ならば、徹底的な物量と集団運用で想定し得る多くの問題は解決出来るはずだ。ダサい? それが性能とどう関わりがあるんだ。大荒野や辺境の地の人々も使うかもしれないんだ。見てくれに変にこだわったってしゃあないだろ」
ラグナ・レギンレイヴ(らぐな・れぎんれいぶ)がそっけなく補足する。見た目はともかく、汎用性、量産性に関してもいい線をいっているのかもしれない。
これまでに出た意見を考えるなら、そこに飛行能力を持たせられるかといったことが議題に上がりそうだ。
「おっと、次は俺か」
閃崎 静麻(せんざき・しずま)が口を開いた。
「機体コンセプトは二つ。『発展性の高い量産機』と『イーグリット』と『コームラント』の統合』だ。ベース機には上位互換ということを考え、クェイルを選択したい」
発展性、という点においてこれまで提示された意見と通じる部分がある。
「骨格部分はクェイルに似た形状で遥かに高い強度で再設計。後年の改修やバリエーション機開発でかなり無茶を出来るようにする。長期的な視点も必要だと思ってな。
特殊な機能は採用せず、機構を可能な限り単純化して量産性を高める。イーグリット同様の肩部スラスターを装備、脚部にもスラスターを配置して空中戦に適応。装甲配置はクェイルベースに被弾率の高い胸部等や被弾時に影響が大きい肩部スラスターなどはコームラントレベルでキッチリ強化。
外装はベース機から大きな変化はなし。骨格や装甲の強化に肩部側面スラスターと脚部スラスターのため、全体的に一回りから二回り大きくなると想定。ギリギリMサイズで収まれば御の字、ってところだな。武装は頭部機晶バルカン以外に内臓武装は一切装備しない。初期携帯武装はシールドにビームライフル、ビームサーベル。サーベルはシールド内にマウント、他に腰部両側にも携帯武器用ウェポンラックを設置。背部は機体用途や作戦内容、戦場状況に合わせて複数のバックパックを使いわけられるように接続部を作り、一つの機体で様々な状況に対応出来るようなバックパック交換スタイルを指定」
それにより、機体の拡張性も図れると予想される。
「標準バックパックとしては肩越しに撃つ形式に変更した折り畳み可能な大型ビームキャノン一門、予備のビームサーベル。増えた分の重量に対応するためのスラスターを装備したバックパックも必要になるか」
その設計図を静麻提示する。
ネックとなるのは、やはり機体が大型化することだろう。そこをクリア出来るかが問題だ。
「ええと、私ですか」
次はリース・アルフィン(りーす・あるふぃん)の番だ。クロード・レジェッタ(くろーど・れじぇった)が記した仕様書を目の前に掲げた。
(まったく、クロード君ってば肝心なところの説明を私に丸投げとか……まぁ、別にいいんだけど)
なにやらぶつぶつと呟いた後、説明を始める。
「さて、私達は主に以下の三つのことを追求した機体を提案します。この機体は、クェイルをベースとして考えて下さい」
彼女達もまた――正確にはクロードだが、クェイルベースで考えていた。
「OSのアップグレード及び、サポートシステムの導入。既存のイコンとの装備、部品の共用化。装甲、推力など基本スペックの向上による生存性の高さ。この三点です」
そして、一つ一つについて言及していく。
「一つ目に関しては、イコンの操縦の難解さを克服するため短い時間で機体を不自由なく動かせるよう、操縦をサポートするシステムを導入することにより習熟の早期化を図る、というものです」
「タダでさえ難しいオペレーションを要求され、機体を換えるごとに異なる操縦技術が求められる。今の状態では、イコン操縦に特化した訓練を受けている天御柱学院の人間以外には、酷なものがあるよ。
ああ、続けていいよ、リース」
クロードが補足した後、リースが続けた。
「それと並行してシステム面の見直しを行い、よりパイロットにストレスを与えないようにアップグレードすることにより、イコンの性能をさらに発揮出来るものにする。これにより、ある程度のラインまでなら誰でもイコンを扱えるようになると考えられます。
二つ目と三つ目について。基本兵装はマシンガンとビームサーベル。あとシールド兼用の可動型バインダービーム砲。肩に担いだり、腰部に構えて撃つなどの利用法が想定出来ます。特殊兵装やパーツの部品を今までのイコンのものと共有化することで、コストの削減を目論むものと考えられます。さらに、スラスターや装甲を今までのものより強化することによって、生存率の高さを追求すべきだと提案します。せっかく習熟出来ても、安全性に欠いた機体じゃ、いつ死ぬか分かりませんからね。兵士は生き残ることによって強くなる、ってことです。こんな感じでいかがでしょうか」
「これが採用されたなら、ボクやリースはテストパイロットになる覚悟はあるよ。自分が立案したものだし、自分でチェックするのは科学者の基本じゃないか」
「って、そんなの聞いてないよ!?
あ、あくまで全体の意見がまとまってからだからね、そういうのは」
とにかく、まだ一周してはいない。
「いよいよ俺の番だな」
晴人が声を発する。
「ベースは俺もクェイルを採用すべきだと考えている。最も普及している量産機の一つで、学院の生徒なら覚醒も使えるから、今あるクェイルを全部、F.R.A.Gの第二世代機に対抗できるようアップデートしたい。最優先事項は、飛行機能を持たせることだな。デフォルトで飛べないっていうのはかなりのネックだ。寺院のイコンは全て飛行型、帝国も飛竜に乗った龍騎士だからな。陸と空に対応できればベターだ。
空を飛べてこそ、真の意味でイーグリットの量産型だ。そうなると、必然的に二人乗りになるな。三人乗り以上は、少数で十分だと思う」
それから、武装案に移る。
「武装は改良型アサルトライフルと、イコン用対装甲ナイフ。ライフルは取り回しを重視。移動しながらの射撃に最適で、単発、連射切り替えが可能。ナイフには振動剣の技術を応用。ビーム刃と比べエネルギー消費が少なく、水中でも使える。可能なら対ビームコーティングを施して、ビーム刃を受け流せるようにしたい。寺院のパイロットで、実体剣でビームを斬り裂いたパイロットがいたって聞いたことがあるから、学院の技術でも十分実現可能なはずだ」
それと、と付け加える。
「さっきあったように、専門的な訓練を受けてない者でも扱いやすいように、操縦系の改良も必要だな。理想はロボットもののアーケードゲーム経験者ならすぐ動かせる程度だが……さすがにゲーム感覚ってのは無理があるか」
いくら簡易化したとはいえ、そこまでやれるのなら天学パイロット科が存在する意味がない。
「これは、機体案とは違ったものになるけど」
一通りの案が出揃ったところで、エース・ラグランツ(えーす・らぐらんつ)が口を開いた。
「拡張性という観点から、種族の特性を活かした武器を導入すればイコンの幅が広がるのではないかと思う。基本機体は問わないから、あくまで武装案、ということになるな」
彼に続いて、メシエ・ヒューヴェリアル(めしえ・ひゅーう゛ぇりある)がその意図に触れた。
「せっかく兵器種族があるのだからその特性をイコン兵装にも応用したい、と考えるのは自然なことだよ。剣の花嫁から取り出される光条兵器をイコンで使えるように出来るのならその有用性は大きいかと思う。兵器はその使用目的に沿ってちゃんと兵器として使ってあげなくてはいけないよ」
今ある光条武装は、剣の花嫁をエネルギーデバイスとして機能するものだ。そうではなく、個々の剣の花嫁から取り出した武器を、イコンに反映するという手法を取りたい、ということだろう。
と、いうことでエースがそれを説明する。
「『剣の花嫁がパイロットにいる場合、地球人の使用形態あるいは剣の花嫁の仕様形態の光条兵器をイコンでも使用可能にする』ことが出来るようにしたい。現状での剣の花嫁はただのエネルギー装置でしかない。そうではなく、使用者の任意に形状を選択出来るものとする。それでも、花嫁が媒体であることは同じなので、エネルギーは消費される。時間制限は止むをえないな。仕様時間に関しては、機体を最大四人乗りにすることによって延ばすことは出来るかもしれないが、やはりそれは先の話なので現行の二人乗りで考えていきたい」
「光条兵器のメリットとしては、機晶コーティングを貫通させることが出来る、という点にあるね。任意で斬るものと斬らないものを選択出来るという点は大きく、例えばF.R.A.Gの実体シールドを貫通させることも出来るかもしれない。
あくまで理論的な可能性だけど、対イコンの切り札として、プロジェクトと並行しての開発を提案するよ」
発表しているエース自身は、メシエの言葉を聞きながらやや複雑な表情を浮かべていた。あまり搭乗者までもを、「兵器」として追求し過ぎたくないということだろうか。
実際に、誰もが単に兵器開発のためにここに来ているというわけではない。
これまでの意見には、戦闘以外の用途を見出そうというものもあるくらいだ。
「兵器云々はおいとくとして、光条兵器の特性をうまく使えば、効率よく相手を無力化出来るかもしれんの」
袁紹が相槌を打つような感じで呟いた。
兵器という言葉で、やや硬直した雰囲気を和らげるという意味もあったのだろう。
「とりあえず、ある程度共通したものは出てきたな。それらをまとめると、だ――」
晴人が意見に基づいて、全校イコンに必須とされる要素を挙げていく。
・飛行
・拡張性、量産性、汎用性
・基本的な操作性の簡易化
飛べないイコンでも、戦い方次第で十分活躍の場があるが、それは初心者には難しい。敵が飛べることを前提とした場合、やはりなければならないだろう。
また、シャンバラ全校の使用を考え、量産性に優れていなければならない。また、イコンの生産コストの問題もある。そのため、デフォルトの機体はそこまで性能にこだわる必要はない。
その点を補うための、拡張性だ。パイロットの練度に応じて装備を変更する。それだけではなく、用途に応じての換装も行えるようにすることで、幅広く対応が出来る。それにより、汎用性の問題もクリア出来る。外付けの武装次第では、軍事目的以外での使用も可能となるだろう。
そのときの壁となるのは、イコンの操作性だ。イコンの操縦は、誰でも簡単にとはいかない。特に飛行機能を持つ機体は、持たないものよりも難しいとされている。
さすがに一切の訓練なく、というわけにはいかないが、自動車の免許を取るくらいのレベルにまではハードルを下げたい。
その点に関しては、イコンへのパイロットサポートシステムの導入が提案されている。技術的な問題はあるが、飛行における浮遊感覚の維持は最低限盛り込んでおきたい。
「具体的な武装案なんかは、まだ詰めるのは難しいな。あとは、ベースとなる機体の候補だが……」
量産性の観点からいけば、クェイルが妥当。
ただ、機体の構造の面で不安があるならば、イーグリットやコームラントを再検討し、そこから改めて簡易化を進める必要がありそうだ。
あとは、拡張性を確保するにも、あまり装備がごちゃごちゃし過ぎないようにする必要がある。出来ればベースとなる機体のサイズを縮小し、拡張武装を含めた上でMサイズになるのがベターだ。
挙げられた意見を取り入れながら、基本仕様案がまとまっていく。
もちろん、あくまでも案だ。一度ホワイトスノー博士からのフィードバックを通して、次の段階に移っていくことになるだろう。
武装や搭乗人数などの具体案は次回へ持ち越しとなり、最初の全校イコン開発会議はひとまず終了した。