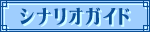 |
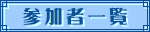 |
リアクション
第五章 〜進展〜
・天学イコン開発会議
「それでは、天御柱学院向けの第二世代機開発案を考えていきたいと思います」
長谷川 真琴(はせがわ・まこと)の進行で、案出しが始まった。
こちらは、全校イコンとはコンセプトが異なるものとなることだろう。
「他校生が、と思われるかもしれませんが提案させて頂きます」
口火を切ったのは、緋桜 遙遠(ひざくら・ようえん)だ。
天学の生徒と意見を交わすことで、より深くイコンを知れるという考えもあってのことだろう。
そのため、あえてこちらで提案を行うのかもしれない。
「先に開発されている第二世代機のブルースロートが防御特化機とのことですので、対になるように攻撃型がいいと思われます。それと、目指すのは既存機からの出力向上ですかね。それにより戦闘力・戦闘時間・覚醒時間の向上を図れるでしょうから。
高出力型を目指すに当たり、ある程度の大型化は仕方ないと思っています。小型化出来た方が色々とメリットは多いでしょうが、最初は単純出力向上を目指した方が技術的な敷居や開発期間という観点から見てもいいと思い、このような意見となりました」
そして、仕様をスクリーンに提示する。
「ベース機体はイーグリットです。攻撃型という観点から見ても、これがベストかと。高機動型というのも攻撃の面では重要ですしね。
搭乗可能人数は三名から四名。高出力化を念頭に入れると、搭乗する契約者の数は多いことを想定した方がいいかと。まだ、パートナーの数が増えればそれだけ出力が上がるという実証データがないため、『上がる』と仮定してですが。契約者二組の四名搭乗、というのもありですかね?」
同じ四人でも、契約者二組の方が出力が上がりそうな感じだ。
「武装は大口径ライフル及び高出力サーベル。高出力を生かした武器ですね。あまりこったものより基本的なものがいいかと。その他、外装やカラーリングに関しては特に希望はありません。有視界戦闘であれば迷彩塗装等も考えられますが、ある程度の見栄えは必要だとは思いますが、その辺はまぁ……芸術性のある方にお任せします」
一通りの発表を終えた。
「確かに、ブルースロートによって防御面の拡充は見込めますからね。攻撃型、という観点は私も同感です」
エルフリーデ・ロンメル(えるふりーで・ろんめる)がプレゼン用の資料を配り、発表を始めた。
「こっちは準備出来たぜ」
リーリヤ・サヴォスチヤノフ(りーりや・さう゛ぉすちやのふ)がスクリーンにスライドを映した。なお、データはフラッシュメモリタイプの魔道書である【戦術情報知性体】 死海のジャンゴ(せんじゅつじょうほうちせいたい・しかいのじゃんご)の本体に収められている。モニターに姿が投影出来るので、補足要員という扱いでもあるのだろう。
それらを使って進めていく。
「私はイーグリットをベースに高機動近接格闘戦に特化した強襲型機体、グライフを提案します。
この機体はインファイトでの一撃離脱による強襲戦法をコンセプトとし、圧倒的な加速を活かし上空より敵機に肉薄し粉砕することを主目的とし設計しました。背部に大型のウィングバインダーを二機増設することによって大推力の獲得、また両手両足を拡張し、さらに腕部には伸縮機構を内蔵します」
CGでモデリングされた黒一色の機体が映し出されている。ラグナル・ロズブローク(らぐなる・ろずぶろーく)が作成したものだ。
実際のカラーリングの案は、増加装甲部分も白にした黒と白のツートンカラーとなっている。それもまだサンプルの段階であるが。
「ベース機のイーグリットに比べ、機体そのものを大型化することによって生じた各部のペイロードを利用し、増加装甲及びスラスターを増設。末端の手部・足部に近接戦闘用のビームクローを標準で装備します。外観上、増加装甲によって増大した分の重量が従来の機動性の阻害になるように思われるでしょうが、増加したスラスターの圧倒的な推進力によりこれを補い、そのまま攻撃の際の打撃力に転化することが可能です」
大型化によるデメリットを、それで是正出来るという。
「まさに疾風怒涛といったところでしょうか。搭乗員は従来通りの二名体制を想定しています。また、従来機を元にしていることによって、メンテナンスの面での負荷の軽減・部品の共有化による従来に近い形での生産性を維持することが可能です」
やり方次第では、武装の互換性もある程度はもたせることも出来るだろう。ブルースロートに防御面をサポートしてもらい、奇襲を行う。
攻撃特化という意味では、ここまでの二案は出力に重きを置くことで共通していた。
「別件になりますが、新型機においてこれまでダークウィスパー隊にて試験運用を重ねてきたレプンカムイの導入に関しても検討頂ければ幸いです」
その運用データを提示する。
端的に言うならば、機体間での連携を行うためのサポートシステムである。全校イコンの話し合いに出てきたサポートシステムの導入に、これが一役買うかもしれない。
「攻撃特化型か。俺も、機動重視の攻撃力特化な機体を推す」
声を発したのは、久我 浩一(くが・こういち)だ。
「現行で使える機体のみがベースになり得るというなら、イーグリットを使うことを提案する。今の意見と重なるが、格闘戦を重視したい。
機体の外装についてだが、肩口のスラスターを取っ払い、腰周りにブースターを回す。脚は少し大型化、カウンターウェイトの特性を残しつつ、地上での稼働時間向上を図る。空中戦がこれまでの主流だったが、地上の地形を活かした戦い方も出来た方がいいと考えている。搭乗人数は従来通り二名、武装はビームサーベル」
プロジェクトは時間との戦いでもある。その中で、可能性を選択していかなければならない。切り捨てるものが出ても、筋は通す。他の意見も合わせることで、よりよいものを目指していくのである。
「機体全体の空力を計算して電力消費を抑える。イーグリットの角二本の形にも、空力上の意味があるだろう。センサー系統の拡充によって、機体全体として電力消費の低減を図るようにしたい。機体のカラーはブルーを希望する」
青と蒼。海と空を連想させるものだ。
「それと、学院の生徒だけが使える『覚醒』についてだが……千里」
パートナーの希龍 千里(きりゅう・ちさと)の意見を仰ぐ。
「覚醒、ですか? まだ私は実機で試したことはありませんが、エネルギーが跳ね上がって行動しやすくなるもの、という認識です。しかし、それでは振り回されやすい」
彼女は自分の身体に置き換えて考えているらしい。
「要するに、集中力を高め渾身の一撃を放つということ。力を理論的に制御し破壊力を増す。拳法の発頸等もそれが基本です。腰と腕の回転力を一点に持っていくこと。
そのために必要なのは、全身の制御と自身の身体をちゃんと理解することです」
どんな力であっても、それを理解し使いこなせなければ意味がない。まして、覚醒は未だ持て余しているパイロットも多いくらいだ。
それを活かすための機体開発への意見を千里が述べる。
「パイロットがそれを意識し、それを機械的にパラメーター化出来れば効率化が図れます。力は無駄に使うものではありません」
覚醒時の状態が今以上に分かるようになれば、「やり過ぎる」こともなくなる。相手を無力化することに特化し、殺さずに済む戦い方を見出せるかもしれない。
もっともそのためには、パイロットが力に溺れないことが絶対条件となるわけだが。
それが盛り込めるかは、次の段階に入ってからの確認となるだろう。
「覚醒を活かす、か。少しここまでとは違う意見になるが、覚醒と通常時で異なる形態をとる可変型というのを私は考えている」
リーゼロッテ・フォン・ファウスト(りーぜろって・ふぉんふぁうすと)が口を開いた。
「ベースとなる機体は、イーグリット。色は白。搭乗可能人数は二名。デフォルト装備はイーグリットと同じく、ビームサーベルとビームライフル。そして最大の特徴となる可変型だが、これは通常時は人型で飛行型、覚醒時に人型ちは違った形態に変化するというもの」
イメージとしては、戦闘機寄りの鳥型、といった感じらしい。
「これは反対でも構わない。この機体の最大の長所は、汎用性と格闘戦能力、機動性の三つを併せ持っていることにある。一撃離脱、奇襲攻撃どちらも行うことが出来る。航空機型になることで、イコンの人型形態では出せない速度を出すことも可能だからだ。
短所としては、高速移動の実現の反面機構が複雑化するため、乗りこなすのが困難だということ。とはいえ、天御柱学院の生徒、ということであればパイロット科での技能が秀でていれば十分扱える代物だろう」
「覚醒のときの……機体と一体化するイメージを持っていれば……難しいことじゃない」
フィア・シュヴェスター(ふぃあ・しゅう゛ぇすたー)が呟いた。
「そうは言っても、特別な機体とならざるを得ないかもしれない。その点は、開発段階に入って、機構を少しでも簡易化出来るかどうかにかかっている」
プロジェクトの趣旨は、決して特別なイコンを開発することではない。搭乗可能な者が多いに越したことはないのだ。
「ここまで、攻撃特化で続いておりますね。それを踏まえた上で、わたくしからも提案を行います」
アウグスト・ロストプーチン(あうぐすと・ろすとぷーちん)が説明を始める。
「敵地への強襲・強行突撃・殲滅攻撃・駆逐を目的とした単独運用可能な重火力、高機動力特化イコンの提唱を促すものでございます。タイプは『強襲機動型イコン』、試作機の名称は『パンテール・ド・シャッス』
計画に用いるベースとなる機体はイーグリットでございます。搭乗定員は従来通りの二名。火気管制と操縦の分担を行うことで、機体制御問題をスムーズに解決するものとします。本機の大きな特徴は、四枚の大型バインダーにあります。それ自体あシールドとなったり、大出力スラスターを担い、バックパックのような収納・搭載力を有しております。この形状から設計段階での愛称は『鬼灯』となりました」
続いて、武装案に移る。
「想定中の本機の武装は、頭部に二十五ミリバルカン砲を二門、バインダーの収納部位に専用ビームサーベル二本、サイコキネシスで誘導可能なミサイル、アサルトビームランチャーなどです」
レイヴン以外で、超能力を機体に反映出来ないことをどうやら知らないらしい。とはいえ、言うのは勝手である。
「この火力は敵施設の強襲・殲滅を目的したもので、一対一での戦闘においても第二コンセプト『駆逐』に適うだけの重火力・高機動力を目指しております。本機はイーグリットのポテンシャルから次代の戦闘スタイルを塗り替えるつもりで、発案致しました」
イーグリットベースのため、空と陸での戦闘を想定されている。
サンプルは純白の機体が映し出されたが、実用化になったら黒鉄色で考えているらしい。
「装備を充実させたり出力を上げたりするには、大型化は避けられないみてーだな」
佐野 誠一(さの・せいいち)が声を発した。
「とはいえ、俺達の考えもここまでと似たようなもんだ。仕様については、手元の資料にある通りだ。イーグリットをベースにして、搭乗人数を三人に。基本武装はビームサーベルとアサルトライフル。飛行型であることに加え、ある程度の水中耐性を持ち、ハードポイントシステムを採用。機動性増加のためにスラスターを増設。見た目は人間型のままだな。そこに拡張用のハードポイント接続がある感じだ。カラーリングは青。コンセプトについては……真奈美、頼む」
誠一に促され、結城 真奈美(ゆうき・まなみ)が説明を始める。
「目指すコンセプトは、高火力と高機動の実現です。瞬間火力による敵の制圧とそれをより確実にするための機動力。イーグリットをベースとしたのはそのためです。搭乗者の増加を盛り込んだのは、より確実な期待制御を行うためです。仮想的はF.R.A.Gのイコンです。基本的に海京の地理的要因から飛行機能は外せず、万一を考え水中耐性を持たせることを盛り込んであります。
ハードポイントシステムの採用はイコンを戦場に応じた武装で送るためと、基本武装での長時間稼動を目的とします。基本性能の伸張は既に見込めていると思うので、それを活用する方向でまとめてみました」
「あと、可能ならば教導団がイコン開発に使った技術をこちらで使わせてもらえればありがたい。あちらさんの稼働時間の長さは魅力的だからな」
飛行機能を持たない分、そちらにエネルギーを回しているのかもしれないが、それでも天学に比べ倍近い稼働時間を誇るのは、目を見張るものがある。
学院のイコンは高性能だが、稼働時間が短いのがどうしてもネックとなる。国軍としても、自国の戦力に繋がるなら、協力はしてくれそうなものだ。
「補足でハードポイントについてだが、追加武装、機能としては大型ビームキャノンやレールガン、追加ブースターやエネルギーパックみたいなものだな。それによって、高火力・高機動などのモードをパイロットの性質に合わせて選択しやすくしたつもりだ」
機体そのものはシンプルにし、カスタマイズすることで広い状況に対応する。
「拡張性の高さは、シャンバラ王国用イコンの会議でも重要だってことで挙げられてたな。参考までに向こうの方では、クェイルベース、拡張性・量産性・汎用性、飛行機能、それと操縦システムの簡易化、ってのが仕様として盛り込むべき内容ってことになった。
整備科としちゃ、機体がシンプルな方が整備がしやすいし、武装やパーツも規格が揃っていれば、それだけで余計な手間が省ける」
クリスチーナ・アーヴィン(くりすちーな・あーう゛ぃん)が言った。やはり、拡張性については懸念している者が多かったらしい。
「ここまで、学院用イコンはイーグリットベースで話が進んでいますね。
現在、学院のイコンは接近タイプのイーグリット、射撃タイプのコームラントと、それを元にした超能力タイプのレイヴンの三種類四機が存在します。レイヴンについて、まだ詳細にご存知ない方もいるかと思いますので説明しますと、『ブレイン・マシン・インターフェイス』というシステムを使って、機体とパイロットの脳をリンクさせ、制御を行う機体です。端的に言うと、イコンとパイロットの一体化を促し、操作性を向上させ、さらに脳波を読み取ることで超能力を機体外へ出力する――超能力による武装を使用可能なイコンです。理論上の性能では、覚醒も併用することによって第一世代を遥かに凌駕するとなっています。
しかし、一.五世代でありながらまだテスト段階であり、通常起動では安全ということになっていますが、まだ謎の多い機体です」
そのため、それを第二世代機に使うにはリスクが大きい。しかし、適性さえあれば第二世代機と同等以上の力を発揮出来る可能性を秘めた機体である。
「それと、先程リーゼロッテさんが可変機を提案されましたが、レイヴンと同時期に開発され始めた一.五世代機が、水空両用の機体であるとの情報です。こちらは、コームラントがベースとなったようですね。アウグストさんの意見にあったバインダー型の外装が可変機構として働く、となっているようです。機体は一回りサイズが大きくなってもいるようですね」
真琴の手元には、整備科長から渡された資料がある。既に数機、その可変一.五世代機は海底で運用が始まっているらしい。まだ公に出来ない理由があるらしいが。
「では、私の方からも第二世代機案を出させて頂きます。ブルースロートが防御特化なので、やはり他の方同様、攻撃に重点を置いた機体にすべきだと考えています。
本来なら、ブルースロートの元となった【ナイチンゲール】の姉妹機としたいところですが、そのデータは入手出来そうにないので、イーグリットないしコームラント……機動性の維持、という点も踏まえ、イーグリットでしょうか。あとは覚醒のデータを活用して、より効率のいい運用システムを組むことでしょうか。覚醒についても、オンかオフしか出来ない状態ですので、『半覚醒』のような状態に持っていったりと出来るようになればと思います。
武装については、第一世代機との互換性を持たせて、利用出来ればいいですね」
これまでの意見をまとめるなら、イーグリットをベースにし、機動性を活かした攻撃特化機、という方向になる。
「他、イーグリット以外をベースにしているなど、案のある方はどうぞ」
異なる意見があれば、それも参考になるだろう。
「流れを切るようだけど、私は水中機を提案するわ」
荒井 雅香(あらい・もとか)が説明を始める。
「先日、エリュシオンが攻めてきたとき、向こうは水中でもある程度戦えるようになっていたわ。天御柱学院にも水中用イコンがあってもいいと思ってね。一.五世代がどんな機体かは気になるところだけど、私としてはキラー・ラビットをベースにした動物型の機体もいいかと思う」
もちろん、一つ機体案だけが採用されると決まっているわけではない。彼女の意見もまた、通るかもしれないのだ。
まだ明かされない可変機が水中で活動しているというのなら、今後はそちらで活躍出来る機体というのが求められるのかもしれない。
「水棲生物のような姿が活動に適しているかもしれないわね。なんの生物かは、まだ検討中だけど。ワニとかかしら?」
動物型だが、どことなく変形しそうな感がある選択だ。
もしかすると、例の機体も動物型と人型で変形する機体なのかもしれない。あくまでも想像ではあるが。
「あと、色はブルー。水中だから、迷彩塗装としてね。
例の機体がもっと分かればいいんだけど、ベースがコームラントってことは、水中でも砲撃寄りなのかしら? それならば、高速機動型の方がいいわね」
水中で戦える高速機動イコンは、未だどこの勢力にも存在しない。
あるのかもしれないが、少なくとも運用されてはいない。
彼女の提案は、それまでのイーグリットベースの機体案とは別のコンセプト案として、記録される。
「あの、いいかしら?」
次に口を開いたのは、アウリンノール・イエスイ(あうりんのーる・いえすい)だ。
「私も水中仕様はあっていいと思う。エリュシオンは龍騎士が主戦力とはいえ、ヴァラヌスを増強してきてもいる。なので、こちらにも水中機の備えがあってもいいかと」
水中仕様そのものは、あっても困るものではない。
「ベースには、薔薇の学舎のシパーヒーを推すわ。まだ未知数だけど、もしかしたら学院のイコンよりも上かもしれない。それと、機体は小型化して搭乗人数を一人にする方が、効率的ね」
一人乗りと言い出した時点で、それが出来ないということは彼女以外の全員が分かっていることだ。
加えてレイヴンの話が出たときに、謎の多い機体を使うのはリスクが大きいといったニュアンスがあったのに謎の多いシパーヒーを挙げた時点で、それさえも聞いていないと分かる。
そのため、プロジェクトにあたってアウリンノールの意見には何の意味もない。
「とりあえず、機体案は出揃いましたね」
学院用イコンの案が大体出たところで、必要な要素を挙げていこうとする。
方向性としては、
・高機動、高出力の攻撃型
・イーグリットベース
を前提として、装備や仕様を検討していくといったところだろう。
他、生産性や整備のし易さというのもポイントになる。
パイロットに関しては二名で当面は考え、バリエーション機として三人、四人のパターンも視野に入れる、として考える。
あとは、拡張性の観点がこちらでも関わってきそうだ。
「武装案等、他にありましたらどうぞ」
「質問宜しいでしょうか?」
オリガ・カラーシュニコフ(おりが・からーしゅにこふ)は気になっていたことを尋ねる。
「ブルースロートの電子戦機としての仕様、分かりますか?」
「電波による、一時的な機体制御への干渉、という風になってますね」
第二世代機の開発プロジェクトなら、電子戦も可能なブルースロートへの言及を行っても大丈夫なはずだ。
ベトナムで、試験導入された寺院の機体を改造した電子戦機に乗った者として、提案を行う。
「天御柱学院パイロット科オリガ・カラーシュニコフより『第二世代機開発プロジェクト』における電子線装備に関して以下の通り提案致します。機体制御への干渉は、かなり有効な機能かと思いますが、それだけではまだ不十分なように思えますので」
考えてきたことを伝える。ここでの発言は記録されるため、ブルースロートに関することは後でホワイトスノー博士にも伝わることだろう。
「一つ目に、光学迷彩を施された敵機体及び施設発見のために電磁スペクトル発信機能の強化。二つ目に、秘匿性を高めるために電波、赤外線を吸収する特性を持つ特殊塗料を使用。そして三つ目に、通信妨害への抵抗力を高めるために、通信機能の強化です」
その理由に触れる。
「一つ目については、敵基地発見時に光学迷彩解除に時間がかかり、敵イコンの襲撃を招いてしまいました。あれ以降、基地や機体に光学迷彩が使われているのを見たことはありませんが、敵が隠し玉として持っている可能性は高いです。二つ目については、ブルースロートは防御能力の強化を謳っていますが、最大の防御は敵に発見されないことにあります。そのため、ステルス性能の強化が望ましいかと。三つ目については、ベトナムでの遭遇戦時、通信遮断が行われたため、別小隊とのスムーズな連携が行われませんでした。新型機は隊長機としても使用が考えられるため、小隊機及び他隊長機との連携は必須です。そこで、通信妨害時の復旧力を強化することが望ましいと考えました。以上ですわ」
ブルースロートもまだ試作段階であり、いくらでも改善可能な機体だ。
別の第二世代機を考えるのが、今回の会議の議題の中心ではあったが、彼女はブルースロートのことを疎かにしてはいなかったのである。
「駒鳥は色々な音を奏でます。音は波です。電磁波も音波も同じく波です。新機体も様々な波を奏でる機体とすれば、学院のために藪の木々の上から賛美歌で祝うでしょう」
ヒー、ウィル、シング、ア、サーム。
夜明けを謳う鴬が、元の機体だ。
それを受け継ぐのが、ブルースロート。
今後は、その機体がこれから開発される機体を守り、これから開発される機体もまた、前に出てブルースロートを守るという戦い方になるのかもしれない。