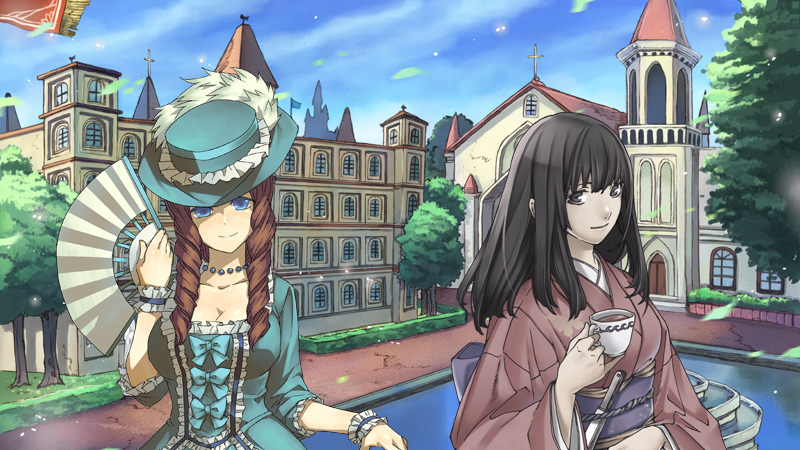リアクション
* ──その話を語る前に、一人の青年とドラゴニュートの話をしておこう。 夏の日はすぐ高くなってしまう。手をふいに止めて、きらきらと輝く日差しに負けることなく煌めく白い船を眺めながら、 「そろそろお茶会が始まる頃かな? 皆頑張ってるんだろうねぇ」 黒崎 天音(くろさき・あまね)はのんびりと言った。 エアコンの効いているだろう船内とは違い、ここは暑い。じりじりと焼けそうな素肌に羽織ったパーカーが、潮風をはらんで翻る。白い砂もあと数時間もすれば、素足で歩くには痛く感じるだろう。 けれどあの中で行われている交渉の方がむしろもっと熱いだろうことは、天音には分かっていた。 ここは言葉の銃弾も微笑の盾もない。代わりに──ビーチボールが降ってくる。 ばふ。……ぽてん。 ビーチボールが天音の側頭部にあたって、砂浜に転がった。 自分の勝ちだというように、ボールを投げたサンドドルフィンがひれをぱたぱたさせた。 他の二匹サンドドルフィンもきゅーきゅー鳴いて、潜ったり飛び跳ねたり、天音をはやし立てる。呼応したように海を泳いでいたパラミタイルカもまた、波の間を高く跳ねた。 「……急によそ見をするな」 「ああ、ごめんごめん」 パートナーのブルーズ・アッシュワース(ぶるーず・あっしゅわーす)に叱られて、天音はビーチボールを拾い上げると、ちょっと早いけどお昼にしようか、と声をかけた。 「む、もう昼か?」 投げたボールの代わりに浮き輪に腰にはめ、ブルーズは残念そうな顔をした。いかつい黒い鱗に、水着と浮き輪の取り合わせ。 天音は泳ぐ気満々なパートナーに弁当の後でねと言って、先に歩き始めた。後をブルーズとイルカ、それにパラミタペンギンがてこてこと追う。 彼らの頭上に広がる優しい青色は、太陽に近づくにつれて何処までも突き抜けそうに青く蒼く、白く湧き上がる雲とのコントラストが鮮やかだ。 空の色を映す海は穏やかに静かで、太陽の光を水面に反射させ、時折水平線の彼方からやってくる波が鏡面を揺らしていた。 左手を見れば、明るい草地と深い森の緑。 どこまでも続きそうな海岸に、緩んだ白い波が静かに打ち寄せては洗う。ビーチサンダルの足元を少しぬるい波が浚っていく。 ここには何もない。目の前にあるのは海と空と森の青だけ。耳には波と、天音たちが踏み鳴る砂だけ。 人はいない。草地から続く海と空に迫り出した崖に立つ古代の住居跡の白く折れた柱が、ここかとうに忘れ去られた場所であることを示していた。 天音も、ラズィーヤに景色の綺麗な場所を教えて欲しいと聞いて知った場所だ。 立てておいたビーチパラソルの下にもぐりこみ、シートの上に二人して座る。 天音とブルーズがお昼にするのを理解したのか、食事を求めてペンギンたちがイルカの跳ねる海へと向かう。イルカの頭には、やっぱり連れてきたスクィードパピーが一匹ずつ海上の散歩を楽しんでいた。 「本来なら食事にされているだろうにな」 「ブルーズは心配性だねぇ」 海岸に咲くカモミールの香りが心地よく、ブルーズが開けたピクニックバスケットから漂う美味しそうな匂いが食欲を刺激した。 「何で卵焼きがこんなにあるの?」 おにぎりやおかずの他に、卵焼きだけが入ったカゴを開けて、天音が首をかしげる。 「砂糖と塩とどっちが良いか散々迷ったのだが、両方作ればいいだろう、と思いついた」 「それはいいアイデアだね……ところで」 そして、天音の視線の先を辿って、ソレに気付いたブルーズは慌てて彼らの方に向かっていった。イルカの頭から、スクィードパピーが消えていたのだ。 よくよく見ると、イルカの口の間から、透明な足が垂れている。 「ああっ! こら! ぺっしないか、ぺっ!」 イルカに向かって身振り手振りで口を開けようとするブルーズは、尚ものんびりとから揚げを口に運ぶ天音に抗議の声をあげた。 「やはり捕食者と共にするのは間違いだぞ!」 「……からかわれてるだけだと思うな。ほら」 「何を……」 向き直ったブルーズの前で、イルカが口を開けていた。その中でスクィードパピーが、元気そうに二本の触腕を振ってぴこぴこ跳ねている。 がっくりとうなだれるブルーズ。 天音は携帯を取り出して、そんな彼らを画面に収め。 海岸はまだしばらく静かで、不審な人間や船の姿もない。 「本当に唯のバカンスになりそうだね」 天音は呟いて、夏の日の一コマを友人たちにもお裾分けすべく、メールを送信するのだった。 |
||