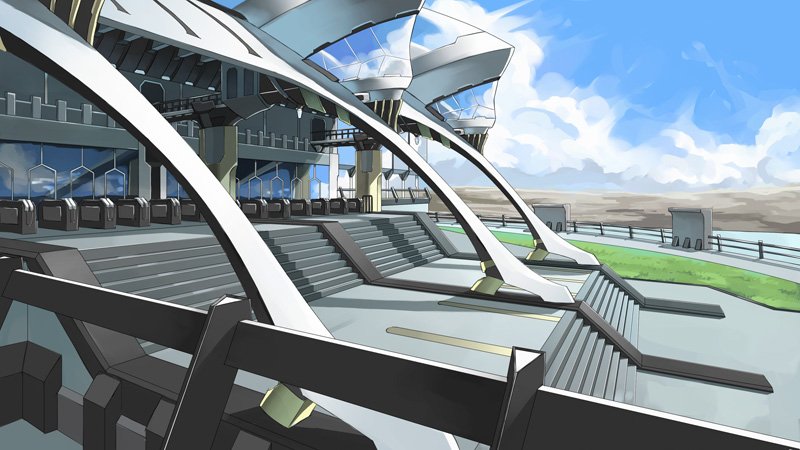First Previous |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Next Last
リアクション
第2章 隠された思惑 3
標高高き山岳の空――一機の小型飛空艇が、まるで観察でも行っているかのように辺りを旋回しつつ浮遊していた。
「それほど人を襲う事がない怪鳥が発掘作業の妨害ねぇ……何か裏があると考えてもおかしくないだろうな」
「ですね。でも……イルマンプスの巣があるのは確かですから、あながち嘘というわけでもないようです」
飛空艇を操縦する閃崎 静麻(せんざき・しずま)の呟きに答えたのは、レイナ・ライトフィード(れいな・らいとふぃーど)だった。二人は極力鳥や獣を刺激しないようにゆっくりと旋回しながら、イルマンプスの巣がある頂上の洞穴を見下ろす。
巣の前には一機の飛空艇が着陸していた。……味方の飛空艇だ。静麻たちが上空から巣と、その付近の炭鉱を観察している間に、イルマンプスの巣そのものを調べているのである。
大した変化もない山岳の風景。半ば退屈そうに静麻はあくびを噛み殺すが――その視線だけは、絶えず炭鉱の数と位置を把握するに努めていた。
「妙だな」
と、ふいに呟かれた声にレイナが振り向いた。
「え? なにが……ですか?」
「……見てみろ」
怪訝そうに首をかしげた彼女に、静麻が顎をしゃくった。それが示すのは、山岳のいくつかの炭鉱地帯だ。発掘が行われているのであろう洞穴がいくつか確認できる。
「炭鉱……ですけど、それが?」
「よく見ろ。イルマンプスが発掘を妨害しているとして、あれだけ離れている位置にある現場に、わざわざ手を出すか?」
「それは……」
ない、とは言いきれない。しかし、可能性の問題として捉えるならば、本能的にそこを襲う可能性は低いと言える。生存を邪魔するほどでなければ、動物の本能は防衛意識を持ったりしないからだ。仮に興奮状態にあったとしても、刺激するような距離にあるわけではない。
そんなとき。考え込んでいた静麻の腕がわずかに震え、電子音が鳴った。
「クァイトスか」
装着していた籠手型HCのモニタを展開させると、そこに周囲のマップ情報とこちらからは把握しきれない炭鉱の位置が光点となって表示された。単身調査を行っていた機晶姫、クァイトス・サンダーボルト(くぁいとす・さんだーぼると)が送ってきた情報である。
と――視界の端で、ブースターの加速音とともに上空を飛行するクァイトスの姿が見えた。ドッグファイトさながらに加速をそのまま旋回している。一瞬だけこちらに翠玉のような視覚素子を向けると、無機質な電子音を鳴らして飛び去っていった。
「働きもんだな、あいつは」
「感心してる場合じゃないですよ。それで、マップはどうなんですか?」
「やっぱり、クァイトスの調べたデータも視認できる範囲とさほど変わらんな。俺の推測が正しかったら……もしかして」
静麻はそれ以上口にすることはなかった。あとは……情報屋の情報次第か。あくびを再び噛み殺して、静麻は自動操縦に任せたままごろりと寝転がった。レイナの呆れた視線が注がれる。
――なに、負けるものか。俺は寝るぞ。
そんな夢見心地の中で、寝返りを打ってふと……静麻は思った。
「難儀なもんだよな、人も動物も」
「……?」
ぽつりとそんなことを呟いた静麻を、レイナは不思議そうに見つめていた。
イルマンプスの巣は、洞穴の吹き抜けに作られたものだった。まるで卵の頂点を割ったような形をした洞穴の奥。恐らくは巨大なイルマンプスが、その吹き抜けを利用して巣まで降りてくるのだろう。自然が生み出したものか、はたまたイルマンプス自身が破砕したものかは分からぬが、吹き抜けから巣まで降り注ぐ陽の光が、どこか幻想的な雰囲気を生み出していた。
はじめにたどり着いたときはその光景に驚いたものだが――それよりもなにより、巣に残っていた卵と雛の姿に、エヴァルト・マルトリッツ(えう゛ぁると・まるとりっつ)たちは驚嘆した。
「イルマンプスの……子供か?」
「うっわー! 可愛いー!」
「ちょ、ちょっと美羽っ! 無闇に触ったらダメだってば!」
羽根も生え揃っていない、淡い毛並みをした三匹のイルマンプスの子供に、小鳥遊 美羽(たかなし・みわ)が目を輝かせて近づこうとする。パートナーのコハク・ソーロッド(こはく・そーろっど)は、そんな彼女をなんとか引きとどめた。
イルマンプスに見つからないようにブラックコートやベルフラマントなど装備を整えてきたのはいいが……どうやらそのイルマンプス自体はまだ巣に戻っていないらしい。餌でも取りに行っているのだろうか?
と、訝しく周りを見回すエヴァルトの傍で、佐々木 弥十郎(ささき・やじゅうろう)が耳を澄ますような仕草をした。
『弥十郎……どうやら、イルマンプスはしばらく戻ってこなさそうだ。先ほど北西のほうに飛んでいくのを確認した』
耳朶の奥――脳裏との狭間で揺れるように聞こえた声。精神感応で話しかけてきた兄、佐々木 八雲(ささき・やくも)の声だ。
「兄さんから連絡。イルマンプスは北西のほうに飛んでいったって……」
「そうか……しばらくは時間が稼げそうだな。それにしても……やっぱり、イルマンプスはこの子供たちを守ろうとしてるんだろうか?」
エヴァルトはイルマンプスの雛たちを見下ろした。銀髪の下の表情が、わずかに曇って見える。
「そうかも……しれないね」
弥十郎はそれに逡巡しながらも同意した。子供たちを守ろうとしたイルマンプスの母性本能が、近づく者を襲うという行為に繋がっているのかもしれない。
兄の八雲と精神感応の特訓をしていた最中で事件の事を聞き、エヴァルトたちと合流した弥十郎。この依頼を受けた張本人であるコビアと直接に顔を合わせたわけではないが……子を守ろうとしている親を無残に退治してしまうのは、いささか躊躇われるものがあった。
それは、どうやらエヴァルトたちも同じようだ。
美羽はイルマンプスの子供たちを指先でつつくようにして、彼らと戯れていた。まだ幼い子供たちは、甲高い鳴き声をあげて楽しそうにはしゃいでいる。
「うはー、可愛いー」
「あーあー、もう……」
コハクは呆れながらもほほ笑んでその光景を見守る。すると、美羽が何かに気づいた声をあげた。
「あれ……この子?」
それは一匹の幼鳥だった。他の二匹に比べて元気がなさそうなそれの身体をよく見ると、淡い毛並みの中に赤い何かが見えた。それは――
「これって……血!?」
美羽の声に気づいたエヴァルトたちは一斉に幼鳥のもとに駆け寄る。ただでさえ巨大なイルマンプスの子供は、人間の子供と同じ程度の大きさだ。それが幸いしてか、怪我をしているということはすぐに分かった。
「どけぃ」
すると――後ろからくぐもったような声が聞こえてきた。振り返った美羽たちの間に割って入って、フードを目深くかぶった魔道書の化身が顎で誰かを促す。いつの間にか魔道書の傍にいた倦怠感を漂わせる男が、静かに手をかざした。
「さて、治療……って言うんでしょうか? これは」
「良いから早ぅやれ。親鳥が戻ってくると厄介じゃ」
手のひらから大地へと繋がった生命の奔流。あふれ出てきた祝福の力が、穏やかな光となって幼鳥を包み込んだ。光に包まれて、穏やかに目をぱちぱちとさせる幼鳥。それを見下ろして、魔道書――シュリュズベリィ著 『手記』(しゅりゅずべりぃちょ・しゅき)は満足げに薄くほほ笑んだ。
彼女のそんな表情に気づいたのかどうか……ラムズ・シュリュズベリィ(らむず・しゅりゅずべりぃ)は微笑する。
「鳥、嫌いだったんじゃないですか?」
「ああ、大嫌いじゃよ」
手記はまるで自分に言い聞かすように、答えた。
「大嫌いでなければ、目をかけてなどやるものか」
答えになっているのかどうか――さりとて、目の前の光がその答えなのかもしれない。鳥に効くかどうかは分からなかったが、祝福の力は幼鳥の傷を癒してくれた。
美羽はほっと安堵の息をつく。
「ありがとう、手記さん」
「ふん……お礼はこやつに言うんじゃな。我は大したことはしとらん」
美羽にお礼を言われて、手記は早々に翻った。ラムズが代わりに、美羽へと苦笑する。
「すみません……少々気難しい方で」
「ううん……ラムズさんも、ありがとう」
「いえいえ」
優しい笑みを返すと、ラムズは手記を追って翻った。
常にフードを被ったままの不気味な印象を受ける魔道書であったが……もしかしたらそれは、彼女のただ一つの側面でしかないのかもしれない。美羽は、そんなことを思った。
と――轟然。
「な、なにっ!?」
獣の足音と咆哮が聞こえたのは、そのときだった。振り返った美羽の前に、人影が降り立つ。天井の吹き抜けから直接降りたのであろう。銀光の下の双眸は左目だけを失っており、残された右の緑玉の瞳が、巣へと飛び込んできた獣たちを見据えていた。
「兄さん!」
「弥十郎、おとりになれ」
振り返った八雲が弥十郎に告げた。戻ってきて早々、何を言い出すのか。
「えっと、兄さん。おとりになってどうするのかな」
「決まってるじゃないか。ひきつけろ」
「えっ、またー?」
どうやら過去にも度々あったことらしい。
渋々と、獣たちの前をわざと目立つように跳躍する弥十郎。獣たちの標的は、彼に認識されたようだ。一気に、咆哮とともに地を踏み散らす。
「エヴァルト、美羽、やれるか!」
「ああ、任しとけ!」
「いつでもー!」
その隙に、八雲は機関銃を構えていた。彼に呼応して、エヴァルトと美羽もそれぞれの武器を構える。ワイヤークロー、それに氷柱の両手刀“六花”だ。
弥十郎を追いかける獣三匹。こちらに気づかぬ間に、エヴァルトのワイヤークローがその動きを防いだ。つながれたワイヤーに絡まった獣たち。その上空へと、飛び上がる美羽。
「いっくよー! エヴァルトさん!」
「よし……来い!」
エヴァルトが腕を振り上げると、ワイヤークローに捕まった獣が宙へと放り投げられた。向かう先は――美羽の刀身である。
「はああああぁぁ!」
一閃。そして閃光。剣線が獣を切り裂くと、陽光に煌く氷結の輝きが飛び散った。間を置いて、獣の体躯が真っ二つに断ち切られる。しかし、まだ二匹残っている。
「捉えた!」
轟く八雲の声。機関銃の銃口がワイヤークローに捕まった二匹の獣を捕らえると――横合いから銃弾の嵐が降り注いだ。いくら外殻が硬くとも、機関銃の銃弾をこれだけ浴びせられて無事で済むはずもない。血を噴き出した獣は、二匹ともども横転して動かなくなった。硝煙を吐き出したままの機関銃。
ようやく構えを解いて、八雲たちは互いを見合わせた。
「……こう、獣が襲ってくるのを見たんじゃ……なかなかここから離れるのも躊躇われるな」
「ああ……しばらく残って様子を――」
そのとき、エヴァルトの銃型HCに反応があった。誰かからの連絡のようだ。表示したモニタに映った名前は――
「静麻……?」
それは、周辺を調査しているもう一組の仲間の名前であった。
●
山岳の歩み慣らされた山道で……一人、鮮やかな花の前に
アリア・セレスティ(ありあ・せれすてぃ)は屈み込んでいた。いや――違う。
彼女は一人ではなかった。よく見れば、小人のように小柄な花妖精が一人、彼女の肩に乗っかっているではないか。衣服という概念が花妖精にあるのかどうかはわからぬが、彼女は純白の花弁のような形をしたドレスを纏って、ふわっと綿のように軽い体でアリアの肩を移動した。白き花弁の妖精――
モニカ・クラウズ(もにか・くらうず)にとって、アリアの肩はどうやら自分の定位置のようだ。
そんな愛くるしい花妖精にくすぐったげな笑みを見せたアリアは、花たちに向けてようやく本題を切り出した。コビアの受けた依頼――つまりイルマンプスの退治についてだ。
「……少しでも良い解決策を探したいの、お話を聞かせて?」
かいつまんでイルマンプスのことを伝えたアリアは、花たちに向けて話を聞いた。
草木と花たちは、その場を動けぬ生命体でありながらも、終始山岳の様子を見つめ続けている観測者でもある。一房一房の情報量は少ないものの、それが集まったときには人には見えぬであろう大地の脈動や絶えず見つめ続けてきた光景の詳細を伝えてくれる。
草木と花の心……そんな目に見えぬ存在を感じ取ることが出来るアリアだからこその、自分なりの調査方法だった。
それに、モニカもいる。彼女は久しぶりに自分の同種たる存在に出会えたこと、それにアリアの力になることも嬉しいのか、にこやかに笑顔を浮かべていた。
「お花さん、草木さん、お話ししましょう♪」
アリアだけでは聞き取れぬ植物たちの声を、モニカは普段の会話とさして変わりない様子で聞いている。うんうんと頷き、時にはほえーっと驚嘆し、そして――依頼の裏かもしれぬある一端を垣間見た。
それは、イルマンプスには子どもがいるらしいという話だ。花たちもそれを直に見て確認できたわけではないようだが、山岳の上層部から伝え聞いた話だと、十中八九間違いないということである。
子ども……ということは、イルマンプスはそれを護ろうとして村人を襲っている? 決してそれが許される行為であると肯定するわけではないが――無下に退治されるのは、避けたい。アリアはそう思った。そして、思考が己の道を導いたときには、すでに体は動き出していた。
――山岳の頂上を目指して、全身全霊をかけて疾走する。ときに聞こえるのは、モニカの懸命な声だ。
「お姉さま、そちらの道を!」
道中の草木たちと対話し続ける彼女は、そこから得られる情報で山頂までの最短ルートを導き出し、アリアに伝えてくれる。アリアは、モニカの指示に従って迷うことなく突き進んだ。
「お願い、間に合って……!」
思わず漏れる願いの声。それは――たとえ人の命でなくとも、怪鳥の命であろうとも護りたいとする、彼女の決然とした意思に他ならなかった。
First Previous |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Next Last