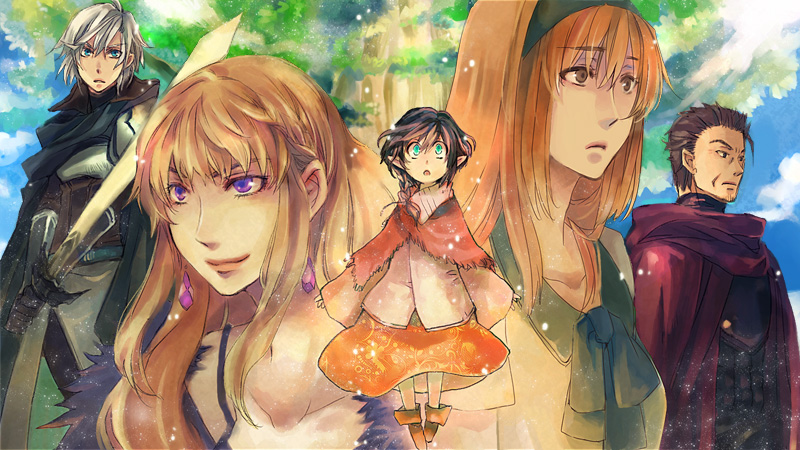リアクション
かの国は一度滅び 空飛ぶ船も、それを操る者も失われ 今や忘れ去られて久しいが 初めて自らの力で空へと臨む者へ、先達は必ず その言葉を贈ったのだ 「ウラノスの加護があるように」と 第1章 Giant ――ッガ、ガガッ…… ピー――――・………… ――――ヲ、補足、解析 レベル1/10ニテ発信 ピ、ピ、ピ…… レベル1/100ニテ発信 ピ、ピ、ピピッ ――反応アリ ……ヲ、送信―――― ◇ ◇ ◇ 女王殺害計画の一端を担った罪で、国軍身柄預かりとなっている巨人族の男、アルゴスの元を、リカイン・フェルマータ(りかいん・ふぇるまーた)とパートナー達は訪ねた。 教導団のイコン格納庫が一棟、アルゴスを収容する施設となっている。 「話をしたいだけなら、テレパシーでいいでしょうに……」 シルフィスティ・ロスヴァイセ(しるふぃすてぃ・ろすう゛ぁいせ)に引きずられる形となったリカインは、そう零した。 以前シルフィスティが、アルゴスにテレパシー爆弾攻撃して疎まれていることなど露知らないのだった。 そんなリカインの頭の上では、ギフトのシーサイド ムーン(しーさいど・むーん)が静かにカツラとなっている。 「それ、まるで私がカツラを必要としてる頭みたいで嫌なんだけど……」 溜息をつきつつ、外すことは最早諦めている。 二人の後ろを、未来人のケセラン・パサラン(けせらん・ぱさらん)がふよふよとついて来ていた。 「巨人族の遺跡のことなら、何も知らんぞ」 面会の開口一番、アルゴスはそう言って、建前の用は終わってしまった。 「行ったことないの?」 「無い。 俺がその遺跡の話を聞いた時には、既に『遺跡』と呼ばれていた。 遺跡ということは、誰も居ないということだろう」 彼はかつて、仲間を探していた。 始めから居ないと解っている場所になど、行く気にはならなかったのだ。 「でも秘宝があるかもしれないんでしょ。仲間に関する手がかりだってあるかも」 「考古学知識など、俺にはない」 シルフィスティの言葉に、アルゴスは言う。 何千年も生きていて何を言っているんだかと思ったが、むしろ交渉の余地というものだ。 「だったら、調査ついでに、どさくさに紛れてそれっぽいもの持って帰って来ようか?」 シルフィスティはにこりと笑う。 「別に、引き換えに何か教えろとか言わないから!」 アルゴスは、呆れ返った顔をした。 「お前の知りたいことなど、何も知らんぞ」 「またまたぁ」 「……ちなみに、アルゴスくん、その遺跡のこと誰から訊いたの?」 リカインが問うと、ああ、とアルゴスは頷いた。 「ドワーフ達だが」 「ドワーフ?」 「その遺跡を造ったのは、ドワーフらしいからな」 「……それはまた」 人よりも大きな巨人族と、人よりも小さなドワーフ族との対話を想像して、リカインは肩を竦めた。 「ところで。ひとつ試して欲しいことがあるのだけど」 そう言うと、リカインは徐に戦闘態勢をとった。 面会に立ち会う教導団員達が身構えるが、アルゴスが彼等を制す。 リカインは、アルゴスに『滅気・龍気砲』を撃った。 「……物騒な女だな」 正面から受け止めたアルゴスは、リカインの背後で剣呑な様子の教導団員を見やりつつ、言った。 「感想を聞きたかったのよ」 「感想?」 「実戦向きじゃないのはわかってるんだけど。溜めの間無防備になるし。 純粋に、威力としてはどうかしら。使い物になる?」 「それは、受ける相手次第だな」 「そうね、今のところ、フィス姉さんに直撃“しちゃう”ことが多いかしら」 そもそも使用の目的は、暴走するシルフィスティを粛清……もとい、援護射撃する為のものだ。 「ならば、充分だろうよ。その女も痛い目を見てるんじゃないのか」 「痛い目をみて、懲りてくれればいいんだけどね……」 そうじゃないから苦労なのよ。 リカインは深々と息を吐き、アルゴスは成る程と言いながらくつくつと笑った。 |
||